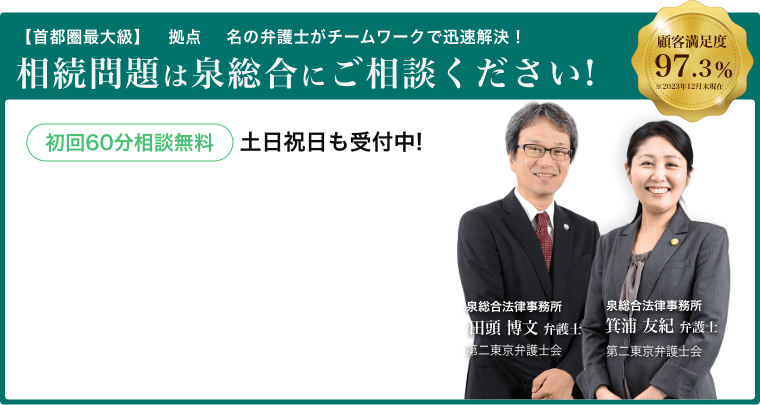公正証書遺言の遺言能力の判断基準|遺言作成時の注意点

遺言書の方式にはいくつか種類がありますが、確実な手段として公正証書遺言が選択されることは多いです。
もっとも、公正証書遺言であれば絶対に有効というわけではなく、遺言者の遺言能力(意思能力)が欠けていると判断される場合には、公正証書遺言であっても内容が無効になる可能性があります。こうなると、相続人間でトラブルが発生しかねません。
よって、公正証書遺言を残す際には、遺言能力(意思能力)についても理解しておくことが必要です。
今回は、公正証書遺言と遺言能力(意思能力)との関係や、公証人がどのように遺言者の遺言能力を判断しているのか(判断金順)、公正証書遺言の有効性の立証方法などを解説します。
1.公正証書遺言とは?
(1) 公正証書遺言の方式
公正証書遺言とは、公証役場において、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成する遺言書のことをいいます。
 [参考記事]
公正証書遺言に欠かせない公証役場・公証人とは
[参考記事]
公正証書遺言に欠かせない公証役場・公証人とは
公正証書遺言の方式は、以下のように定められています(民法969条)。
- 証人2名以上の立ち合いがあること
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、公証人がこの筆記したものを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させること
- 遺言者および証人が筆記の正確性を承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
- 公証人が、その証書の方式に従って作成した者である旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
公正証書遺言にしておくことによって、遺言書の紛失や偽造を防止することができます。
また、法律の専門家である公証人が作成してくれる遺言ですので、形式不備による無効のリスクを軽減することができます。
 [参考記事]
公正証書遺言とは|メリット・デメリットや作成の流れ、費用
[参考記事]
公正証書遺言とは|メリット・デメリットや作成の流れ、費用
(2) 公正証書遺言が無効になるケース
公正証書遺言は公証人という法律の専門家が作成する遺言ですが、そのような遺言でも無効になる可能性は0ではありません。無効になる可能性があるのは以下のようなケースです。
- 遺言者の遺言能力がない場合
- 不適格な証人が立ち会った場合
- 方式(口授)の違反
特に、公証人は医師ではありませんので、遺言者に意思能力があるかどうかを正確に判断することはできません。
(もちろん、一目見て遺言の内容を理解することができない程度に認知症が進行しているような人であれば、公証人が公正証書遺言の作成を断ることもありますが、認知症の程度にもさまざまなものがあり、瞬時に判断することは難しいのです。)
そのため、公証人が当時は「意思能力がある」と判断して作成した公正証書遺言であっても、後日無効になるということがあります。
こうなると、財産の分け方などで相続人同士が争いになるリスクが生じます。
公正証書遺言が無効になるケースについて、詳しくは以下のコラムをご覧ください。
 [参考記事]
公正証書遺言も無効になることがある?効力と裁判例
[参考記事]
公正証書遺言も無効になることがある?効力と裁判例
2.遺言書の作成に必要な遺言能力の判断方法
さて、遺言能力の欠如を理由に公正証書遺言が無効と判断されないようにするためにも、どのように遺言能力の有無が判断されるのかを知っておくことが有益です。
以下では、遺言作成に必要な意思能力がどのように判断されるのかを確認します。
(1) 意思能力の判断基準(裁判例)
遺言作成に必要な意思能力の判断については、個々の遺言内容がさまざまであることから、一義的に明確な基準が存在するわけではなく、個別の事案ごとに具体的に検討していく必要があります。
もっとも、過去の事例では、「遺言能力の有無は、遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移、発病時と遺言時との時間的関係、遺言時と死亡時との時間的間隔、遺言時とその前後の言動及び健康状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無等遺言者の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項(遺言の内容)を判断する能力があったか否かによって判定すべきである」(東京地裁平成16年7月7日判決)としていることから、そのような諸要素を踏まえた上で遺言能力を判断していくことになります。
(2) 具体的な判断基準
では、遺言能力の有無を判断する要素について具体的に説明します。
遺言の内容
遺言の内容は、遺言者が問題となっている遺言の内容を理解・判断することができたか?という観点から、遺言能力を判断するための重要な要素となります。
遺言能力については、問題となっている遺言内容との関係で相対的に決定されることになります。
つまり、遺言の内容が単純であれば判断能力が低下している状態であっても遺言能力が肯定されやすく、反対に遺言の内容が複雑になればなるほど高度の遺言能力が必要とされるため、遺言能力が否定されやすくなります。
年齢・病状など心身の状況
年齢は、それ自体で遺言能力の有無を左右する要素になるものではありませんが、高齢者が作成した遺言をめぐってその効力が争われることが多いため、遺言能力の判断の一要素となります。
また、遺言者が判断能力の低下をもたらしうる脳梗塞、認知症、統合失調症などに罹患している場合には、医師の診断と相まって遺言能力を否定する要素となります。
遺言前後の生活状況、言動
遺言前後の遺言者の生活状況は、遺言作成時の遺言者の判断能力の程度を認定するための需要な要素とされています。専門医による認知症の診断がない場合であっても、遺言前後の生活状況から重度の認知症が認定される場合もあります(名古屋高裁平成5年6月29日判決)。
また、脳梗塞などに罹患したことによる判断能力の低下が認められても、その後の生活状況によっては遺言作成時の判断能力が認められる例もあります(和歌山地裁平成6年1月21日判決)。
遺言書の作成経緯、作成状況
遺言書の作成に至る経緯、作成時の状況は、遺言が遺言者の自発的意思に基づくものであるか否かという観点から問題とされます。遺言の作成が遺言者の自発的意思によるものであると考えられれば遺言能力は肯定されやすいです。
一方、遺言作成に至る経緯で、親族などの他人が主体的に動いていることや、作成時に遺言者が積極的な意思表明をしていないなどの事情がある場合には、遺言能力は否定されやすいといえます。
遺言書の体裁
遺言書の文字の記載、文章の体裁な、ど遺言書自体の体裁が調っていないことは、遺言者の遺言能力が否定される要素となります。
遺言者と受遺者の関係
問題となっている遺言書が指定された相続人や受遺者に有利なものである場合、これらの者と遺言者の間に遺言書の内容を根拠受けるだけの事情が認めらない場合には、遺言能力を否定する要素となります。
3.まとめ
公証人は、遺言者の遺言能力を正確に判断することができませんので、公正証書遺言を作成していたとしても遺言能力の欠如を理由に遺言が無効になる可能性もあります。
遺言書は元気なうちから早めに作成することが重要ですが、判断能力が低下した状態で作成せざるを得ない場合には、遺言能力の判断要素を踏まえて遺言能力があったといえる証拠を収集しておくと良いでしょう。
例えば、認知症が疑われる場合には、医学的観点と行動観察的観点の双方の観点から遺言者の当時の心身の状況を具体的に立証していくことが必要になります。
これらは、遺言者の遺言作成時およびその前後の診断書、看護記録、入院診療録などを取り寄せることによって立証していくことになります。
すべての相続人が遺言書が無効であることを認めているのであれば、相続人全員で遺産分割協議をすることで、遺言書と異なる内容の遺産分割をすることができます。
しかし、遺言書の有効性を争う相続人がいる場合には、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟といった手段によって遺言書の有効性を確認しなければなりません。
遺言書の作成や、残された遺言書に関するトラブル、遺産分割協議など、弁護士はあらゆる相続問題に対応することが可能です。
お悩みの方は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。