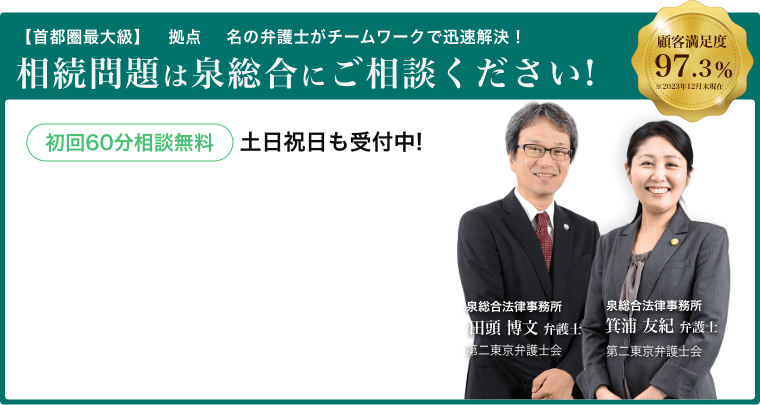認知症診断を受けた人の遺言の効力が争われた裁判例

遺言書を有効に作成するためには、遺言者に遺言能力があることが必要になります。
一般的には「認知症の方では有効な遺言書を作成することはできない」と思われがちですが、認知症であるからといって、直ちに遺言能力が否定されるわけではありません。
生前対策として有効な遺言書ですが、認知症の方が作成した遺言書はどのような場合に無効になるのでしょうか。
今回は、認知症と遺言書の効力との関係について、具体的な判例を解説します。
1.認知症の判断
認知症かどうかについては、以下のような検査を行った結果を踏まえて、最終的に医師が判断することになります。
(1) 神経心理学検査
神経心理学検査として代表的なものは、以下の2つが挙げられます。
①改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
9項目の設問によって構成された簡易知能評価スケールです。30点満点中20点以下だと認知症疑いとなり、点数が低いほど重度の認知症であるとされています。
ただし、本人の体調や気分によって結果が変わることも多いことから、改訂長谷川式簡易知能評価スケールの点数のみを根拠として認知症と判断されるわけではありません。
【参考】改訂長谷川式簡易知能評価スケール
②ミニメンタルステート検査(MMSE)
11項目の設問によって構成された検査であり、見当識だけでなく計算力や図形の描写力などが問われます。
30点満点中23点以下だと認知症疑いとなり、27点以下だと軽度認知障害の疑いとされます。
(2) 脳画像検査
上記の神経心理学検査だけで認知症と診断されるわけではなく、上記の検査によって認知症の疑いが生じた場合には、脳の萎縮状態を把握するためにCTやMRIといった脳画像検査を実施します。
脳のどの部分がどのくらい委縮しているかどうかを検査によって明らかにすることによって、認知症の進行度やタイプを知ることができます。
これらを踏まえた上での認知症と遺言能力との関係・判断基準については、以下のコラムをご覧ください。
 [参考記事]
認知症の人が書いた遺言書は有効か|遺言能力と判断基準
[参考記事]
認知症の人が書いた遺言書は有効か|遺言能力と判断基準
2.認知症と遺言の効力が争われた具体例
認知症の方が作成した遺言の効力が争われた判例としては、以下のものが挙げられます。
(1) 遺言能力がないと判断された裁判例
大阪地裁昭和61年4月24日判決
公正証書遺言作成の2日前から昏睡度3(ほとんど眠っており、外的刺激で開眼し得る状態)と4(完全に意識は消失するが、痛み・刺激には反応する状態)の間を行き来する状態で推移し、公正証書遺言作成の翌日には昏睡度5(痛み・刺激にも全く反応しなくなる状態)に陥り、死亡した事案について、遺言能力がないと判断しています。
東京地裁平成10年6月12日判決
自筆証書遺言において、76歳の遺言者につき、死亡の1年半前の精神知能検査で老人性痴呆と診断され、その約1年半後に自筆証書遺言を作成したが、1か月もしないうちに急性心不全により死亡した事案です。
痴呆の原因が加齢であることからすると、遺言当時も同様であるとみられ、遺言書自体も文章としての体裁が整っておらず、重要部分の趣旨が不明であるなどの理由から遺言能力がないと判断しています。
東京高裁平成21年8月6日判決
遺言者は、平成8年ころから痴呆の状態が顕著になり、このころアルツハイマー病を発症したと推認され、平成9年9月に脳梗塞で倒れ、見当識障害、記憶障害などの症状が認められるようになりました。
そして、アルツハイマー病と左脳脳梗塞との合併症で痴呆が重症化し、平成12年2月には老人性痴呆は重症であると診断され、同年4月に実施された「改訂 長谷川式簡易知能評価スケール」で8点とやや高度の痴呆とされました。
その後も老人性痴呆が進行している状態で自筆証書遺言が作成されたことから、裁判所は、遺言者には遺言能力がないと判断しました。
東京地裁平成28年8月25日
遺言作成の約2か月前に実施された改訂長谷川式簡易知能評価スケールの結果は9点であり、その1か月後には認知症と診断された遺言者が作成した遺言公正証書です。
認知症の専門病院の医師の意見書や証人尋問の結果から、遺言能力がなかったものとして遺言の効力を否定しました。
(2) 遺言能力が認められた裁判例
東京地裁平成28年1月29日判決
公正証書遺言について、遺言の当時、認知症状の進行した状態にあったということができ、理解力や判断力にも相応の障害が生じていたものと推認することができるとされました。
しかし、本件遺言の内容がわずか3条からなるものであり、従前の遺言を撤回して、相続人の1人またはその長男に相続させるというものにすぎず、複数の者に多数の遺産を配分するようなものではなく、殊更に複雑な判断や理解を要するものとは解されず、遺言者の当時の認知能力によっても理解が困難なものであったとはいえないとして、遺言能力が認められました。
3.まとめ
認知症と診断されたからといって、直ちに遺言が無効になるというわけではありません。
しかし、認知症と診断された後に作成された遺言については、遺言者が亡くなった後、相続人からその有効性を争われることがあります。
遺言者の死後の相続人同士の争いを回避するためにも、遺言書の作成はできる限り早めに作成しておくことをおすすめします。
遺言能力があったとしても、遺言書に形式的な不備があった場合には、遺言が無効になる可能性もありますので、遺言書の作成を検討している方は、弁護士のアドバイスを受けながら進めていくのが良いでしょう。
→ご相談メニュー「遺言書」