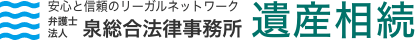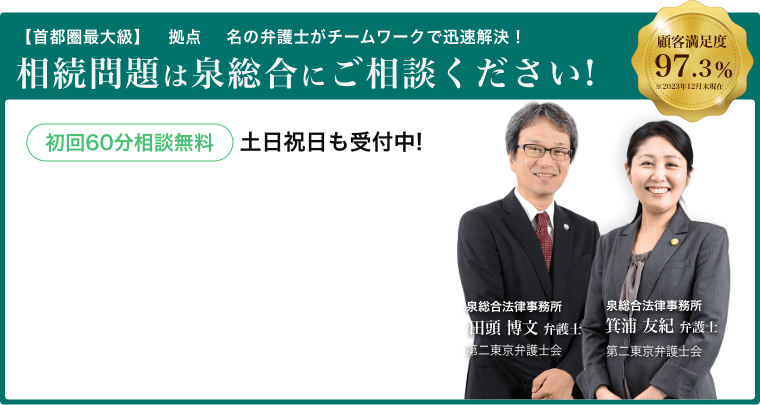被相続人の預貯金は調べられる?銀行への開示請求

相続が開始すると遺産分割の前提として、調査を行い相続財産を確定しなければなりません。
金融機関への相続財産の調査方法には、被相続人の預貯金口座の確認や残高照会があり、さらに必要があれば、預貯金口座の取引履歴の開示請求を行います。
そこで問題となるのが、相続人に、取引履歴の開示請求することができるかどうかです。
今回は、故人の銀行口座を調べるための金融機関に対する取引履歴の開示請求について解説します。
1.相続財産調査と預貯金口座
最初に、取引履歴の意味と、開示を求める目的についてご説明しましょう。
(1) 預貯金口座の取引履歴とは
相続財産調査のために、金融機関から取得する書類の1つに、残高証明書があります。
ただし、残高証明書は、特定の日における預貯金口座の残高を記載した書類であり、過去の入出金の履歴を知ることはできません。
一方、預貯金口座の取引履歴には、対象となる口座の入出金の記録が記載されています。
被相続人の預貯金口座の入出金の流れを知ることは、相続人間に次のような問題がある場合に、重要な意味があります。
(2) 取引履歴の開示を求める目的
亡くなった人の預貯金口座の取引履歴を開示請求するのは、使途不明金を明らかにして不当利得返還請求(不法行為に基づく損害賠償請求)をしたり、特別受益の有無を確認したりする目的があるからです。
被相続人の預貯金に使途不明の支出が疑われる場合
遺産分割で問題となる事案の1つに、相続人の一人が被相続人に無断で預貯金の引き出しを行っているケースを挙げることができます。認知症の被相続人と一緒に生活している相続人が、判断能力の低下につけ込んで、被相続人の預貯金を引き出し私的に利用した事案が典型的な事案です。
こうしたケースでは、預貯金を私的に利用した相続人に被相続人の通帳を開示するよう請求しても、なかなか開示してくれないでしょう。
しかし、預貯金の取引履歴を調べ、多額の預貯金が複数回にわたって引き出されていることがわかれば、使途不明金に関する責任を追及するきっかけとなります。
 [参考記事]
遺産の使い込みが発覚!取り戻すにはどうすればいい?
[参考記事]
遺産の使い込みが発覚!取り戻すにはどうすればいい?
相続人に特別受益を受けた可能性がある場合
また、生前に被相続人から多額の贈与を受けている場合には、遺産分割手続きでは、特別受益として持ち戻しの対象となることがあります。取引履歴を調査し、特別受益の有無を明らかにすることによって、公平な遺産分割を実現することが可能です。
このように、残高証明書以外に取引履歴を請求することには、重要な意味があります。
 [参考記事]
特別受益の「持ち戻し」とは?計算方法や注意点、持ち戻し免除を解説
[参考記事]
特別受益の「持ち戻し」とは?計算方法や注意点、持ち戻し免除を解説
2.預貯金口座の取引履歴は開示請求できる?
過去、金融機関は、相続人全員の依頼がない限り、預貯金口座の取引履歴の開示に応じてきませんでした。
しかし、以下の最高裁判決が出たことを受け、現在では多くの金融機関で相続人単独での預貯金口座の取引履歴の開示請求に応じています。
(1) 被相続人の死亡時まで預貯金口座が存在していた場合
最高裁平成21年1月22日判決は以下のように述べています。
金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。そして、預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法〔注:民法〕264条、252条ただし書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。
この判決により、共同相続人は、他の共同相続人全員の同意なくして、金融機関に対し、被相続人が有していた預貯金の取引履歴の交付を請求することが可能となりました。
一般的な金融機関では、10年間を取引履歴の保管期間としており、理屈上は、10年分であれば預貯金の取引履歴を請求することが可能だといえます。
仮に、単独の相続人が金融機関から取引履歴開示請求を拒否されたとしても、弁護士を通じて状況を解決することが考えられます。
(2) 被相続人の生前に預貯金口座が解約されていた場合
先ほどの最高裁判決は、被相続人が死亡するまでの間、銀行口座が存続していた事案に対する判決です。そのため、被相続人の生前に既に口座が解約されてしまっている場合には、必ずしも当てはまりません。
生前に口座が解約されていた場合の考え方については、東京高裁平成23年8月3日判決に述べられています。
預金契約についても、銀行は、預金契約の解約後、元預金者に対し、遅滞なく、従前の取引経過及び解約の結果を報告すべき義務を負うと解することはできるが、その報告を完了した後も、過去の預金契約につき、預金契約締結中と同内容の取引経過開示義務を負い続けると解することはできない。
この裁判例に従うのであれば、相続人側は、解約された口座については、銀行との間の契約をもとに預金履歴の開示を求めることはできないことになります。事実、実際に開示を拒絶された事案も散見されるところです。
しかし、預貯金口座の取引履歴は、遺産調査においても重要な資料になります。
被相続人が生前に口座を解約していたとしても、弁護士会照会といった方法を用いて開示してもらえるように働きかけることが重要になります。
(3) 取引履歴の開示請求は弁護士に依頼すべき?
ここまでご説明した通り、被相続人の取引履歴は、相続人の一人からでも開示請求することができます。
しかし、被相続人が生前口座を解約していたケースを含めて、金融機関が開示を拒んでいれば、弁護士照会などの方法を取る必要があります。そのため、ご不安のある方は、弁護士に相談するといいでしょう。
3.開示請求の手続きの流れ
預貯金口座の開示請求の手続きについては、各金融機関によって異なります。詳しくは、対象となる金融機関に問い合わせてから行うことをおすすめします。
一般的には、以下のような必要書類を持参し、金融機関の窓口で取引履歴の発行依頼を行うことになります。
- 被相続人が死亡したことが確認できる戸籍謄本など
- 申請者が相続人であることがわかる戸籍謄本など
- 申請者の印鑑証明書
- 手数料
4.被相続人が口座を開設していた金融機関が分からない場合
相続人が被相続人の預貯金をまったく把握していなければ、通帳やキャッシュカードを手掛かりに、口座を持っていたことが想定される金融機関をしらみつぶしにあたるしかありません。
ただし、特定の支店に預貯金の有無の照会を求めた場合には、当該支店だけを調査して回答される可能性も否定できません。そのため、遺産の詳細を把握できていないケースでは、本店およびすべての支店における預貯金の有無を確認する必要があります。
こんな場合にも、弁護士に依頼すれば、相続財産調査すべてをまとめて任せることが可能です。
5.まとめ
預貯金口座の取引履歴の開示請求は、適切な遺産分割手続きを行う前提として非常に重要となります。取引履歴を取得したところ、不明な出金が多数存在していることが判明した場合には、相続人による不正な出金の疑いもあります。
使途不明金の問題を解決するためには、専門的な知識が必要になります。使途不明金が判明した場合には、お早めに泉総合法律事務所までご相談ください。