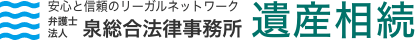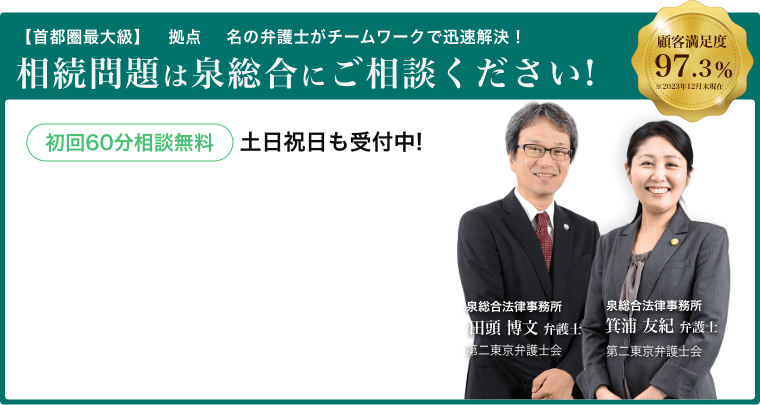遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

自分の希望通りの遺産分割を実現するという目的や、自分が亡くなった後の相続争いを回避するという目的から生前に遺言書を作成する方が増えてきました。
遺言書の作成は、死後の相続争いを回避する手段として非常に有効なものとなります。
また、遺言書で遺言執行者を指定することによって円滑な遺産分割を実現することが可能になります。
しかし「遺言執行者」がどのような役割をする人なのかについて正確に理解している方は少ないでしょう。
そこで今回は、遺言執行者の役割と選任するメリット、選び方などについて解説します。
1.遺言執行者とは?
遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定するかどうかを考えなければなりません。
遺言執行者とは何をする人で、指定するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
(1) 遺言執行者は遺言内容を実現するための手続きをする
遺言執行者とは、遺言者の指定または家庭裁判所によって選任され、被相続人の死後に遺言書の内容を実現する手続きをする人のことをいいます。
実際の仕事内容としては、財産目録を作成し各相続人に送付したり、遺言書の内容に従って、預貯金口座を解約し、遺産を各相続人に分配したり、不動産の名義変更手続きなどを行います。
このように遺言執行者とは、遺言者の死後に、遺言者の意思に従って、相続に関する諸手続きなどを行う人のことを指します。
(2) 遺言執行者の指定は必要か?
遺言書に以下のような遺言事項が含まれているときには、遺言執行者の指定が必要となります。
- 遺言認知(民法781条2項)
- 推定相続人の廃除・廃除の取消(民法893、894条)
これらの遺言事項は、相続人では行うことができないため、遺言書で遺言執行者が指定されていないときには、家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任してもらわなければならないからです。したがって、これらの事項が遺言書に含まれていなければ、遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。
しかし、遺言執行者を選任することによって以下のようなメリットがあるため、遺言執行者を指定するかどうか迷っている方は、前向きに検討してみることをおすすめします。
(3) 遺言執行者を選任するメリットとは?
遺言執行者を選任することで、以下のようなメリットがあります。
①不動産の相続登記(所有権移転登記)がスムーズにできる
相続登記
これまで不動産について特定財産承継遺言があると(特定の不動産を特定の相続人に相続させるといった記載方法)、遺言で指定された不動産の所有権が相続開始時から指定された相続人に移転しており、相続人単独で登記できることから、遺言執行者は登記義務を負わないとされていました(最高裁平成7年1月24日判決)。
しかし、改正民法により、遺言執行者は相続人が第三者対抗要件を具備するために相続登記を申請できることが明記されました(民法1014条2項、899条の2第1項)。
遺贈の登記
遺言書に記載された遺贈は、遺言執行者がいなくても実現することが可能です。
しかし、遺贈の目的物が不動産の場合には、相続人全員が登記義務者となり所有権移転登記を行うため、一部でも相続人が遺贈に不満を持ち協力してくれなければ登記をすることが困難になってしまいます。
一方で、遺言執行者を指定しておけば、登記義務者は遺言執行者になるので、相続人の協力がなくてもスムーズに遺贈の内容を実現することが可能となります。
 [参考記事]
民法改正|遺言執行者の権限を強化するルール変更の内容は?
[参考記事]
民法改正|遺言執行者の権限を強化するルール変更の内容は?
②預貯金の払戻手続きが簡略化できる
被相続人の預貯金口座を解約するときには、遺言書で被相続人の預貯金を取得する相続人が定められていたとしても、金融機関によっては相続人全員の印鑑証明書を要求されることがあります。
相続人が複数であったり、遠方に住んでいる相続人がいたりする場合には、相続人全員の実印と印鑑証明書を準備するのは、相当な負担となります。
しかし、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者だけで預貯金の払戻手続きを進めることができ、簡易かつ迅速に払い戻しが可能となります。
2.遺言執行者の職務と任せられる内容
遺言者が亡くなった後、遺言執行者はどのような職務を行うのでしょうか。
以下では、遺言執行者の具体的な職務の流れについて説明します。
(1) 就任通知書の作成・交付
遺言書で指定されたからといって、必ず就任しなければいけないわけではありません。就任するかどうかは指定された方がご自分の意思で判断することができます。
遺言執行者に就任すると判断したときは、遺言執行者に就任した事実や遺言の内容を相続人に知らせるために、就任通知書を作成し、相続人全員に送付します(民法1007条2項)。
(2) 相続人の調査
遺言執行者は、就任後、遺言の内容を実現するために準備をすることになります。
そのために、まず必要となるのが相続人の調査です。
遺言執行者は、被相続人の戸籍を取得するなどして、誰が相続人になるのかを確定させます。
相続人調査の完了時には、相続人の範囲を明らかにするためにも、法定相続情報一覧図や相続関係説明図などを作成するとよいでしょう。
(3) 相続財産の調査
遺言執行者は、相続人に対して財産目録を送付しなければなりません。その準備をするために、被相続人の相続財産の調査を行います。
たとえば、被相続人の預貯金には、各金融機関に照会をし、預貯金の有無とその額を明らかにしていきます。
また、不動産があるかどうか不明な場合には、市区町村役場から名寄帳を取得し、その内容をもとにして不動産の登記事項証明書を取得します。
被相続人の財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含むことになり、遺言執行者が被相続人の信用情報の開示請求をするなどして、借金の有無も調査する必要があります。
(4) 財産目録の作成・交付
上記のような相続財産の調査が終わったら、その内容を財産目録にまとめます。
財産目録の書き方については特に決まったものはありません。相続財産の内容が特定できるように記載すればよいでしょう。
作成した財産目録は、相続人全員に送付します。
(5) 遺言の内容を実行
上記の作業が終了した後は、遺言の内容を具体化する手続きに移ります。
預貯金などの払戻手続きや不動産の所有権移転登記手続きをするなど、遺言書の内容に従って必要な手続きを行っていきます。
(6) 任務完了後に相続人に報告
遺言内容の実現がすべて完了すると、遺言執行者は、相続人全員に対して任務完了の報告を行い職務は終了となります。
3.遺言執行者の権限の範囲
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)とされています。
遺言執行者の代表的な権限には、以下のものがあります。
(1) 子どもの認知
認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもに、法律上の親子関係を生じさせる手続きのことをいいます。
認知は、生前に行うのが一般的ですが、遺言によって認知することも可能です。
遺言によって認知する場合には、被相続人の死後に認知の手続きを行う遺言執行者の指定が必要になります。
遺言認知には、遺言執行者の指定を忘れてはいけません。
(2) 相続人の廃除
相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けていたなどの理由によって、相続人を推定相続人から除外する手続きのことをいいます。
認知と同様に相続人の廃除は、遺言者の生前に行うこともできますが、遺言によって相続人の廃除を行うことも可能です。
ただし、遺言書で相続人の廃除をする場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対し相続人の廃除の申立てをする必要があります。
そのため、遺言で相続人廃除をする場合にも、遺言執行者の指定を忘れないようにしましょう。
(3) 遺贈
民法改正によって、遺言執行者が指定されているときには、遺贈の履行義務があるのは遺言執行者だけであることが明確になりました(民法1012条2項)。
したがって、遺言執行者を指定しておけば、受遺者(遺贈を受ける人)が相続人との争いに巻き込まれることなく、スムーズな遺贈の実現が可能になります。
4.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する方法には、遺言書で指定する方法と、家庭裁判所に申立てを行い選任してもらう方法の2つがあります。
(1) 遺言書による指定
遺言者は、遺言書以外で遺言執行者を指定することはできません。
もっとも、遺言書では遺言執行者を直接指定できるだけでなく、遺言執行者の指定を信頼できる第三者に委託することもできます(民法1006条1項)。
(2) 家庭裁判所への選任申立て
遺言によって遺言執行者が指定されていなかった場合や、指定されていた人が就任を拒否した場合などには、相続人や利害関係人などの家庭裁判所への申立てにより、遺言執行者が選任されます。
ただし、家庭裁判所によって遺言執行者が選任されるためには、「遺言の執行が必要である」という要件が必要になります。遺言の内容が遺言執行を必要としなければ、申立てがあったとしても却下されてしまいます。
5.遺言執行者には誰を指定するべきか
遺言執行者の具体的な役割が分かったところで、最後に誰を遺言執行者に指定すればよいかが問題になります。
(1) 遺言執行者が相続人と同一人でも制度上は問題なし
遺言執行者には、未成年者および破産者以外であれば、特別な資格を要せずに誰でもなることができます(民法1009条)。
したがって、制度上は、相続人や受遺者と同一人物であっても遺言執行者になることは可能です。
(2) 遺言執行者は弁護士にお願いするのがおすすめ
しかし、遺言執行をスムーズに行うためには、相続に関する知識や経験が必要になります。そのため遺言執行者は、親族や知人などではなく弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に遺言執行者を依頼するのであれば、遺言書の作成からサポートしてもらえることも多く、将来争いにならない有効な遺言書の作成が可能になります。
また、遺言の内容によっては、相続人同士でトラブルになることも考えられます。しかし、専門家である弁護士が遺言執行者に指定されていれば、トラブルに対してもしっかりと対応してもらうことができます。
したがって、遺言書を作成するときには、弁護士に遺言執行者に就任してもらうことも検討してみましょう。
 [参考記事]
遺言執行者は誰がなれるの?弁護士・弁護士法人ではどちらがいい?
[参考記事]
遺言執行者は誰がなれるの?弁護士・弁護士法人ではどちらがいい?
6.遺言執行者についてのよくある質問(FAQ)
遺言執行者とは相続人全員の代理人として、遺言内容を執行する行為をします(改正前の民法では遺言執行者が相続人の代理人とみなすと規定されていました)。 さらに2019年の民法改正によって遺言執行者には復任権が認められ、遺言者が遺言書で別段の意思表示をした場合を除き、遺言者の責任において第三者に任務を行わせることができるようになりました(1016条1項)。いわば、代理人である遺言執行者が、復代理人を選任できることになったのです。 このため、民法改正後の遺言書に基づき遺言執行者に指定された方は、弁護士など専門家に遺言執行業務を依頼することができることになります。 遺言執行者ができないことの一つに相続税申告があります。 相続税の申告と納付は相続人固有の義務であり、遺言執行者が直接相続税申告を行うことはできません。 遺言執行者が税理士であっても、あらためで相続人から相続税申告についての依頼をする必要があります。
遺言執行者は誰の代理人?復任権ってどんなもの?
遺言執行者にできないことは?
7.まとめ
遺言書を作成するときには、遺言執行者を指定しておくことによって、遺言者が亡くなった後の遺言内容の実現がスムーズに進むとともに、相続人同士の争いを回避することができる場合があります。
遺言書の作成と併せて、遺言執行者についてもぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。