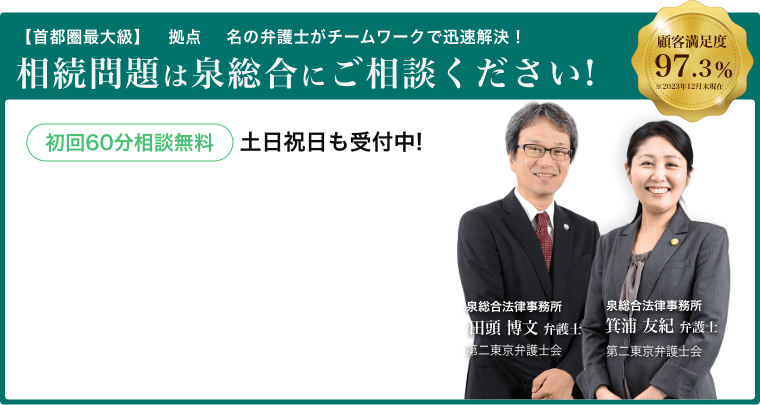公正証書遺言も無効になることがある?効力と裁判例

将来の相続争い(いわゆる争続)を防止するために有効になるのが、生前に遺言書を作成することです。なかでも「公正証書遺言」は、公証役場の公証人という専門家が作成する遺言書であるため、「無効にするのは難しい」遺言書だと考えている方も多いでしょう。
しかし、公正証書遺言だからといって、絶対に無効にならないわけではありません。自筆証書遺言に比べれば稀にではありますが、公正証書遺言でも無効になることがあります。
今回は、公正証書遺言が無効になる場合と具体的な裁判例について解説します。
1.公正証書遺言でも無効になることがある
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言のことをいいます。公正証書遺言の方式は、民法によって以下のように決められています(民法969条)。
- 証人2名以上の立ち合いがあること
- 遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、公証人がこの筆記したものを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させること
- 遺言者および証人が筆記の正確性を承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
- 公証人が、その証書の方式に従って作成した者である旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
公正証書遺言とは、専門家である公証人が作成する遺言書で、遺言者本人が作成する自筆証書遺言に比べて、上記の方式不備が原因となって無効になることは稀であることは確かです。
しかし、公証人が作成した遺言書であったとしても、後述するケースでは無効になることもあり、争われた裁判例も多くあります。
2.公正証書遺言は絶対に無効にならない?
公正証書遺言であっても、絶対に無効にならないわけではありません。
公正証書遺言が無効になるケースとしては、主に以下のようなものが挙げられます。
(1) 遺言者に遺言能力がない場合
遺言書を有効に作成するためには、遺言者が15歳以上であることに加え、遺言能力があること必要になります。遺言能力とは、遺言の内容を理解して、遺言の結果を弁識できるに足る意思能力のことをいいます。
高齢化が進んだ現代においては、遺言者に認知症などの症状がある場合の遺言能力が問題になることが多々あります。認知症が進行し、意思能力を欠く常況である場合には、当該遺言は無効になります。
公正証書遺言では、公証人が遺言者に遺言の内容を確認するなどして意思能力の有無を判断しますが、診断書などで確認をするわけではありません。公証人が遺言者の意思能力の欠如を看過して、公正証書遺言を作成してしまうこともあり得ます。
公正証書遺言が無効になるケースで一番多いのが、この遺言者に遺言能力がない場合です。
(2) 不適格な証人が立ち会った場合
①未成年者
②推定相続人、受遺者またはこれらの配偶者、直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員
公正証書遺言の作成時には、上記の不適格事由に該当しないかを公証人から確認されるため、不適格な証人が立ち会うということはそれほど多くはありません。
しかし、何らかの理由で上記の不適格事由があることを秘して証人になってしまった場合には、相続開始後に他の相続人から遺言の無効を主張されるおそれがあります。
(3) 口授を欠いた場合
公正証書遺言の作成時は、遺言者が公証人に遺言内容を伝える遺言者の「口授」という過程があります。
遺言者の口授とは、遺言者が遺言内容を口頭で公証人に伝えることです。
もっとも、遺言者は高齢であることが多く、自分で考えた遺言内容を淀みなく伝えることができることは多くありません。そのため、実務上、ある程度緩和された運用がなされています。
しかし、この口授を欠いた公正証書遺言は無効になるため、問題になることがあります。
もっとも、公証人が手続きしていますから、全く遺言内容を伝えていないということは通常はありません。
公証人とはやり取りしていたものの、民法の求める「口授」には満たないと判断されるケースがあるということです。
この点は、後ほど裁判例でご説明します(4.(2))。
3.公正証書遺言の効力を争う方法
公正証書遺言の効力を争う方法としては、相続人のなかに遺言の無効を争う人がいるかどうかによって、以下のように異なってきます。
(1) 相続人が遺言の無効を認め、争わない場合
遺言能力を欠くなどの理由によって公正証書遺言が無効であると考えられる場合には、まずは、他の相続人の意見を確認するようにしましょう。
遺産分割においては、遺言書が遺産分割協議に優先することになりますが、遺言書と異なる内容の遺産分割協議が絶対的に禁止されているわけではありません。相続人全員が遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことについて合意しており、かつ遺贈による受遺者(この場合は相続人以外の者)が遺贈の放棄をした場合には、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことも可能です。
相続人全員が、遺言書が無効であることを争わない場合、後述する裁判手続きによることなく、遺言とは異なる内容の遺産分割協議を行うことによって遺産を分割することができます。
(2) 一部の相続人が遺言の無効を認めない場合
一部の相続人が、遺言書が無効であることを認めず、かつ遺産分割協議にも応じない場合には、「遺言無効確認請求訴訟」を提起して、公正証書遺言の有効性を争っていくことになります。「一部の相続人に全ての遺産を相続させる」旨の遺言がなされた場合には、遺産を取得できなかった相続人が訴訟提起することが多くなります。
遺言無効確認請求訴訟では、遺言が無効であると主張する相続人が、遺言が無効であることの立証責任を負います。
たとえば、遺言能力としての意思能力を欠くことを理由に公正証書遺言の無効を立証する場合には、次の諸事情を総合的に考慮して判断していくことになります。
①遺言作成時の遺言者の心身の状況
遺言時における遺言者の心身の状況は、遺言能力の有無を判断するにあたって最も基礎的かつ重要な事情です。
一般的に、遺言者は高齢であることが多く、加齢や、認知症などの罹患によって認知、判断能力が低下し、正常な判断を成し得ない状況で作成される場合があります。
もっとも、単に認知症であったということだけで遺言能力が否定されるわけではなく、医学的観点と行動観察的観点の双方の観点から遺言者の当時の心身の状況を具体的に立証していくことが必要になります。
これらは、遺言者の遺言作成時およびその前後の診断書、看護記録、入院診療録などを取り寄せることによって立証していくことになります。
②遺言内容それ自体の複雑性
遺言能力は、当該遺言の内容および当該遺言の法的結果を弁識、判断するための能力であるため、その存否の判断にあたっては当該遺言の内容も影響してきます。
たとえば、遺言の内容が相続税にも配慮したもので、財産の配分内容も複雑なものである場合には、より高度な判断能力が要求されることになります。
他方、「すべての財産を特定の相続人に相続させる」といった単純な内容の場合には、遺言書作成にあたってそれほど高度な判断能力は要求されないことになります。
③遺言内容の不合理性・不自然性
遺言内容が生前の遺言者と受遺者との関係に照らして、そのような遺言をする動機・理由が遺言者に見当たらず遺言内容が不合理である場合や、遺言者の考え方が大きく変化する事情がないにもかかわらず何度も遺言の内容を大きく書き換えているという場合には、遺言者が十分な判断能力を有しない状態で遺言書が作成されたと推認するための重要な間接事実になります。
4.公正証書遺言が無効になった裁判例
公正証書遺言が無効になった裁判例としては、以下のようなものがあります。
(1) 東京高裁平成25年3月6日判決
遺言者は、全財産を妻に相続させる旨の自筆証書遺言を作成していましたが、その後、全財産を妹に相続させる旨の公正証書遺言を作成したため、その公正証書遺言の有効性が問題となりました。
裁判所は、遺言者は、自筆証書遺言作成後に難治性の退行期うつ病に罹患し、公正証書遺言が作成された当時の被相続人の症状は認知症とみるほかないこと、被相続人の妻が生存中であるにもかかわらず、妹に全財産を相続させる旨の遺言を作成することについて合理的理由が見当たらないことなどの事実から遺言能力を否定し、公正証書遺言を無効と判断しました。
(2) 東京高裁平成27年8月27日判決
口授を欠いたとして公正証書遺言の無効確認等が争われた事案です。
裁判所は、公正証書遺言作成における「口授」について次のように述べ、本件では公証人から確認されたのみで遺言者自身が遺言内容について語っていないことから、無効であると判断しました。
「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」とは、遺言者自らが、自分の言葉で、公証人に対し、遺言者の財産を誰に対してどのように処分するのかを語ることを意味するのであり、用語、言葉遣いは別として、遺言者が上記の点に関し自ら発した言葉自体により、これを聞いた公証人のみならず,立ち会っている証人もが、いずれもその言葉で遺言者の遺言の趣旨を理解することができるものであることを要するのであって、遺言者が公証人に自分の言葉で遺言者の財産を誰に対してどのように処分するのかを語らずに、公証人の質問に対する肯定的な言辞、挙動をしても、これをもって、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したということはできないものと解するのが相当である。
(3) 東京地裁平成28年1月28日判決
問題となった公正証書遺言は、遺言者の成年後見開始の審判申立後、開始決定前の期間に作成されたものでした。
遺言公正証書作成日の約6か月前の時点で、任意後見監督人選任申立のための書類として裁判所に提出された診断書では、「計算はほとんどできない」「理解力、判断力が極めて障害されている」という記載があったことから、裁判所は、この時点で、脳内血管の器質的障害を原因とする回復可能性の極めて低い精神障害により、意思能力を欠く常況となり、かつ、遺言時の前後を通じてそのような状態が継続していたと認定しました。
そして、遺言者の遺言能力としての意思能力を否定し、公正証書遺言を無効と判断しました。
(4) 東京地裁平成28年3月4日判決(公刊物未登載)
遺言者は、公正証書遺言を作成した当時94歳であり、これまで認知症と診断されたことはありませんでしたが、せん妄の症状がみられることがありました。
裁判所は、公正証書遺言よりも前に作成していた遺言の内容から遺言者が翻意する合理的理由がないことや、公正証書の作成によって利益を受ける相続人の関与があったことから、遺言者には遺言時に判断能力がなったものとして、公正証書遺言を無効と判断しました。
(5) 東京地裁平成28年8月25日判決(判例時報 No.2328p65)
遺言者は、遺言作成の約2か月前に実施された改訂長谷川式簡易知能評価スケールの検査結果が9点であり、その1か月後には認知症と診断されました。
そのような状況で作成された公正証書遺言について、認知症の専門病院の医師の意見書や証人尋問の結果から、遺言の能力がなかったものとして、公正証書遺言を無効と判断しました。
5.まとめ
今回説明したとおり、公正証書遺言であっても無効になることもあり、実際の裁判例でも無効が認められているケースもあります。
公正証書遺言を作成しようと考えている方は、将来遺言書が無効にならないように、遺言能力や証人の適格性には十分に注意を払う必要があります。
また、内容に不合理・不自然な遺言書を発見した場合には、遺言書作成当時の遺言者の判断能力を調査し、遺言の無効を争える場合があるかもしれません。
「無効を申し立てられた」、「無効にしたい」といった公正証書遺言についてのお悩みのある方は、ぜひ泉総合法律事務所までご相談ください