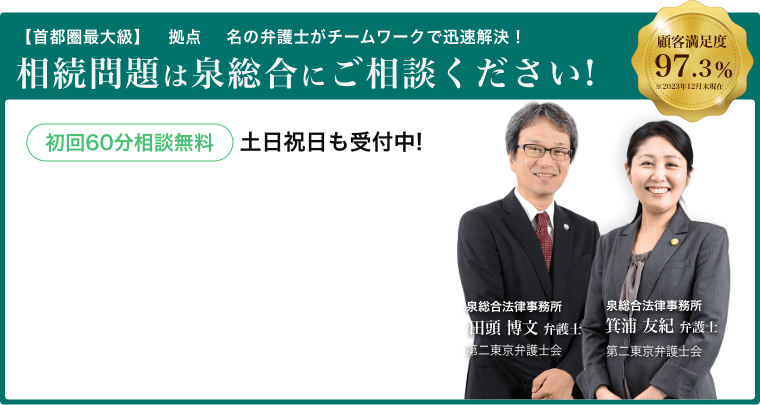死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリットを解説

「子どもがいないので、財産を、直接甥と姪に渡したい」
「籍に入っていない事実婚とはいえ、パートナーに財産を渡してあげたい」
家族や結婚形態が多様化していることもあり、このようなお悩みをお持ちの方も増えてきているかと思います。
このような問題を解決する方法として、まず思いつく方法が、遺言による「遺贈」ですが、この他に、「死因贈与」という方法もあります。
そこで、今回の記事では、死因贈与とはどのような方法か、遺言による遺贈との違いは何かそれぞれのメリット・デメリットは何かなどについて解説します。
1.死因贈与とは?
「死因贈与」は、使い勝手がよく、相続のトラブル防止などに効力を発揮します。
まずは、「死因贈与とは何か」「遺贈との同異点」について説明します。
(1) 死因贈与とは?
死因贈与は、文字通り贈与の一形態です。
贈与には、大きく分けると、次の2種類があります。
単純贈与
通常の一般的な贈与は、この単純贈与のことです。
条件・期限付贈与
ある条件が成就したときや、ある期限が到来したときに初めて、贈与の効果が発生する贈与です(そのため、贈与を受ける側(受贈者)は、条件の成就等があるまでは、贈与の履行を請求することはできません)。
死因贈与は、この「条件・期限付贈与」の一種で、贈与する側(贈与者)が死亡することによって初めて贈与の効果が発生します。
つまり、贈与者の死亡を原因として(死因)、その財産を譲り渡す(贈与)契約のことです。
(2) 死因贈与の成立要件
死因贈与が成立する要件は、次のとおりです。
死因贈与契約の締結
死因贈与も贈与契約の一種です。当事者が合意して、死因贈与契約を締結する必要があります。
法律上、贈与契約は、当事者の合意のみで成立するので、口頭の約束でも成立します。
ただし、贈与者が亡くなってからでは死因贈与を立証するのが難しいため、通常は契約書を作成します。
さらに念を入れるなら、契約書を公正証書で残すことも検討すべきでしょう。
贈与者の死亡
贈与者が死亡することにより、この贈与の効果が生じます。
2.死因贈与と遺贈の同異点
一方、死因贈与と同様に、自分の死後、特定の相手に財産を渡すことができる「遺言による遺贈」があります。
ここでは「遺贈」について、「遺贈とは何か?」「死因贈与と遺贈の同異点」について説明します。
(1) 遺贈とは何か?
遺贈とは、遺言によって、遺贈者(遺産を渡す人)の財産を、受遺者(遺産を受ける人)に、譲り渡すことを言います。
遺言で「誰に、どの財産を渡すか」を指定しますので、法定相続人はもとより、法定相続人以外にも(親族関係の無い相手にも)財産を渡すことができます。
遺贈について詳しくは、次の記事をご覧下さい。
 [参考記事]
遺贈と相続は違うもの?遺贈の種類と活用方法
[参考記事]
遺贈と相続は違うもの?遺贈の種類と活用方法
(2) 死因贈与と遺贈との違い
死因贈与は契約で、遺贈は単独行為
遺贈は、誰に何を遺贈するかを一方的に遺言で指定するため、遺贈者である被相続人の意思だけでよく、受遺者の合意は必要ありません(単独行為)。
これに対して、前述の通り、死因贈与は贈与契約を結ぶ必要があり(契約)、贈与者・受贈者が合意しない限り、死因贈与は契約として不成立になります。
よって、遺贈は単独行為、死因贈与は契約という点が異なります。
書面の要否
遺贈するには、遺言書の作成が必要です(遺言書は、自筆証書遺言よりも公正証書で残す方が後々のトラブルを防げます。自筆証書遺言を作成する場合は、紛失や改竄を防止するため、法務局の遺言書保管制度を利用することも検討するとよいでしょう)。
一方で、死因贈与の契約自体は、書面の約束でも口頭の約束でも成立します。
年齢
遺贈は、遺言を作成することができる15歳以上でなければできません。15歳未満は、親権者などの法定代理人の同意があっても遺贈できません。
これに対して、死因贈与は契約であることから、単独で行うには、成年に達していなければなりません。
未成年者の場合は法定代理⼈の同意を得る必要がありますが、遺贈と異なり、同意を得れば可能です。
なお、単純に贈与を受ける行為は、未成年者でも単独で行うことができます(お正月のお年玉を想像すると分かりやすいでしょう)。
不動産取得時の税率
遺贈や死因贈与で不動産を取得した場合、ともに、名義の変更に当たって、登録免許税と不動産取得税がかかります。
| 遺贈 | 死因贈与 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 |
|
⼀律 2.0% |
| 不動産取得税 |
|
⼀律 4.0% (令和3年3月31日までは3.0%) |
※それぞれの税率を対象の不動産の評価額に乗じて税額を算定する
ただし、上記の表のとおり、死因贈与は、税率が相続人か否かに関わらず一律であるのに対し、遺贈の場合は、法定相続人がそれ以外に比べて税率が低く有利という点が異なります。
「始期付所有権移転仮登記」ができるのは死因贈与だけ
始期付所有権移転仮登記(以下、仮登記という)とは、「不動産の所有権が被相続⼈の存命中は被相続⼈に属し、被相続⼈の死亡を原因として、所有権が相続⼈に移る登記」のことです。
死因贈与では、贈与者の承諾があれば、贈与者が単独で仮登記を行うことができます。この際に、贈与者の承諾書と印鑑証明書を添付しますが、死因贈与の契約書を公正証書化して添付しておけば、贈与者の印鑑証明書は不要になります。
ただし、公正証書に、贈与者による仮登記申請に関する認諾条項(贈与者が『仮登記していいです』と認めること)があることが必要です。
他方、遺贈の場合は、こうした仮登記はできません。
負担付死因贈与は撤回できない場合も
単独行為である遺贈の場合は、遺言書を書き直すことにより撤回が可能です。
死因贈与も、基本的には、贈与者からの贈与契約の撤回は可能です。
ただし、「負担付死因贈与」、つまり、財産を贈与する代わりに、贈与した相手に自身の生活の面倒をみるなどといった義務や負担を課している贈与契約のケースでは、贈与を受けた側が既にその義務・負担を履行していると、撤回を認めることは義務・負担を履行した者に不利益となるので、撤回が認められない場合もあります。
詳しくは、後述の「4.死因贈与のメリット・デメリット」をお読みください。
(3) 死因贈与と遺贈の共通点
死因贈与と遺贈とは共通点も存在します。死因贈与と遺贈は、次の点が共通します。
- 被相続人(贈与者)の死亡により効力が生ずる
どちらも、財産を譲る人の死亡によって、効力が生じます。- 相続人以外にも財産を譲ることが可能
どちらも、法定相続人以外を指定して財産を譲ることができます。- 相続税が課税される
どちらも、被相続人の相続財産として課税されます。死因贈与も、贈与者の死亡によって効力が生ずるため、遺贈に準ずる課税になります。- 遺留分侵害額請求の対象となる
どちらも、被相続人の相続財産を譲り受けることになり、法定相続人の遺留分を侵害した場合には、遺留分侵害請求(改正前の相続法では遺留分減殺請求)の対象になります。
下記の表に、死因贈与と遺贈の同異点を一覧にまとめますので、ご覧下さい。
| 遺贈 | 死因贈与 | |
|---|---|---|
| 契約か単独行為か | 単独行為 | 契約 |
| 遺言書の作成が必要か | 必要 | 不要 ただし、贈与契約が必要(書面または口頭の約束) |
| 可能となる年齢は | 15歳以上 | 単独では成年以降 未成年者の場合は親権者などの法定代理⼈の同意が必要 |
| 不動産取得時の税率は | 法定相続人:優遇税率 法定相続人以外:通常税率 |
一律、通常税率 |
| 仮登記が可能か | できない | できる |
| 撤回が可能か | 撤回が可能 | 原則、撤回は可能 ただし、贈与契約が必要(書面または口頭の約束) |
| 効果が生じるタイミングは | 被相続人の死亡時 | 贈与者の死亡時 |
| 相続人以外にも財産を譲ることができるか | 相続人以外にも譲れる | 相続人以外にも譲れる |
| どのように課税されるか | 相続税 | 相続税 |
| 遺留分侵害額請求の対象となるか | 対象になる | 対象になる |
3.死因贈与をする方法
前述のとおり、死因贈与を行なう場合、当事者間で贈与契約を結びます。
以下に、死因贈与契約書のひな形を掲載しますので、参考にして下さい。
死因贈与契約書のひな形
|
死因贈与契約書 贈与者 山田太郎 (以下「甲」という。)と受贈者 木村次郎 (以下「乙」という。)は、次の通り死因贈与契約を締結した。 第1条 甲は現金 1,000,000円を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
記 住所 上記契約を証するため本証書を2通作成し、各自署名押印し、甲乙1通ずつ持ち合うものとする。 令和 年 月 日 贈与者(甲)
受贈者(乙) |
4.死因贈与のメリット・デメリット
(1) 死因贈与のメリット
贈与不動産は仮登記で確実に取得が可能
贈与財産が不動産であれば、贈与者の承諾を受けて仮登記手続を行っておき、不動産所有権移転登記の順位を確保することで、贈与者が亡くなった後に、受贈者がより確実に財産を取得することができます。
負担付死因贈与が可能
死因贈与では、「負担付死因贈与」、つまり、自分の生活の面倒をみるなどの義務や負担を負ってもらう代償として財産を贈与するといった贈与契約とすることができます。
贈与者が亡くなるまで、受贈者はその義務や負担を全うし、贈与者はその利益を受けるということになります。
他方、遺贈にも、「負担付遺贈」があり、遺贈する代わりに一定の義務を負わせる条件をつけることができます。例えば、「残された配偶者の面倒をみる」などの条件です。
しかし、負担付遺贈は、相続発生「後」の義務履行が条件となるため、遺贈者本人は義務履行をチェックすることができません。
また、遺贈は、受遺者の意思と無関係に行なわれる遺贈者側の一方的な行為ですから、受遺者がそれを受けるか否かを選択する自由があり、遺贈を放棄することができます。
さきの負担付き贈与の例(「残された配偶者の面倒をみる」という条件付き)でいうと、遺贈者の死後、もし受贈者から遺贈を放棄されてしまえば、残された配偶者の面倒を見る人がいなくなってしまいます。
配偶者居住権を死因贈与することも可能
「配偶者居住権」とは、夫あるいは妻が亡くなった時に、その配偶者(被相続人と同居していた配偶者)が自宅に住み続けることができる権利です。
この配偶者居住権は、遺言による遺贈や遺産分割で設定することができますが、死因贈与により設定することも可能です(なお、配偶者居住権には、長期と短期の2種類がありますが、いずれも死因贈与で取得させることができます)。
配偶者居住権については、次の記事をご覧下さい。
 [参考記事]
配偶者居住権とは?メリット・デメリットと使い方を解説
[参考記事]
配偶者居住権とは?メリット・デメリットと使い方を解説
(2) 死因贈与のデメリット
登録免許税、不動産取得税の税率が高い
不動産を取得する場合、登録免許税と不動産取得税を納税しないといけません。
前述のとおり、遺贈の場合は、相手が法定相続人であれば税率が優遇されます。対して、死因贈与の場合は、相手が法定相続人であろうとなかろうと、一律、通常の高い税率となってしまいます。
負担付死因贈与は撤回できないことがある
死因贈与は、基本的には、贈与契約の撤回は可能です。贈与に関する民法第554条により、遺贈撤回に関する条項(民法第1022条)が準用されるからです。
ただし、前述のとおり、「負担付死因贈与」、つまり、贈与を受ける人に、自身の生活の面倒をみるなどの義務や負担を負ってもらっている贈与契約の場合は、撤回が認められない場合もあります。
これは、受贈者が既に義務や負担を履行している場合は、贈与者はその利益を既に受けてしまっているから(この状態で贈与者に撤回を認めるのは、受贈者の受ける不利益が大きいから)です。
一方で、遺贈の場合は、遺言書を書き直すことにより撤回が可能です。
農地の場合、登記に農地法3条の許可が必要になる
死因贈与によって農地の贈与を受ける場合は、農地法第3条の許可申請をする必要があります。
これに対して、遺贈でも包括遺贈(財産の取得割合を示して遺贈する方法)の場合は、農地法第3条の許可申請は不要です。
しかし、遺贈でも、相続人以外への特定遺贈(農地を特定して遺贈する方法)の場合は、死因贈与と同様に、農地法第3条の許可申請が必要となります。
贈与者・受贈者が認知症の場合に死因贈与は成立しない可能性も
民法549条には、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。
死因贈与が効力を生じるためには、贈与契約の成立要件である贈与者の「財産を無償で相手方に与える意思を表示」と受贈者の「受諾の意思表示」が必要になります。
そのため、死因贈与契約における当事者の一方又は双方が認知症で正常な判断ができない場合には、当該当事者について、有効な贈与契約の意思表示があったとは認められない可能性があります。最終的な判断は、裁判所の判断によりますが、当事者の有効な意思表示が認められなければ、死因贈与契約は成立しません。
判断能力に問題のある当事者が有効な契約を行なうためには、当該当事者に対し、成年後見人等を選任することが必要とされます。
贈与不動産の登記には相続人全員の承諾が必要
贈与財産である不動産の仮登記の本登記や、仮登記をしていない場合の所有権移転登記には、贈与者である被相続人を登記義務者、受贈者を登記権利者として所有権移転登記を共同申請します(ただし、仮登記の本登記は、登記義務者が本登記に協力しない場合、本登記をすべきことを命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有する調停調書等を含む)を得れば、単独申請が可能になります)。
しかし、被相続人は亡くなっているため、実際には、死因贈与の執行者がいれば執行者が、いなければ相続人全員が登記義務者の代わりとして登記手続きを行います。
したがって、死因贈与契約によって執行者を定めていない限り、相続人全員の承諾が必要になります。
一方、遺贈は現状仮登記ができないのですが、仮登記ができなくとも、2024年施行される改正不動産登記法60条3項により、受遺者が相続人であれば、所有権移転登記を単独で申請することが可能になる予定です。
共同申請よりも時間や手間がかからないので、迅速な権利移転手続が可能になるわけです。
5. まとめ
今回は、「死因贈与とは何か、遺贈との違いはどこにあるのか」について見てきました。
「死因贈与は当事者間の贈与契約」で、「遺贈は被相続人の意思である遺言」と形式は違いますが、法的な効力は大差ないように思います。
しかし、実際に相続財産を法定相続人やそれ以外の人に残す時には、「負担付」の条件をつけるのかどうか、税務的なメリットはどうかなど、個々の状況を踏まえて最善の判断する必要があります。
泉総合法律事務所では、死因贈与をはじめ、様々な相続問題に対応しております。死因贈与についてお悩みであれば、是非一度、泉総合法律事務所にご連絡下さい。