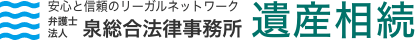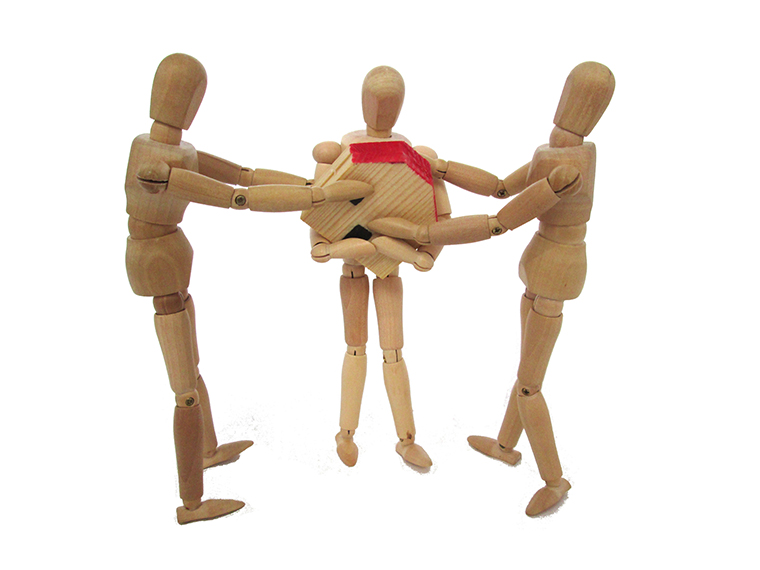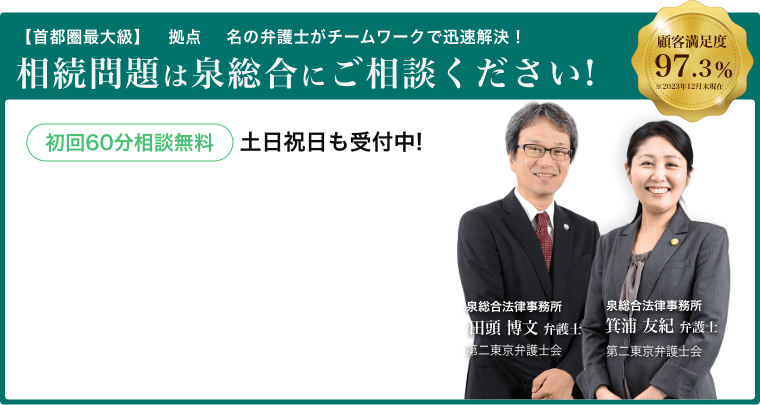2023年4月施行|相続法改正のポイントをわかりやすく解説

2023年4月1日より、相続に関するルール変更を含む改正民法が施行されました。
今回の改正民法には、相続法の抜本的な変更が多数含まれています。2023年4月以降に相続が発生した方や、将来的な相続に備えたい方は、改正民法(改正相続法)のルールを正しく理解しておきましょう。
今回は、2023年4月施行・改正相続法の変更ポイントを解説します。
1.2023年4月施行|改正相続法の主な変更ポイント
2023年4月1日に施行された改正民法には、相続について主に以下のルール変更が盛り込まれています。
①長期間経過後の遺産分割|具体的相続分による分割の期限を新設
②遺産共有と通常共有が併存している場合の特則の新設
③相続財産の管理に関する制度変更
④不明相続人の不動産の持分取得・譲渡
次の項目から、上記の各項目について詳しく解説します。
2.長期間経過後の遺産分割|具体的相続分による分割の期限を新設
1つ目の変更ポイントは、長期間経過後の遺産分割に関するルールの見直しです。特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による遺産分割につき、原則として相続発生後10年という期限が設けられました。
(1) 具体的相続分とは
「具体的相続分」とは、特別受益および寄与分を反映した相続分をいいます。
①特別受益(民法903条、904条)
相続人が被相続人から特別に受けた贈与または遺贈です。特別受益のある相続人の相続分は減り、その他の相続人の相続分は増えます。
②寄与分(民法904条の2)
事業の手伝いや介護などにより、相続財産の維持または増加に貢献した相続人に認められます。寄与分のある相続人の相続分は増え、その他の相続人の相続分は減ります。
(2) 相続開始から10年経過後は、具体的相続分による遺産分割が原則不可に
今回の相続法改正により、相続開始の時から10年を経過すると、特別受益と寄与分に関する民法の規定が原則として適用されなくなりました(民法904条の3)。
具体的相続分による分割の期限が新設された背景には、早期の遺産分割を促進する目的や、書証などの散逸により具体的相続分の算定が困難となることへの懸念などがあります。
(3) 具体的相続分による分割の期限の例外・経過措置
ただし例外的に、相続開始の時から10年を経過した場合であっても、以下のいずれかに該当すれば具体的相続分による遺産分割の請求が認められます(民法904条の3但し書き)。
- 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき
- 相続開始後10年間の満了前6か月以内の間に、遺産分割を請求できないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき
また、家庭裁判所の審判手続きによらず、相続人全員の合意に基づき具体的相続分による遺産分割を行うことは可能です。
なお、本改正は改正相続法の施行日より前に生じた相続についても適用されますが、施行日から5年間の経過措置が設けられています。
(例)2013年1月1日に相続が発生した場合
→相続開始の時から10年経過時(2023年1月1日)、または改正法施行日から5年経過時(2028年4月1日)のいずれか遅い時までに、家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、具体的相続分による遺産分割ができる
→2028年4月1日までに、家庭裁判所へ遺産分割審判を申し立てればOK
3. 遺産共有と通常共有が併存している場合の特則の新設
2つ目の変更ポイントは、遺産共有と通常共有が併存している場合に関する特則の新設です。
財産の共有者のうち1人が死亡した場合、その財産については「遺産共有」と「通常共有」が併存する場合があります。
①遺産共有
相続人全員が、分割前の遺産を共有することをいいます(民法898条)。②通常共有
複数の共有者が財産を共有することをいいます。(例)土地共有者A・BのうちBが死亡し、CとDがBを相続した場合
→通常共有持分(A)と遺産共有持分(C・D)が併存する
従来の民法では、遺産共有と通常共有が併存する場合、共有関係を裁判で解消するには、共有物分割と遺産分割の手続きを別個に実施しなければなりませんでした。
今回の相続法改正により、相続開始から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も共有物分割訴訟によることができるようになりました(民法258条の2第2項)。
ただし共有者は、共有物分割訴訟によって遺産分割を行うことにつき、訴状の送達を受けた日から2か月以内に異議を申し立てることができます(同条3項)。
なお、共有物分割訴訟によって遺産分割を行う際には、具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分(=遺言によって指定された相続分)によります(民法898条2項)。
4.相続財産の管理に関する制度変更
3つ目の変更ポイントは、相続財産の管理に関する制度変更です。具体的には、主に以下の3点が変更されています。
①相続財産保存制度の見直し
②相続放棄時に保存義務を現占有財産のみに限定
③相続人不存在の相続財産の清算手続きを簡略化
(1) 相続財産保存制度の見直し
相続開始後から遺産分割の完了まで、いつでも利用できる相続財産の保存に関する制度が新設されました(民法897条の2)。
利害関係人は家庭裁判所に対して、相続財産の管理人の選任や、その他の相続財産の保存に必要な処分を申し立てることができます。
新たな相続財産保存制度は従来と異なり、共同相続人が遺産を共有している段階や、相続人のあることが明らかでないケースでも利用可能です。
(2) 相続放棄時に保存義務を現占有財産のみに限定
相続放棄をした者が負う相続財産の保存義務(旧:管理義務)が、相続放棄の時点で現に占有している相続財産に限定されました(民法940条1項)。
相続放棄をした者は、相続放棄の時点で現に占有している相続財産につき、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存する義務を負います。
相続放棄をした者の保存義務が限定されたのは、従来の民法における管理義務の発生要件や内容が不明であり、相続放棄をした者が過大な負担を強いられるケース多い点が問題視されたためです。
(3) 相続人不存在の相続財産の清算手続きを簡略化
相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は最終的に国庫へ帰属します(民法959条)。
相続財産を国庫へ帰属させるまでには、相続財産管理人の選任後、最低10か月間に及ぶ3段階の公告手続きを経なければなりませんでした。
今回の相続法改正により、相続人不存在時における公告手続きが最低6か月間に短縮され、手続きの簡略化が図られました(民法952条2項、957条1項)。
また、相続財産を国庫に帰属させる業務を行う者の呼称も、「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に変更されました(民法952条1項)。
5. 不明相続人の不動産の持分取得・譲渡
4つ目の変更ポイントは、所在等が不明な共有者が有する不動産の共有持分につき、他の共有者による持分の取得・譲渡に関する手続きが新設された点です。
所在等が不明な不動産の共有者がいる場合、他の共有者は裁判所に対して、自分に共有持分を取得させる旨の裁判を請求できます(民法262条の2第1項)。
また、他の共有者全員が一致すれば、裁判所に対して当該不動産の売却権限の付与を請求できます(民法262条の3第1項)。
相続人の一部が行方不明のケースでも、上記の共有持分の取得・譲渡に関する手続きを利用すれば、遺産分割を完了できる場合があります。
ただし、共有持分が相続財産に属する場合には、相続開始の時から10年を経過していなければなりません(民法262条の2第3項、262条の3第2項)。
なお、裁判所に対して上記の各請求をする際には、所在等が不明な共有者が有する持分相当額の金銭を供託する必要があります。
6. 2023年施行・相続法改正についてよくある質問
-
改正相続法はいつから施行された?
2023年4月1日から施行されました。
-
施行日より前に発生した相続についても、改正相続法は適用される?
改正相続法は原則として、施行日(2023年4月1日)以降に発生した相続に限って適用されます。同年3月31日以前に発生した相続については、改正相続法は適用されないのが原則です。
ただし例外的に、具体的相続分による分割の期限に関する規定は、改正相続法の施行日より前に発生した相続についても適用されます。この場合、5年間の経過措置を受けることが可能です。
7.まとめ
ここまでご紹介下通り、令和5年4月1日から相続に関するルールがいくつか変更になっています。
特に遺産分割における具体的相続分には10年の期限が定められたため、経過措置はあるものの、早期の対応が求められます。
遺産分割協議は相続人間で意見が食い違い、解決には専門家への相談が必要になることが多くなります。
泉総合法律事務所では、遺産分割に限らず相続案件に積極的に取り組んでいます。相続問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、一度ご相談ください