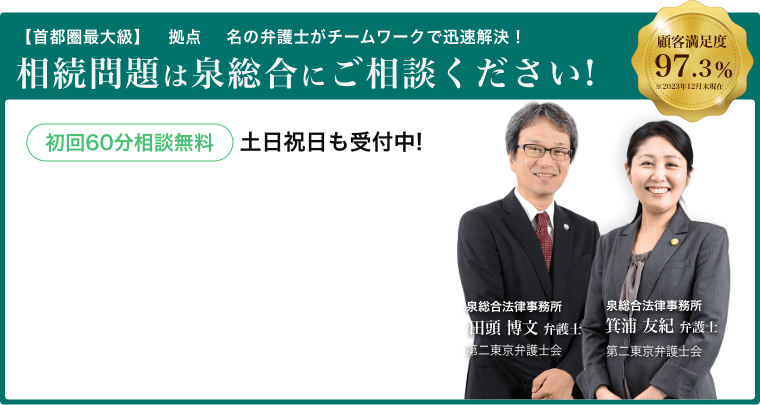遺贈と相続は違うもの?遺贈の種類と活用方法

家族や結婚形態が多様化していることもあり、自分の意思を反映させて財産を分配したい、とお思いの方も増えていると思います。
自分の意志で財産を分配することができる方法には、遺贈や贈与、死因贈与などがあります。
そこで、今回の記事では、この「遺贈」に焦点を当てて、遺贈とはどのような方法か?遺贈と相続の違いは何か?などについて解説します。
1.遺贈とは?
あまり聞き慣れない言葉ですが、被相続人が亡くなった際には、よくでてくる単語です。
まず、この章では、遺贈とは何か?遺贈によって何ができるか?について解説します。
(1) 遺贈の定義
遺贈とは、遺言によって、被相続人の財産の全部またはその一部を、受遺者(遺産を受ける人)に、無償で譲り渡すことを言います。
遺贈は、遺言によって「誰に、どの財産をどれくらい渡すか」を指定して行います。
そのため、法定相続人はもちろんのこと、法定相続人以外にも財産を譲り渡すことができます。
(2) 遺贈の要件
遺贈は遺言に因りますので、遺言を作ることが必須です。
遺言は、被相続人の意思だけで作ることができ(単独行為)、受遺者の合意は必要ありません。
もちろん、その遺言は、遺言として有効な形式で作成されている必要があります。
被相続人が死亡することにより遺言が有効になり、この遺贈の効果が生じます。
(3) 負担付遺贈
「負担付遺贈」というのは、財産を遺贈する代りに、相続発生後、一定の義務を負わせる条件をつけたものです。
例えば、「夫が亡くなった後、残された配偶者の面倒をみる」などの条件です。
(4) 遺贈の放棄
受遺者は、遺贈される財産をそのまま譲り受けてもいいですし、受け取りたくない場合は、「遺贈の放棄」をすることもできます。
負担付遺贈でも、負担・義務を受けることを拒否したいのであれば、遺贈自体を放棄することができます。
なお、遺贈の放棄について詳しくは、「4.遺贈する際・される際の注意点」をご覧ください。
2.包括遺贈と特定遺贈
遺言での遺産分割の指定の仕方によって、遺贈には、大きく分けて2種類あります。
- 包括遺留
- 特定遺留
ここでは、その2つの遺留の違いについて説明します。
(1) 包括遺贈
「遺産の半分」とか「遺産の4分の1」というように、具体的に財産を特定せずに、一定の割合を指定する遺贈を「包括遺贈」と言います。
「遺産の全部」という指定方法もこれに含まれます。
包括受遺者は、相続人と同じ権利や義務が生じるため、譲り受けるプラス財産の割合に応じて、借金などのマイナス財産も合わせて譲り受けなければなりません。
包括遺贈は、主に、次の3種類に分類できます。
全部包括遺贈
「全遺産を甲に遺贈する」と指定して遺贈する方法を、「全部包括遺贈」と言います。
割合的包括遺贈
「全遺産の半分を甲に遺贈する」のように、一定の割合よって行う遺贈を「割合的包括遺贈」と言います。
特定財産を除いた財産についての包括遺贈
「遺産のうち、A県B市C番地の⼟地を甲に遺贈し、それ以外の財産を乙に遺贈する」と指定した場合、この遺言の中の「乙」への遺贈を「特定財産を除いた財産についての包括遺贈」と言います。
また、この例での「甲」に対する遺贈は、遺贈する財産を特定していますので、後段で説明します特定遺贈になります。
(2) 特定遺贈
「財産のうち、A県B市C番地の⼟地を甲に遺贈する」や「D銀行の全預金を乙に遺贈する」というように、具体的に特定して行う遺贈を特定遺贈といいます。
包括受遺者は相続人と同じ権利や義務が生じますが、この特定受遺者についてはそのような權利や義務は生じません。
特定受遺者は特定の遺産しか継承しないので、借金などのマイナス財産を継承することはありません。
3.遺贈と相続との相違点
遺贈とよく似たものに「相続」があります。
ここでは、遺贈と相続の相違点について説明します。
(1) 財産を譲り受ける人
相続は、法律で決まっている法定相続人にしか財産を譲り渡すことができません。
一方で、遺贈は、遺言で「誰に、どの財産を渡すか」を指定しますので、法定相続人以外にも財産を譲り渡すことができます。
(2) 遺言は必要か
法定相続人が相続する場合は、法的に被相続人の財産を譲り受ける權利がありますので、遺言は必ずしも必要がありません。
遺言がない場合は、法定相続人の間で遺産分割協議を行って、遺産をどのように分けるかを決めます。
一方で、遺贈は、遺言を作成することが必須です。
(3) 代襲相続の対象か
代襲相続とは、法定相続人(例えば、子ども)がすでに死亡している場合、子どもの子ども(被相続人の孫)が代りに相続できる權利です。
相続は代襲相続の対象です。
一方で、遺贈については、代襲相続は発生しません。
遺贈は、被相続人と受遺者との間の法律行為であり、被相続人よりも前に受遺者の方が亡くなってしまうと、その遺贈は無効として扱われるためです。
なお、遺言には「予備的条項」というのがあり、遺言書を作成した後に一定の事由が発生する場合(今回の場合は、受遺者の死亡)に備えて、別の条項を定めることができます。
予備的条項により、受遺者の死亡に備えて、受遺者の子などを新たな受遺者として指定しておく事ができます。
このようにしておけば、代襲相続と同様に、財産を移転させることができるようになります。
4.遺贈する際・される際の注意点
ここでは、遺贈を行う場合の注意点についてみていきます。
(1) 遺留分侵害額請求の対象となる
遺留分とは、法律上保障された、被相続人の兄弟姉妹以外に認められた相続財産を受け取れる最低限の権利のことです。
遺贈は、被相続人の相続財産を譲り受けることになりますので、相続と同じように、法定相続人の遺留分を侵害した場合は、遺留分侵害請求の対象になります。
(2) 遺贈する財産が賃借権の場合、賃貸人の承諾が必要
原則、賃借権の譲渡の場合は,賃貸人(地主)の承諾がないと、その賃借権契約が解除される可能性があります。
相続・遺贈により法定相続人が譲り受ける場合は、賃借権の譲渡には該当しませんので、賃貸人の承諾は必要ありません。
一方で、遺贈で法定相続人以外の人が譲り受ける場合は、贈与として扱われて、賃貸人の承諾が必要になります。
(3) 相続税の2割加算の対象となる場合がある
遺贈で法定相続人が譲り受ける場合は、相続と同じで、2割加算に対象になりません。
一方で、法定相続人以外に遺贈する場合は、2割加算の対象になり、相続税が2割加算されてしまいます。
(4) 相続税の基礎控除の計算に注意
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数により計算します。
そのため、法定相続人以外の人が遺贈により遺産を譲り受けても、基礎控除額を計算する法定相続人の数に含まれませんので、何人に遺贈しても、基礎控除額に影響しません。
ちなみに、法定相続人が相続放棄をした場合であっても、その人が放棄しなかったとした時の法定相続人の数で基礎控除額を求めます。
(5) 相続人以外の受遺者は不動産取得の課税対象になる
通常、不動産を取得した場合は不動産取得税がかかりますが、法定相続人が取得する場合は、この不動産取得税が免除されます。相続人に対する遺贈の場合も、同様の取り扱いとなります。
一方で、法定相続人以外が取得する場合は、通常の税率で不動産取得税が課されます。
不動産取得税
| 法定相続⼈ | ⾮課税 |
|---|---|
| 法定相続人以外 | 4.0%(令和3年3月31日までは3.0%) |
(6) 登録免許税の税率
不動産を登記する場合は、不動産取得税と同様に、登録免許税も課されます。
法定相続人が不動産を取得する場合は、この登録免許税の税率が優遇されていますが、法定相続人以外が不動産を取得する場合は、通常の税率が適用されます。
登録免許税
| 法定相続⼈ | 0.4% |
|---|---|
| 法定相続人以外 | 2.0% |
(7) 特定遺贈には農地法3条の許可が必要
原則、農地の権利の移転・設定を行う場合は、農地法3条の許可を得る必要があります。
ただし、相続による場合は、農地法3条の許可が必要ないとされています。
遺贈の場合、包括遺贈(財産の取得割合を示して遺贈する方法)では、受遺者は相続人と立場上は 同じになりますので、農地法第3条の許可申請は不要です。
一方で、特定遺贈(農地を特定して遺贈する方法)の場合は、農地法第3条の許可申請が必要です。
(8) 遺贈の放棄の方法は包括遺贈か特定遺贈かで異なる
相続と同じように、遺贈も放棄ができます。
包括遺贈の場合は、相続人と同じように、3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し放棄の申請をします。
特定遺贈の場合は、相続人に「遺贈を放棄する」旨を伝えるだけで放棄できます。期間の定めもありません。
ただし、相続人から「遺贈を受けるかどうかの確認」の催告がきた場合は、期間内に返事しないと、遺贈を承認したものとみなされますので、注意が必要です。
5.まとめ
今回は、遺贈とは何か、相続と贈与の違いについて見てきました。
遺贈先が法定相続人の場合は相続と大差ありませんが、法定相続人以外に遺贈する場合は、いくつか違いがありますので、注意が必要です。
また、遺贈にもいくつかの種類があり、受遺者の權利や義務が変わってきます。
この点にも気を配る必要があります。
遺言による遺贈をお考の方は、相続についての豊富な専門知識を持った泉総合法律事務所に是非一度ご相談ください。