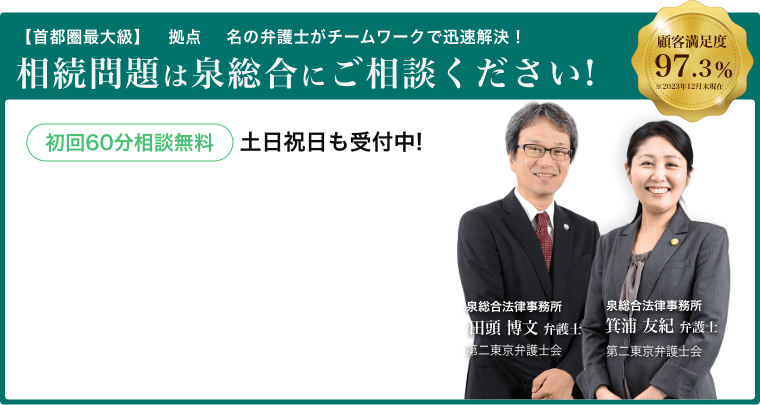贈与税の基礎控除110万円は廃止される?

令和4年度(2022年度)の税制改正に関しては、相続税の節税策として世間に浸透している「暦年贈与」の見直しが議論されていました。
結果的に、令和4年の税制改正には盛り込まれずに終わりましたが、引き続き「暦年贈与」について、廃止を含めた見直しが行われる可能性は残っています。
今回は、将来的な税制改正の焦点となっている、いわゆる「暦年贈与」の概要や改正の見通し、さらに暦年贈与以外に考えられる相続税対策などについて解説します。
1.「暦年贈与」による節税について
(1) 「暦年贈与」とは?
「暦年贈与」とは、贈与税の非課税枠を活用した節税目的の贈与のことです。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の金額に対して課税する、「暦年課税」という方式が原則となっています。
贈与税の暦年課税を受ける場合、年間110万円の基礎控除が設けられています。
そのため、毎年110万円までの贈与については、贈与税が非課税となります。
この贈与税の非課税枠を利用すると、110万円までの金額を毎年贈与し続ければ、無税で大きな金額の財産を移転することができるのです。
また実際には、110万円を少し超える程度の贈与を毎年行う節税対策もよく見られます。
贈与税が課税されるのは、110万円を超える部分の金額に対してのみですので、この場合もきわめて軽い税金で財産を移転することが可能です。
なお、暦年課税とは異なる課税方法である「相続時精算課税」を選択している場合には、年間110万円の基礎控除を活用した暦年贈与を行うことはできません。
(2) 暦年贈与を活用した相続税の節税シミュレーション
暦年贈与による相続税対策を行うことで相続税額をどの程度圧縮できるのか、シンプルなモデルケースを用いてシミュレーションしてみましょう。
<設例>
被相続人は、55歳から30年間にわたって、子Aに対して毎年110万円の暦年贈与を行い、85歳で亡くなった。子Aは、被相続人の唯一の法定相続人である。
被相続人が亡くなった時点で所有していた財産は、総額1億円だった。
上記以外に、相続税の課税対象財産および適用可能な控除(基礎控除を除く)はないものとする。
設例のケースでは、55歳から30年間にわたって、贈与税の基礎控除を活用した、総額3,300万円のAに対する暦年贈与が行われています。
この3,300万円は、すべて贈与税の基礎控除の範囲内なので、贈与税は課税されません。
一方、相続税については、被相続人が亡くなった時点で所有していた1億円に、相続開始前3年以内に贈与された330万円を加え、総額1億330万円が課税対象となります(相続税法19条1項)。
ただし、相続税の基礎控除3,600万円が控除されるため、相続税の課税対象は6,730万円です。
これに相続税の税率表を適用すると、Aが納付すべき相続税額は、以下のとおり計算されます。
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁
相続税額(暦年贈与あり)
=6,730万円×30%-700万円
=1,319万円
これに対して、暦年贈与を全く行わなかったと仮定すると、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産は1億3,300万円となります。
相続税の基礎控除3,600万円を控除すると、相続税の課税対象は9,700万円です。
したがって、暦年贈与がなかったと仮定した場合の相続税額は、上記の税率表を適用した結果、以下のとおり計算されます。
相続税額(暦年贈与なし)
=9,700万円×30%-700万円
=2,210万円
このように、30年間にわたって総額3300万円の暦年贈与を行ったところ、「(2210万円-1319万円=)891万円」の相続税を節約できる結果となりました。
(3) 暦年贈与を行う際の注意点|定期贈与
暦年贈与は、相続税の節税策としてシンプルかつ有用です。
しかし、毎年の暦年贈与が「定期贈与」であると税務署に評価されると、巨額の追徴課税を受けてしまうおそれがあります。
定期贈与とは、「毎年決まった金額を贈与すること」について、贈与者と受贈者の間であらかじめ合意しておく契約を意味します。
たとえば、「10年間にわたって毎年110万円を贈与する」という内容の契約は、定期贈与に当たります。
定期贈与の場合、初年度に全額を贈与したものとして、贈与税が課税されることになっています。
したがって、「10年間にわたって毎年110万円を贈与する」という合意があったとみなされた場合、実際の金銭の授受は毎年110万円ずつであっても、贈与税の計算上は、初年度に1100万円の贈与があったものとして課税が行われてしまうのです。
暦年贈与として毎年110万円を贈与する場合、同じ金額・同じような時期の贈与ということで、定期贈与と評価されやすい傾向があるため注意しなければなりません。
定期贈与としての課税を回避するためには、以下の対策を組み合わせて活用することが有効考えられます。
- 毎年贈与契約書を作成する(確定日付やタイムスタンプを付しておくことが望ましい)
- 毎年111万円以上の贈与を行い、贈与税の申告を行う
- 受贈者が、贈与を受けた金銭を実際に管理・消費する(いわゆる「名義預金」とみなされないための対策)
暦年贈与によって、想定どおりの節税効果を得るためには、法務・税務の観点から適切な手続きを踏むことが大切ですので、事前に弁護士などへご相談ください。
2.贈与税の基礎控除110万円は廃止される?
暦年贈与のポイントになっている贈与税の基礎控除110万円は、近年の税制改正の議論の中で見直しが検討されています。
(1) 令和4年税制改正大綱で見直しに言及
2021年末に政府・与党がまとめ、閣議決定された「令和4年度税制改正大綱」では、贈与税の基礎控除110万円について、以下のとおり見直しに言及されています。
「……高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再配分機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。
このため、資産の再配分機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進課税を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。……」
出典:令和4年度税制改正大綱|自由民主党・公明党 10頁
上記のとおり、令和4年度税制改正大綱では、贈与税の基礎控除110万円を活用した暦年贈与が「相当に高額な相続財産を有する層」にとって有利な制度であり、「格差の固定化」に繋がり得ることを示唆しています。
令和4年度税制改正には、具体的な見直しが盛り込まれることはありませんでした。
しかし、今後は「本格的な検討を進める」とされているとおり、暦年贈与による節税策にメスが入る可能性は大いにあるでしょう。
(2) 見直し時期は不透明
税制改正は毎年行われているため、暦年贈与の見直しについても、早ければ令和5年度(2023年度)から可決・施行される可能性があります。
その一方で、暦年贈与の見直しの在り方についても議論が固まっていないことから、検討に時間を要することも想定され、現段階で見直し時期は不透明です。
いずれにしても、暦年贈与の見直しが行われれば、相続税対策のあり方も大きく変容せざるを得ないので、今後の税制改正の動向を注視する必要があります。
3.暦年贈与の他に考えられる相続税対策
現段階では、将来的に暦年贈与が全くできなくなってしまうのか、それとも形を変えて残るのかはわかりません。
しかし、少なくとも縮小の方向で見直しが行われる可能性が高い状況と言えます。
もし暦年贈与ができなくなった場合、他に考えられる相続税対策としては、以下に挙げるパターンが考えられます。
他にもさまざまな相続税対策があり、状況によって有効な対策は異なるため、税理士や弁護士のアドバイスを受けながら適切な対策を講じましょう。
(1) 別の非課税制度を活用して生前贈与を行う
令和4年度(2022年度)の税制では、一定の目的による贈与については、以下のとおり暦年贈与とは別枠での非課税制度が設けられています。
①住宅取得資金一括贈与の非課税特例
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅用家屋の取得資金の贈与を受けた場合、最大500万円(良質な住宅については1000万円)まで贈与税が非課税となります。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
②教育資金一括贈与の非課税特例
30歳未満の方が、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金として金銭の贈与等を受けた場合、最大1500万円まで贈与税が非課税となります。
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
③結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例
20歳以上50歳未満の方が、父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金として金銭の贈与等を受けた場合、最大1000万円まで贈与税が非課税となります。
参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
もしこれらの非課税制度が暦年贈与の見直し後も残っていれば、節税対策として効果的に活用しましょう。
ただし、令和4年度税制改正大綱では、上記の非課税制度についても、以下のとおり見直しに言及されています。
そのため、暦年贈与の見直しと併せて、上記の非課税制度も見直される可能性がある点に注意が必要です。
「……あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。」
出典:令和4年度税制改正大綱|自由民主党・公明党 10頁
(2) 生命保険金の相続税非課税枠を活用する
被相続人が保険料を負担し、被相続人の死亡によって受け取った生命保険金(死亡保険金)は、原則として相続税の対象となります。
しかし、被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金については、相続税の非課税枠が設けられています。
この非課税制度を利用すると、相続人を受取人として生命保険に加入しておけば、相続税の課税額を減らすことができます。
 [参考記事]
生命保険の活用が相続税対策になる!
[参考記事]
生命保険の活用が相続税対策になる!
相続税が非課税となる生命保険金の金額は、最大で「500万円×法定相続人の数」です。
なお、法定相続人の数には相続放棄をした者も含みます。
ただし、被相続人の養子については、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までしか、法定相続人の数に含めることができません。
(3) 養子縁組をして相続税の基礎控除額を増やす
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が設けられており、この金額以下の相続財産については、相続税が非課税となります。
養子縁組をして子(=法定相続人)が増えれば、基礎控除額が増えるため、相続税の節税に繋がります。
ただし、被相続人の養子については、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までしか、法定相続人の数に含めることができない点に注意が必要です。
(4) 相続税を軽減できる特例を活用する
他にも、相続税の節税効果がある各種の特例のうち、利用できるものは積極的に利用しましょう。
効果的な相続税の節税策としてよく知られているものには、たとえば「小規模宅地等の特例」があります。
相続開始の直前において、被相続人や生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等を相続した者は、「小規模宅地等の特例」を活用することで、相続税を軽減できます(配偶者以外が相続する場合、取得者側で一定の要件を満たすことが必要です)。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
 [参考記事]
小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引
[参考記事]
小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引
(5) 税理士等に不動産や未公開株式の評価を依頼する
不動産や未公開株式など、客観的な市場価格が存在しない財産については、価値評価の方法によって相続税額が大きく変わります。
税理士や税理士業務を行う弁護士に依頼すれば、不動産や未公開株式などについて複数の評価方法を検討し、もっとも合理的な評価方法を用いて相続税額を適正化することが可能です。
4.生前の相続対策は弁護士にご相談ください
暦年贈与が将来的に廃止された場合、相続税の節税策の幅は狭まってしまうでしょう。
しかしその中でも、効果的に次世代へ財産を引き継ぐための節税策は残っています。
税理士・弁護士にアドバイスを求めながら、ご家庭のご状況に合わせた適切な相続税対策を講じてください。