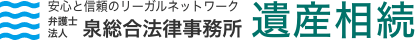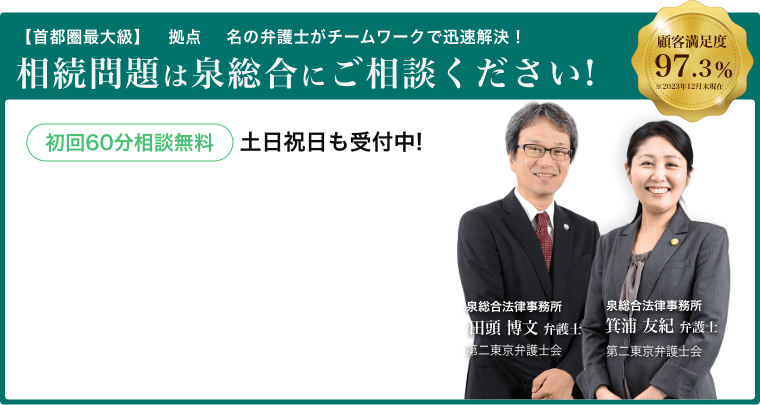法定相続情報証明制度とは|デメリットや必要書類、使えないケース

平成29年(2017年)5月29日からスタートした「法定相続情報証明制度」を利用することにより、相続手続きの提出書類を大幅に簡略化できるようになっています。
特に金融機関での相続手続きが複数発生する際にこの制度を利用すると、大きなメリットにあずかることができます。
この記事では、法定相続情報証明制度の概要・メリット・デメリット・利用方法などを解説します。
【参考】「法定相続情報証明制度」について|法務局
1.法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、被相続人・相続人間の続柄について、法務局所属の登記官による証明を受けられる制度です。
民法上、相続権は「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」など、被相続人との続柄に基づいて発生します。
そのため、金融機関等で相続手続きを行う際には、被相続人・相続人間の続柄を証明する書類を提出しなければなりません。
従来は、複数の戸籍謄本・除籍謄本等を用いて、全相続人についての続柄を証明しなければなりませんでしたが、書類を収集する手間が大きいなどのデメリットがありました。
法定相続情報証明制度を利用すると、法務局の登記官により、簡易な形で被相続人・相続人間の続柄に関する証明が行われます。
そのため、同制度の利用によって、相続手続きに関する利便性の向上が期待されています。
2.法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度を利用すると、各手続きにおける手間・時間・費用を節約できるメリットがあります。
(1) 相続手続きの必要書類を減らすことができる
従来の相続手続きでは、戸籍書類を複数の自治体から取り寄せて提出しなければならず、必要書類も膨大になりがちでした。
一方で、法定相続情報証明制度を利用すると、法務局の登記官から「法定相続情報一覧図」の写しが発行されます。被相続人・相続人間の続柄に関しては、その写しにすべて記載されており、相続手続きの必要書類を減らすことができます。
従来の戸籍についての複数の書類を、法定相続情報一覧図の写しで代用すれば、1か所の登記所で交付を受けられるうえに、部数も1部で済みます。
このように、法定相続情報証明制度を利用することによって、金融機関等で相続手続きを行う際に提出する戸籍書類を、大幅に簡略化することが可能になりました。
そのうえ、法定相続情報一覧図の写しは、金融機関のほか、相続登記や相続税申告、年金手続きなどにも利用できます。
(2) 相続手続きの期間が短縮される
法定相続情報一覧図の写しは、相続権の決定に関する情報が1部にまとまった公的な証明書です。
そのため、金融機関等が相続権の有無について審査を行う際にも、内容の確認がしやすくなり、審査期間が短縮される傾向にあります。
また、従来の実務では、戸籍書類一式を1つの金融機関等に提出し、書類の返却を待って次の金融機関等へ提出するというように、1つずつ順番に手続きを進めなければなりませんでした。
これに対して、法定相続情報一覧図の写しは、必要な手続きの数だけ発行を受けることができるので、複数の機関で手続きを同時に進めることができます。
上記の理由から、法定相続情報証明制度を利用すると、相続手続きにかかる期間を大幅に短縮できるメリットがあります。
(3) 法定相続情報一覧図の写しを発行するための費用は無料
法定相続情報一覧図の写しの発行を受ける際には、手数料が一切かかりません。
戸除籍謄本を個別に取り寄せる場合には、1通あたり300円~750円の手数料がかかることを考えると、費用面でも法定相続情報証明制度を利用するメリットがあるといえるでしょう。
3.法定相続情報証明制度のデメリット
法定相続情報証明制度は非常に便利な制度であり、利用のデメリットはほとんどありません。
強いて言えば、必要書類を取り寄せて法定相続情報一覧図を自分で作成する必要があるため、最初の手間がかかる点が挙げられます。
しかし、法定相続情報一覧図の作成については、以下の専門家に依頼することも可能です。
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
もしご自身で作成する時間がない場合や、作成方法がわからない場合には、弁護士などに作成をご依頼ください。
4.法定相続情報証明制度を利用する流れ
法定相続情報証明制度を利用するには、法務局において利用申出の手続きをとる必要があります。
必要書類の準備から金融機関等への提出まで、法定相続情報証明制度を利用する際の流れを見てみましょう。
(1) 法定相続情報証明制度の必要書類を収集する
法定相続情報証明制度の利用申出をするに当たっては、相続情報を証明するための公的書類を揃えなければなりません。
法定相続情報証明制度の利用申出に必要となる書類は以下のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
出生してから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本・除籍謄本が必要です。
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
②被相続人の住民票の除票
被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。
③相続人の戸籍謄本または抄本
相続人全員について、現在の戸籍謄本または抄本が必要です。なお証明日は、相続人が死亡した日以後である必要があります。
各相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
④申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
法定相続情報証明制度の利用申出を行う代表者について、以下のいずれか1つの書類が必要です。
- 運転免許証の表裏両面のコピー
- マイナンバーカードの表面のコピー
- 住民票の写し など
なお、以下の書類の提出も必要となる場合があります。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
⑤各相続人の住民票の写し
各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。
なお、相続人の住所記載は任意なので、記載しない場合は不要です。
代理人が利用申出の手続きをする場合
⑥委任状
⑦申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
親族が代理人となって利用申出を行う場合に必要です。該当の市区町村役場で取得できます。
⑧資格代理人団体所定の身分証明書の写し
弁護士などが代理人となって利用申出を行う場合に必要です。取得方法は、依頼先の専門家にご確認ください。
被相続人の住民票の除票を取得できない場合
⑨被相続人の戸籍の除票
住民票の除票が廃棄されているなどの理由で取得できない場合には、戸籍の除票を提出する必要があります。
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
(2) 法定相続情報一覧図を作成する
上記の書類と併せて、申出人の側で作成した法定相続情報一覧図を登記所に提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の様式・記載例は、以下の法務省HPで紹介されています。
作成方法がわからない場合や不安がある場合には、弁護士などの専門家にご相談ください。
【参考】主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局
(3) 法務局に利用申出を行う
法定相続情報一覧図を含めた必要書類が揃ったら、法務局に設置された登記所に利用申出を行います。
申出先は、以下のいずれかの地を管轄する登記所となり、申出人が選択できます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
(4) 登記官による確認・法定相続情報一覧図の保管
法定相続情報証明制度の利用申出を受けた登記官は、戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図を照らし合わせて、法定相続情報一覧図の認証を行います。
認証が完了した法定相続情報一覧図の原本は、登記所において5年間保管されます。
(5) 法定相続情報一覧図写しの交付・戸除籍謄本等の返却
申出人は、相続手続きにおいて必要な通数分、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。
なお、追加で法定相続情報一覧図の写しが必要となった場合には、再交付を受けることも可能です。
法定相続情報証明制度の利用申出に用いた戸除籍謄本等は、法定相続情報一覧図の写しが交付される際に併せて返却されます。
(6) 相続手続きが必要な金融機関等への提出
登記官から交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きが必要となる金融機関等に提出します。
5.法定相続情報証明制度についてのよくある質問(FAQ)
法定相続情報証明制度が開始されたのは、2017年5月29日からですが、開始当初は、法定相続情報一覧図を使用した相続手続きが認められないなど、混乱もあったようです。 しかし、法定相続情報証明制度は、審査時間の短縮ができるといった金融機関側のメリットも多く、開始からすでに相当の期間が経過しているため、少なくともみずほ銀行や三菱UFJ銀行、三井住友銀行といった大手で使えない銀行はありません。 証券会社にしても、野村証券や大和証券、三菱UFJ証券、SMBC日興証券、みずほ証券といった大手証券会社では使用可能です。 このように大半の金融機関では、法定相続情報一覧図の利用が可能になっていると推測されます。 もし、法定相続情報一覧図が使えるかどうか不安な方は、先に被相続人が口座を持っていた金融機関に問い合わせてから利用するといいでしょう。 法定相続情報証明制度はメリットの多い制度ですが、被相続人が日本国籍を有しない場合には、法定相続情報証明制度を利用することができません。 そもそも日本国籍を有しない者には戸籍謄本が存在しないため、必要書類を揃えることができないからです。 相続放棄や廃除があった場合でも、戸籍にその旨は記載されません。したがって、こうした相続人については、法定相続情報一覧図には記載することになります。 こうしたケースで法定相続情報一覧図を使いたいときには、相続放棄や廃除があった相続人について相続放棄申述受理証明書や廃除の確定判決の謄本などを一緒に提出して相続手続きを行います。 一方で相続廃除では、戸籍に相続人廃除の記載がなされることになり、一覧図には廃除された推定相続人を代襲相続する者がいる場合には、廃除された推定相続人を「被代襲者」とのみ記載し、代襲者がいなければ廃除された推定相続人を記載しません。 なお、法務省は、「被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができる。」(※)としています。 ※ 【出典】「~法定相続情報証明制度について~(令和3年4月1日改訂)」|法務省民事局
法定相続情報証制度の銀行などの金融機関における対応状況は?
法定相続情報一覧図が使えないケースってあるの?
相続放棄や相続廃除・欠格などがあった場合は相続情報一覧図にどう記載する?
6.法定相続情報証明制度の利用は弁護士に相談を
法定相続情報証明制度を便利に活用できるのは、たとえば以下のようなケースです。
- 被相続人が複数箇所に預金口座を有している場合
- 相続人の数が多く、戸除籍謄本の束が膨大になる場合
- 相続登記、相続税申告、年金手続きなどが複数必要になる場合
これらのケースでは、法定相続情報証明制度を利用することで手続きの手間や時間を大幅に節約できます。
法定相続情報証明制度の利用に当たっては、法定相続情報一覧図の作成が最大のネックとなります。
この点、弁護士などの専門家にご相談いただければ、スムーズに戸除籍謄本等を収集したうえで法定相続情報一覧図を作成し、迅速に相続手続きを完了できるようにサポートいたします。
法定相続情報証明制度の利用をご検討中の方は、一度泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。