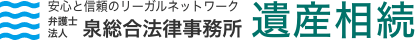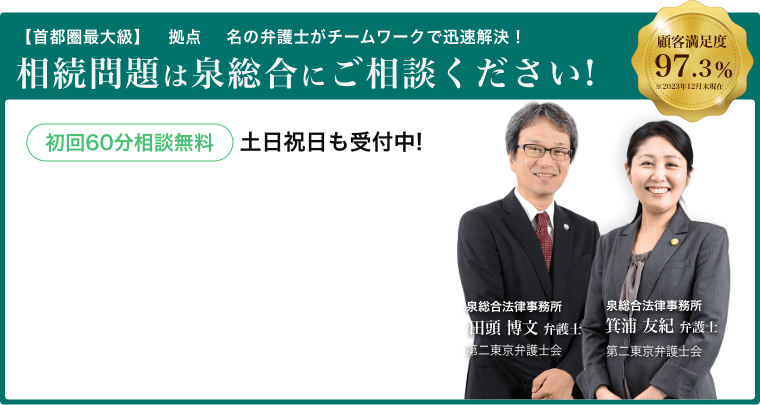任意後見制度のメリット・デメリットや成年後見・家族信託との違い

世界保健機構や国連の定義によると、65歳以上の高齢者の全体の人口に占める割合が7%を超えた社会を高齢化社会、14%を超えた社会を高齢社会、さらに21%を超えた社会を超高齢社会といいます。
総務省の推計によれば、2022年時点での日本の高齢化率は、29.0%となり、超高齢社会に突入しています。
高齢化に伴って心配なのが、認知症などによって支援を必要とする高齢者の増加です。
ご自分が認知症になるとご家族のサポートを受ける必要があり、元気なうちから準備しておくことが重要です。
そこで今回は、判断能力の低下に備えて後見人を決めることができる制度、「任意後見制度」について解説します。
1.任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来の認知症などによる判断能力低下に備えて、本人に十分な判断能力があるうちに任意後見受任者(任意後見人となる方)と委任する事務内容について契約し、本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見人が契約によって決められた「財産管理」と「身上監護」を本人に代わって開始する成年後見制度の一種です。
(1) 任意後見人はいつから委任事務を開始する?
委任事務の開始には、家庭裁判所による後見監督の選任が必要です。本人の判断能力が低下すると任意後見受任者が後見監督人の選任申し立てを行い、家庭裁判所が後見監督人を選任すると任意後見契約の効力が生じ、委任事務が開始されることになります。
通常の委任契約とは異なり、家庭裁判所から選任された任意後見監督人が受任者(任意後見人)の事務を監督しますので、本人の判断能力が低下した後の受任者による代理権濫用のおそれも回避することができる制度です。
本人の意思を十分に反映させつつ、代理権濫用のおそれも回避することができる制度であるため、超高齢社会の現代においては積極的に活用が期待される制度であるといえます。
(2) 任意後見人になれる人
任意後見人には判断能力のある成人であれば、以下の欠格事由に該当しない限り誰でもなることができます。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所から解任などをされたことがある法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して裁判をしたことがある者、その配偶者と直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
もちろん、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。
(3) 任意後見人ができること
任意後見人ができるのは、任意後見契約で定めた「財産管理」と「身上監護」です。
財産管理としては、例えば被後見人の預貯金の払い戻しや預け入れや、年金や手当の受給、公共料金の支払いといったことから不動産などの重要な財産の管理や売却といったことが挙げられます。
身上監護には、医療・介護サービス利用のための契約手続きや、定期的な訪問によって本人の健康状態や、生活環境の確認などが含まれることになります。
ただし、被後見人の看護自体は、身上監護に含まれてはいません。
2.任意後見制度と成年後見制度の違い
任意後見制度と法定後見制度とはどのような違いがあるのでしょうか。
(1) 成年後見制度とは
成年後見制度とは、家庭裁判所により選任された後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)が、既に判断能力の低下した本人の利益を考えながら、本人が法律行為をする際に同意をしたり、本人が後見人などの同意を得ないで行った法律行為を取り消したり、本人を代理して法律行為をしたりすることで、本人を保護する制度のことをいいます。
成年後見制度は、本人がどの程度の判断能力を有しているかによって、以下の3種類に分類されます。
- 後見-判断能力が欠けているのが通常の方(例、重度の認知症)
- 保佐-判断能力が著しく不十分な方(例、中程度の認知症)
- 補助-判断能力が不十分な方(例、軽度の認知症)
 [参考記事]
家族信託と成年後見の違い|メリット・デメリットを比較
[参考記事]
家族信託と成年後見の違い|メリット・デメリットを比較
(2) 成年後見制度との違い
任意後見制度と法定後見制度には、主に以下のような違いがあります。
| 任意後見制度 | 成年後見制度 | |
|---|---|---|
| 利用時期 | 本人に十分な判断能力がある時点 | 本人の判断能力が低下した時点 |
| 後見人の選任主体 | 本人 | 家庭裁判所 |
| 後見人の権限 | 任意後見契約によって定めた行為 | 民法所定の法律行為 |
| 取消権の有無 | ない | ある |
①利用時期
任意後見制度は、本人に十分な判断能力がある時点で将来の財産管理などに関する事務を行うものや行われる事務の内容をあらかじめ決めておくことができる制度です。
これに対して成年後見制度は、本人の判断能力が低下した時点で本人の親族などの家庭裁判所への申立てによって利用される制度です。
そのため、任意後見制度の方が、判断能力が低下した時点の財産管理などについて本人の意思を反映させやすい制度だといえます。
②後見人の選任主体
任意後見制度は、任意後見契約によって本人が後見人を選ぶことができます。信頼できる親族や専門家(弁護士、司法書士など)を任意後見人に選任することができるため、将来の財産管理などの場面で本人の意向を反映させやすくなります。
これに対して、成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を決めることになります。
成年後見制度の申立時に後見人の候補者を立てることができますが、裁判所はそれとは異なる人を後見人に選任することもありますので、必ず希望が通るとは限りません。
③後見人の権限
任意後見制度は、本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務に関してあらかじめ任意後見契約で定めた範囲で任意後見人に権限が与えられます。
これに対して、成年後見制度では、民法が定める一定の権限や家庭裁判所の審判によって与えられた範囲の権限を行使することができます。
④取消権の有無
任意後見制度では、任意後見人に与えられる権限は代理権のみであり、任意後見契約によっても取消権を与えることはできません。
これに対して、成年後見制度では、補助人や保佐人には限定がありますが、取消権が与えられています。
3.家族信託と任意後見人制度との違い
(1) 家族信託とは
家族信託とは、特定の目的に沿って委託者が所有する財産の管理・運用・処分する権限を契約により家族や親族に受託者として与え、受益者がその利益を享受する信託を指します。
受託者は信託契約の目的に従って、管理・運用・処分するため、委託者に判断能力があるうちでなければ、家族信託を組成することはできません。
例えば、委託者である父親が自分のアパートやマンションを信託財産、自分の長男を受託者、受益者をご自分として家族信託を設定すると、父親自身が認知症になっても、アパートやマンションから入る収入で介護サービスを受けることができます。
さらに父親の配偶者を第2受益者として設定しておけば、父親が亡くなった後も、妻は生活費の心配をする必要がありません。
このようなことから家族信託は、認知症対策として注目されています。

 [参考記事]
家族信託とは?メリット・デメリットや活用方法をわかりやすく解説
[参考記事]
家族信託とは?メリット・デメリットや活用方法をわかりやすく解説
(2) 任意後見制度と家族信託の違い
任意後見制度も家族信託も認知症対策として有効です。
では、その違いはどこにあるのでしょうか?簡単にまとめておきましょう。
| 家族信託 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| 制度概要 | 信託契約に基づき、受託者が受益者のために、委託者財産の管理・運用・処分を行う | 任意後見契約に基づき、任意後見人が本人の財産管理・身上監護を行う |
| 財産管理者 | 未成年者以外は契約によって自由に選択可能(※) | 判断能力のある成人であれば誰でも選任可能 |
| 財産管理者の権限内容 | 契約によって自由に設計可能 | |
| 財産の所有者 | 受託者(ただし、受益者のために管理処分権を行使するを負う) | 被後見人(本人) |
| 開始時期 | いつでも可(遺言により設定することも可) | 本人が事理弁識能力を欠く常況となった後 |
| 身上監護権の有無 | なし | あり |
| ランニングコスト | 信託契約で定める | 任意後見契約で定める |
| 解消の可否 | 信託契約解除により可能 | 任意後見契約の効力発生前 本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる(任意後見契約に関する法律9条1項) 任意後見契約の効力発生後 本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる(同法2項) |
※ただし、「信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない(信託業法3条)」と定められており、弁護士などの専門家を受託者とすることはできません。
この他に任意後見制度と家族信託の違いとしては、任意後見制度が財産管理と身上監護を目的としているため、任意後見人が財産の積極的な運用ができないのに対し、家族信託では受託者が積極的な運用や投資ができる点にあります。
4.任意後見制度の種類
任意後見制度には、即効型・将来型・移行型といった3つの種類があります。
本人の健康状態や生活状態にあわせて、どのタイプの任意後見制度が合っているかを検討しましょう。
(1) 即効型
即効型とは、任意後見契約を締結した後、すぐに家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申立てを行うというものです。
任意後見契約時にすでに本人の判断能力が低下し始めており、すぐにでも任意後見を始めたいという場合にはこれを選ぶとよいでしょう。
なお、軽度の認知症であれば、任意後見契約自体は可能です。
(2) 将来型
一般的に任意後見契約を締結する場合には、生活支援、療養看護、財産管理などに関する事項について委任契約を締結します。
しかし、将来型は、後述する「移行型」のように生活支援、療養看護、財産管理などに関する委任契約は締結せずに、任意後見契約のみを締結するというものです。
(3) 移行型
任意後見契約の中でも最も使い勝手が良いのが移行型のタイプです。任意後見契約の締結と同時に、生活支援、療養看護(見守り契約)、財産管理などに関する委任契約の締結をするというものです。
それによって、本人の判断能力があるうちは当初の委任契約に基づく見守り事務などを行いながら、本人の判断能力が低下した後に任意後見に移行することになります。
判断能力があるといっても、年齢を重ねるうちに身体機能が低下して、それまで自分でできていたことが難しくこともあります。
現在のサポートともに将来の財産管理もお願いしたいという場合には有効な手段です。
5.任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
任意後見制度の利用をお考えの方は、メリットとデメリットを比較しながら検討してみましょう。
(1) 任意後見制度のメリット
任意後見制度のメリットとしては、以下のものが挙げられます。
①任意後見人を自分で選ぶことができる
任意後見制度では、判断能力が十分ある時点で自らの希望する人を任意後見人にすることができます。
親族はもちろん、信頼できる第三者や、弁護士などの専門家も選任可能です。
②任意後見人の権限もあらかじめ決めることができる
任意後見人の権限は、任意後見契約によって定められた事項に限られます。
そのため、自分が希望する支援の内容をあらかじめ契約に盛り込んでおくことによって、自分の判断能力が低下した後も自分の意思を反映させた財産管理などを行うことが可能になります。
③後見監督人による監督が期待できる
任意後見制度では、任意後見人の事務処理を家庭裁判所によって選任された後見監督人が監督することになります。
本人の判断能力がなくなった後も、任意後見人による不当な財産処分を防止することが可能となりますので、安心して利用をすることができます。
(2) 任意後見制度のデメリット
任意後見制度のデメリットとしては、以下のものが挙げられます。
①死後の処理を委任することができない
任意後見人の権限は、本人の死亡によって終了します。
そのため、本人が死亡した後の葬儀、自宅の片づけ、相続手続きなどを任意後見人に委任することはできません。
②取消権がない
任意後見人には、成年後見人に認められている取消権が存在しません。
本人が消費者被害になどによって不利な契約を締結してしまったとしても、任意後見人には、その契約を取り消す権限はありません。そのため、本人の財産を保護するためには不十分なこともあります。
6.任意後見制度を利用するための手続きの流れ
最後に、任意後見制度を利用する際の一般的な手続きの流れとしては以下の通りです。
(1) 任意後見契約の締結
任意後見契約の締結は、公正証書によって行います。公証人が関与することによって本人の真意による適正かつ有効な契約が締結されることを制度的に担保することが目的です。
任意後見契約を締結し、公正証書の作成が完了すると、公証人から登記申請がなされて、登記事項証明書に任意後見人である旨が記載されることになります。
(2) 任意後見監督人選任の申立
任意後見契約の締結後、本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
任意後見監督人を選任するためには、少なくとも本人の判断能力が成年後見の「補助」に相当する程度になっていることが必要になります。
(4) 任意後見契約の発効
任意後見契約は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力を生じることになります。
任意後見契約が発効した後は、任意後見人は、任意後見契約に従って事務処理を行い、定期的に任意後見監督人に事務処理状況を報告しなければなりません。
7.任意後見制度についてのよくある質問(FAQ)
メリットでも触れた通り、任意後見制度では任意後人を自由に選ぶことができます。 一方で、法定後見制度では成年後見人を最終的に家庭裁判所が選任します。 また、家族信託では任意後見制度にある「身上監護」を設定することができません。そのため、家族信託の補助的な手段として任意後見制度が選ばれることもあります。 ご自分やご家族にとって一番適切な制度がどれなのか、弁護士などに相談するのも一つの方法です。 任意後見人の報酬額は、任意後見契約で自由に定めることができ、親族などが後見人を務める場合には、無償とすることも可能です。 一般に親族などが任意後見となった場合の報酬相場は月額3万円を超えないことが多いようです。 弁護士など専門家に任意後見人を依頼した場合の報酬相場は、月額3~6万円程度でしょう。 ちなみに報酬は、任意後見契約の効力が生じたときから発生します。 これに対して任意後見監督人の報酬は、任意後見監督人が報酬付与の申立てを行い、裁判所が本人の財産から相当な報酬を監督人に付与する審判を行うことになります。 管理財産額が5,000万円以下の場合は、月額1万円~2万円程度、管理財産額が5,000万円を超える場合には、月額2万5,000円~3万円程度のこと決定されることが多いとされています。 【出典】成年後見人等の報酬額について|裁判所
法定後見制度や家族信託があるのに任意後見制度は必要か?
任意後見人や任意後見監督人への報酬の相場は?
任意後見人の報酬相場
任意後見監督人の報酬相場
8.まとめ
超高齢社会が進むにつれて任意後見制度の利用も増えてくることが予想されます。
任意後見制度を利用するためには、判断能力が十分なうちに行わなければなりませんので、制度の利用を検討し始めたのであればすぐに行動することをおすすめします。
任意後見制度の利用にあたって分からないことや不安なことがあれば、弁護士にご相談ください。