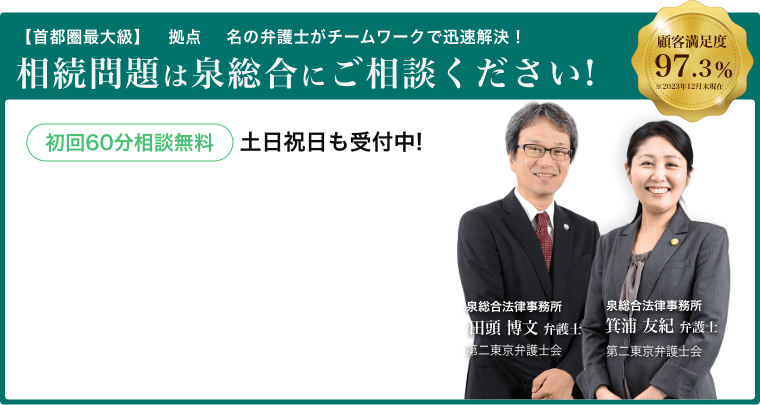家族信託と遺留分|信託契約を無効とした判決を踏まえて解説

家族信託は、その活用可能性の広さから、有力な相続対策として注目されています。
家族信託を遺留分対策としても活用しようとする動きも見られますが、その際には、遺留分潜脱を理由に家族信託の一部を無効とした、近時の東京地裁判決を踏まえた対応が必要です。
この記事では、東京地裁平成30年9月12日判決の内容を踏まえて、家族信託と遺留分の関係について解説します。
1.家族信託を使えば遺留分問題を回避できる?
家族信託を使えば、遺留分問題を回避できるという考え方もありますが、実際のところはどうなのでしょうか。
民法や裁判例の規範に沿って、法律上の取り扱いを検討してみましょう。
(1) 遺留分侵害額請求の対象は「遺贈」と「贈与」
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続できる財産の最低保証額です(民法1042条1項)。
 [参考記事]
遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説
[参考記事]
遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説
遺留分権利者が仮に遺留分未満の財産しか承継できなかった場合、「遺贈」か「贈与」のいずれかによって多く財産を承継した者に対して、不足分を金銭で支払うよう請求できます(民法1046条1項)。
なお、遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与は、以下のとおりです(民法1043条1項、1045条1項、3項)。
遺贈:すべて
贈与:死因贈与および相続開始前10年間に行われたもの(相続人でない場合は1年間)
(2) 信託譲渡は遺留分侵害額請求の対象外
家族信託を設定する場合、委託者から受託者に対して、財産が「信託譲渡」されます。
「信託譲渡」とは、受託者に財産を管理させる目的で、委託者から受託者に財産の所有権を移すことをいいます。
信託譲渡は「遺贈」でも「贈与」でもありませんので、信託譲渡自体が遺留分侵害額請求の対象となることはありません。
(3) 信託受益権は遺留分侵害額請求の対象になり得る
その一方で、家族信託を設定した場合、受益者が「信託受益権」を取得します。
「信託受益権」とは、信託財産から生じる収益の分配を受ける権利です。
したがって、信託受益権には財産上の価値があります。
受益者の信託受益権は、委託者の負担によって財産が信託譲渡されたことによって発生するものです。
つまり、受益者に対する信託受益権の付与は、実質的には委託者から受益者への贈与に相当すると考えられます。
したがって、家族信託によって発生する信託受益権は、委託者の相続人による遺留分侵害額請求の対象になると解されています。
後述する東京地裁平成30年9月12日判決でも、旧民法における遺留分減殺請求の事案について、家族信託の信託受益権が遺留分減殺請求の対象になり得ると判示しています。
上記を考慮すると、家族信託を活用したとしても、遺留分問題を完全に回避することはできないといえるでしょう。
2.遺留分潜脱を理由に家族信託の一部が無効とされた裁判例
遺留分問題を回避するためだけに家族信託を利用すると、家族信託が無効とされるおそれがあります。
実際に、東京地裁平成30年9月12日判決では、遺留分問題の潜脱を理由として、家族信託の一部が無効とされました。
(1) 遺留分問題を回避するために家族信託が利用された事案
東京地裁平成30年判決の事案では、不動産と金300万円が、委託者の次男に対して信託譲渡されました。
委託者は、次男を正当な後継者として家・墓・仏壇などを保守してほしいという意向の下、次男に対して不動産を譲り渡したいと考えていたようです。
しかし、遺贈や贈与によって不動産を次男に譲渡すると、遺留分侵害の問題が発生します。
そこで、遺留分問題を回避するため、家族信託の仕組みが利用されたのです。
(2) 収益を予定していない不動産の信託譲渡が無効とされた
本事案では、家族信託が遺留分の潜脱を目的として設定されたため、公序良俗(民法90条)に反し無効であるという主張が原告によりなされました。
これに対して東京地裁は、次男に対して信託譲渡された不動産の一部につき、遺留分の潜脱を目的としていることを認定したうえで、公序良俗違反により無効としました。
遺留分の潜脱による公序良俗違反が認定されたのは、収益を上げることが現実的に不可能であるなどの理由で、不動産の収益を受益者に対して分配することが想定されていないと判断された不動産の信託譲渡です。
前述のとおり、本事案において東京地裁は、信託譲渡が行われた場合の遺留分減殺請求の対象を、信託譲渡された財産自体ではなく、信託受益権であるという考え方をとっています。
この考え方を前提にすると、遺留分権利者は、遺留分減殺請求を行うことにより信託受益権を取得できる一方で、不動産自体を取得することはできなくなります(現物精算、後述)。
しかし、遺留分権利者が信託受益権を取得しても、もともと収益の分配が想定されないのであれば、遺留分権利者は何らの経済的利益も得ることができません。
このような点を実質的に考慮したうえで、東京地裁は、収益が予定されていない不動産の信託譲渡について遺留分の潜脱目的を認定し、公序良俗違反として無効と判示したのです。
3.東京地裁平成30年判決と相続法改正の関係
東京地裁平成30年判決における判示が、現行民法の下でもそのまま適用できるかどうかは、2019年7月1日に施行された改正相続法におけるルール変更も踏まえて検討する必要があります。
(1) 東京地裁平成30年判決|遺留分減殺請求=現物精算
東京地裁平成30年判決の事案は、改正相続法施行前のものなので、旧法下の制度である「遺留分減殺請求」のルールが前提となっています。
遺留分減殺請求の場合、遺留分を侵害している遺贈や贈与については、遺留分侵害者から遺留分権利者に対して現物を引き渡すことで精算されます。
たとえば、東京地裁平成30年判決の事案では、信託譲渡が行われなかったとすれば、不動産が遺留分減殺請求の対象となるはずでした。
この場合、遺留分減殺請求が行われると、不動産自体が遺留分減殺の対象となり、遺留分侵害者と遺留分権利者の間で共有となることが想定されます。
(2) 現行法|遺留分侵害額請求=金銭精算
これに対して、2019年7月1日に改正相続法が施行されて以降は、遺留分減殺請求に代わり、新たに「遺留分侵害額請求」の制度が設けられました。
遺留分侵害額請求の場合、遺留分を侵害している遺贈や贈与については、現物ではなく金銭による精算が行われます。
たとえば、不動産の遺贈・贈与について遺留分侵害が問題になったとします。
この場合、遺留分侵害額請求が行われても、不動産の現物による精算は行われず、あくまでも侵害額相当の金銭を交付することによって精算が行われるのです。
(3) 現行法下における東京地裁平成30年判決の射程
東京地裁平成30年判決では、家族信託を利用した遺留分の潜脱が問題となりましたが、これは「不動産についての遺留分減殺を避ける」ことを目的とするものでした。
つまり、遺留分減殺請求が現物精算によることを前提として、不動産自体の返還や共有化を避けることが意図されていたのです。
これに対して、現行法の遺留分侵害額請求では、現物精算は行われず、金銭による精算が行われるにとどまります。
よって、仮に東京地裁平成30年判決の事案において、現行法下の遺留分侵害額請求が行われた場合には、そもそも不動産自体の返還や共有化が問題となることはないのです。
したがって、現行法下の事案においては、東京地裁平成30年判決と同様の論理により、遺留分の潜脱を理由として家族信託が無効とされる可能性は下がるように思われます。
ただし、同判決が別途判示しているように、家族信託の信託受益権が遺留分侵害の対象となる点については、現行法下でも適用し得る論理であると考えられます。
そのため、遺留分侵害額請求の対象期間中に、家族信託による信託譲渡が行われた場合には、遺留分侵害額請求による金銭精算が生じ得ると言うべきでしょう。
その場合、信託受益権の価値を算定して、遺留分侵害額を求めることになると考えられます。
4.まとめ
家族信託を活用したとしても、信託受益権が発生する点が、委託者から受益者に対する贈与と捉えられ、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
また、旧民法下の遺留分減殺請求に関しては、遺留分の潜脱を理由として家族信託の一部が無効とされる裁判例も現れました。
この裁判例の論理を、現行民法下の事案にそのまま適用できるかどうかについては疑問が残ります。
しかし、この点について確立した取り扱いがあるわけではないため、家族信託を遺留分対策として活用することには慎重を期す方がよいでしょう。
家族信託に限らず、法的に実践可能な遺留分対策には、さまざまなパターンが考えられます。
もし特定の親族に対して多めに財産を残したいと考える場合には、状況に応じた適切な遺留分対策を講じるために、相続に精通した泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。