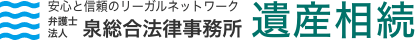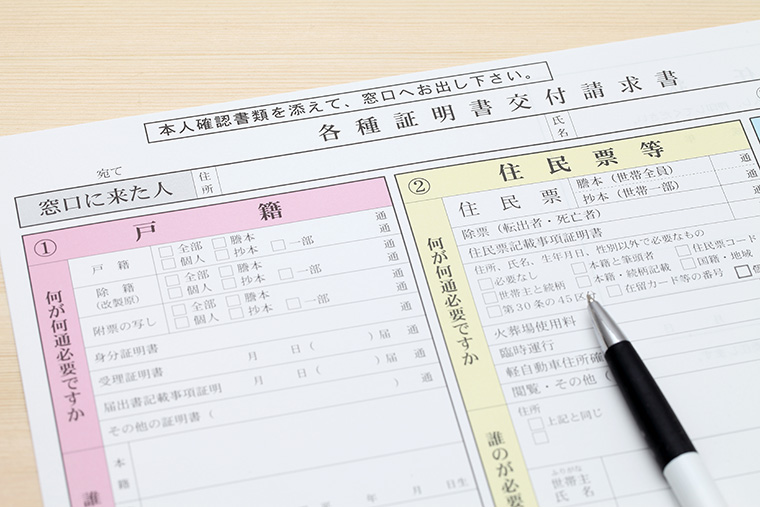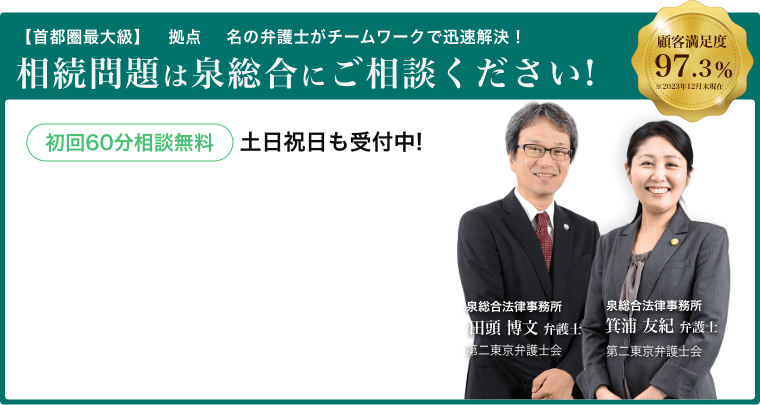特別縁故者の申立|誰がなれる?相続財産分与の条件・裁判例

被相続人と生前特別に縁が深かった方は、相続権を持たなくても「特別縁故者」として最終的に相続財産の分与を受けられる可能性があります。
しかし、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、厳しい要件をクリアしたうえで、複数段階にわたる複雑な手続きを経ることが必要です。
もしご自身が特別縁故者に当たるのではないかと思い至った場合には、実際に相続財産の分与を受けられるかどうかを検討するため、一度弁護士にご相談ください。
この記事では、特別縁故者として相続財産の分与を受けるための要件・裁判例・申立て方法などを中心に解説します。
1.特別縁故者とは?
特別縁故者とは、被相続人に相続人がいない場合、被相続人と縁が深い人物(特別の縁故のあった者)として、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる人を意味します。
相続人がいない場合、相続財産は債権債務関係の清算後、最終的に国庫へ帰属します(民法959条)。
しかし、被相続人と親密に交流していた人や、生前の被相続人に対して多大な貢献をした人がいる場合には、その人に遺産を分け与えることが被相続人の意思に沿う可能性が高いと考えられます。
そこで、相続人がいないケースに限って、相続財産を国庫に帰属させる前に、特別縁故者が相続財産の分与を受ける道が開かれているのです。
なお、特別縁故者が相続財産の分与を受けられるとしても、遺産を全部もらえるとは限らず、家庭裁判所の決定によって分与される遺産額が決定されます。
2.特別縁故者に当たるための要件
特別縁故者として相続財産の分与を受けるには、生前の被相続人と「特別の縁故」があったことが必要です(民法958条の2第1項)。
「特別の縁故者」として、民法958条の2第1項は以下の2つのパターンを挙げています。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
さらに民法958条の2第1項には、「その他被相続人と特別の縁故があった者」との記載もあるため、以下のような者も特別縁故者として認められる可能性があります。
- 被相続人から信頼され、相談に応じていた者
- 被相続人の身元引受人や任意後見人となっていた者
- 被相続人に対して仕送りなど多額の金銭的援助を行った者 など
結局のところ、特別縁故者として相続財産の分与を受けられるかどうかは、「どれだけ被相続人と親しかったか」「その人の義務範囲を超えて、被相続人に対して貢献したといえるか」という観点から、個別具体的に判断されます。
3.特別縁故者についての裁判例
特別縁故者に対する相続財産の分与が認められるかどうか、またどのくらいの金額の分与が認められるかについては、家庭裁判所(即時抗告が行われた場合には高等裁判所)による審査の結果次第となります。
そこで、特別縁故者として相続財産分与を認められた裁判例と、認められなかった裁判例をご紹介します。
(2) 特別縁故者に相続財産分与が認められた裁判例
東京高裁平成26年5月21日決定
被相続人のいとこAが、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
Aは、生前の被相続人の自宅を修理したり、定期的に安否確認を行ったりしていました。
また、被相続人が亡くなった際の遺体発見に立会い、さらに遺体の引き取りや葬儀も行いました。
東京高裁は、上記のAの被相続人に対する貢献を踏まえて「特別の縁故」を認めました。
しかし、その縁故の程度が濃密なものではなかったとして、遺産総額3億7000万円超に対して、300万円の限度でのみ相続財産の分与を認めました。
名古屋高裁金沢支部平成28年11月28日決定
被相続人が入所していた介護施設を運営する社会福祉法人が、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
介護施設は被相続人と入居契約を締結しており、被相続人の療養看護を行う義務を負っています。
しかし本件では、介護施設が行ったサービスは、通常期待されるサービスの程度を超えて近親者の行う世話に匹敵すべきものであったと認定されました。
そのことを踏まえて「特別の縁故」が認められ、社会福祉法人に対して相続財産の全部が分与されました。
(3) 特別縁故者に相続財産分与が認められなかった裁判例
次に、特別縁故者に対する相続財産の分与が認められなかった裁判例を2つ紹介します。
東京高裁平成25年4月8日決定
被相続人の内縁の妻Bが、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
Bは、生前の被相続人と同居し、生計を同じくしていました。
しかしBは、被相続人の遺言書を偽造し、自ら相続財産を不法に奪取しようと企てたことが、確定判決において認定されていました。
東京高裁は、上記のような行為をしたBに相続財産を分与することは相当でないとして、Bの申立てを認めませんでした。
 [参考記事]
内縁の妻・夫がパートナーの財産を受け継ぐ方法
[参考記事]
内縁の妻・夫がパートナーの財産を受け継ぐ方法
東京高裁平成27年2月27日決定
被相続人のいとこ5名が、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
原審判では、いとこ5名に対して合計9500万円の相続財産の分与が認められました。
しかし東京高裁は、親族としての情誼に基づく交流を超えるような親密な付き合いがあったとは認められないとして、原審判を破棄・差し戻しました。
4.特別縁故者が相続財産分与を申し立てるまでの流れ
特別縁故者が相続財産の分与を申し立てるまでには、多くの法律上の手続きを経る必要があります。
以下では、特別縁故者が相続財産の分与を申し立てられるようになるまでの流れと、実際の申立て手続きについて解説します。
(1) 相続財産清算人の選任を請求する
相続人があることが明らかでないとき(相続人がいないとき)には、相続財産清算人による遺産の処理を経る必要があるとされています(民法952条1項)。
そのため、特別縁故者が相続財産の分与を申し立てる前に、まずは相続財産清算人の選任を申し立てることが必要です。
特別縁故者に該当すると主張する人は、「利害関係人」として相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
 [参考記事]
相続財産清算人とは?選任申立ての流れや費用、誰がなるのかを解説
[参考記事]
相続財産清算人とは?選任申立ての流れや費用、誰がなるのかを解説
(2) 特別縁故者の申立てまでに経なければならない公告
特別縁故者の申立てまでには、以下の公告手続きが行わなければなりません。
①相続財産清算人選任と相続人の捜索の公告
家庭裁判所は相続財産清算人が選任された旨と、相続人がいるのであれば一定期間内にその権利を主張すべき旨を公告します(民法952条2項)。
この公告が行われてから6か月の間、名乗り出る相続人がいないかを待つことになります。
②相続債権者・受遺者に対する弁済請求申出の公告
選任された相続財産清算人は、すべての相続債権者・受遺者に対して、一定期間内に弁済の請求をするよう申し出るべき旨の公告を行わなければなりません(民法957条1項1文)。
弁済請求申出の公告期間は、相続人の検索の公告の期間内でかつ最低2か月間とされています(同項2文)。
(3) 家庭裁判所に対して相続財産分与の申立てを行う
相続人の捜索の公告期間に相続人が誰も現れず相続人の不存在が確定し、相続債権者・受遺者への弁済が行われた後に、特別縁故者は家庭裁判所に対して、相続財産分与の申立てを行うことができるようになります(民法958条の2第1項)。
特別縁故者の相続財産分与の申立て期間・裁判所の管轄
特別縁故者が、相続財産分与の申立てをできる期間は、相続人の捜索の公告期間の満了後3か月以内です(同条2項)。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります(家事事件手続法203条3号、民法883条)。
具体的な管轄については、以下のサイトから検索することができます。
裁判所の管轄区域|裁判所
特別縁故者の相続財産分与の申立てに必要な書類・費用
特別縁故者の相続財産分与の申立ての必要書類
- 家事審判申立書
- 申立人の住民票または戸籍附票(標準的な申立添付書類)
特別縁故者の相続財産分与の申立ての費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てを行う裁判所によって異なる)
【出典】特別縁故者に対する相続財産分与|裁判所
申立書の書式や記載例は、上記サイトからダウンロード可能です。
申立人が特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、申立人と被相続人の関係性が深かったことについて、信頼性のある資料の根拠に基づいて立証することが大切であり、申立時に被相続人との特別縁故について詳述した陳述書を添付することも可能です。
また、被相続人と特別縁故の関係にあったことを証明できる証拠をできるだけ多く集めておくことも重要になります。申立てをお考えの方は、弁護士に相談するといいでしょう。
5.特別縁故者の審判
申立期間内に管轄裁判所に特別縁故者の申立てがあると、家庭裁判所は提出された書類以外に、家庭裁判所調査官による調査を行って、特別縁故者にあたるかどうか、相続財産分与の相当性があるかどうかを確認します。
また家庭裁判所は、相続財産清算人に意見書を提出させて意見を聴取しなければなりません(家事手続法205条)。
審理の結果、家庭裁判所が特別縁故者にあたり、相続財産の分与に相当性があると認めれば、相続財産分与の審判を下し、特別縁故者にあたらない、または相続財産分与の相当性がないと認めれば、申立てを却下する審判を下します。
6.特別縁故者についてのよくある質問(FAQ)
特別縁故者として相続財産の分与を受けた場合には、その財産が相続税の課税対象となります。 相続税の申告・納付期限は、審判確定の日の翌日から10ヶ月以内となります。 また、相続税の基礎控除額は3,000万円となるため、分与を受けた財産額がこれ以下であれば、相続税がかからないことになります。 ただし、特別縁故者は「2割加算」の対象となるため、相続税額が法定相続人の2割増しとなります。 相続放棄をしても、特別縁故者として相続財産分与の申立てをすることは可能です。 しかし、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、ここまでご説明した要件に合致する必要があります。相続放棄後に特別縁故者として相続財産分与の申立てをお考えの方は、弁護士に相談することをお勧めします。
特別縁故者にも相続税がかかるの?
相続放棄をしても特別縁故者として相続財産分与を受けることはできる?
7.まとめ
特別縁故者は、相続人がおらず、かつ生前の被相続人と非常に深い関係にあると認められた場合に限って、相続財産の分与を受けることができます。
特別縁故者が相続財産の分与を申し立てるまでには、相続財産管理人を選任したうえで3つの公告手続きを経る必要があり、かなりの時間と手間がかかってしまいます。
そのため、被相続人となる方が自己の特別縁故者と認める方に対して遺産を譲りたい場合には、弁護士にご相談のうえで生前対策(贈与)を実施することをお勧めいたします。
弁護士にご相談いただければ、依頼者様のご状況やご希望に合わせて、生前対策案をご提案いたします。
また、特別縁故者として相続財産の分与を受けたい方には、法律上必要な手続きを踏まえて、できる限り多くの分与を受けられるようにサポートいたします。
特別縁故者への相続財産分与に関するご相談は、泉総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。