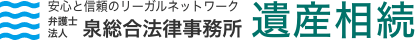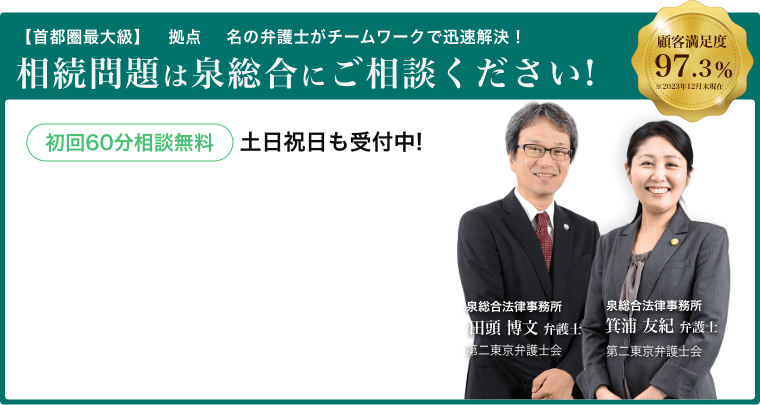遺産の使い込みが発覚!取り戻すにはどうすればいい?

相続が発生し、遺産分割協議を始めるべく遺産の内容を調べていたら、共同相続人のひとりが遺産を使い込んでいた事実が発覚することがあります。
弁護士が受任する遺産相続事件では、遺産の使い込みは珍しいことではなく、むしろ相続トラブルの典型例です(税務署の調査で発覚することもあります)。
この記事では、遺産の使い込みが発覚した場合の法的対処について説明します。
1.遺産使い込みの設例|使い込みは相続発生前?後?
遺産の使い込みは、生前に行われたか死後に行われたかによって考え方が異なります。そこで、わかりやすいように次の設例を使って解説していきます。
被相続人:母A
相続人:長男B、次男C、長女D
遺産:X銀行の普通預金100万円 Y銀行の定期預金2千万円
母Aの死亡後、各銀行の通帳は同居していた長男Bが管理しており、長女Dが通帳を見せてほしいと要求しても長男Bは応じません。
そこで、長女Dは戸籍謄本等、自分が母Aの法定相続人であることを証明できる書類を集めたうえで、各銀行に対して口座の元帳のコピーを請求し、その交付を受けました。
ケース①生前の使い込み
母Aが死亡する5年前から、普通預金口座から毎月引き出しがあり、1,000万円あった普通預金が、母A死亡時には100万円しか残っていないことが判明したというケースケース②死後の使い込み
普通預金口座は、母A死亡時点で1000万円の預金があったが、母A死亡の翌日に900万円が引き出され、現時点では100万円しか残っていないことが判明したというケース
どちらの設例も定期預金2千万円は無事であったとします。
以下では、①生前(相続発生前)の使い込みと、②死後(相続発生後)の使い込みに分けてご説明します。
2.ケース① 生前(相続発生前)の使い込み
相続発生前の預金は母Aの財産であり、その使い途を決めることができるのは母Aだけです。そのため、死亡した母Aの預金を下ろした使途が母Aの意思に基づくものか否かによって罪に当たるか否かの扱いが異なります。
(1) 被相続人の意思に反する場合
横領罪と母Aの請求権
母Aの介護をしていた長男Bが通帳やキャッシュカードを管理し、勝手に預金を下ろして消費していた場合、法的には、自己が法律的に占有する他人の財産をほしいままに処分したものとして、横領罪(刑法252条)に該当しうることになります。
もっとも、母Aと長男Bは直系血族であり、刑の免除が認められているので(刑法255条、244条)、実際には刑事問題に発展することは少ないでしょう。
しかし、民事上の手続により、長男Bが使い込んだお金を取り戻すことは可能です。
生前の母Aは、長男Bの違法行為によって損害を被ったので、長男Bに対して、不法行為(民法709条)に基づく900万円の損害賠償請求権を有していたことになります。
また、長男Bの900万円の利得は違法行為によるものであり、不当利得(民法703条)に該当し、生前の母Aは、長男Bに対して900万円の不当利得返還請求権も有していたことになります。
生前の母Aは、不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得に基づく返還請求の両方、またはどちらか一方を理由として900万円の支払いを長男Bに請求できたわけです(ただし、二重取りはできません)。
請求権は相続される
生前の母Aが長男Bに対して有していたこの損害賠償請求権と不当利得返還請求権は、遺産として相続の対象となります。
したがって、母Aの長男Bに対する900万円の請求権は、長男B、次男C、長女Dが法定相続分である3分の1ずつ、つまり各300万円ずつ相続したことになります。
判例によれば、これらの請求権は一般の可分債権(分割できる債権のこと)であり、法定相続分に応じて当然に分割される扱いなので、遺産分割の対象とはなりません(最高裁昭和29年4月8日判決)。
ただし、このような当然に分割されるはずの債権であっても、共同相続人の「全員」が遺産分割手続で配分を決めたいと希望するのであれば、これをあえて拒む理由もありません。
そこで実務では、共同相続人の「全員」の合意があれば、遺産分割の対象として手続を進めています。
設例の場合、長男B、次男C、長女Dの3名全員が合意すれば、900万円は長男Bが「預かっている」母Aの遺産として分割協議の対象と扱われるのです(※)。
※東京家庭裁判所家事第5部編著『東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割部)における相続法改正を踏まえた新たな実務運用』(日本加除出版株式会社)20頁
逆に、この900万円の問題を遺産分割で解決することに、長男B、次男C、長女Dの3名のうち一人でも合意しない者がいれば、遺産分割の対象にはできません。
遺産分割の対象とならない場合には、次男Cの長男Bに対する300万円の請求権、長女Dの長男Bに対する300万円の請求権は、長男Bが任意に支払わない限り、訴訟で解決することになります。
なお、遺産分割の対象としない場合には、長男Bが相続した300万円については、債権債務が同一人に帰したので、混同により消滅します(民法520条)。
(2) 被相続人の意思である場合
母Aの生前に、長男Bが預金を下ろして、長男B自身のために消費していても、それを母Aが許していた場合は、母Aから長男Bへ、900万円の生前贈与が行われていただけです。
したがって、残りの普通預金100万円と、定期預金2千万円が遺産分割の対象となり、(最高裁平成28年12月19日決定)、その遺産分割の中で、900万円の生前贈与が特別受益(民法903条)に該当するかどうかを問題とすることになります。
 [参考記事]
特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説
[参考記事]
特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説
仮に、この900万円が、長男Bの特別受益と認められた場合には、相続財産に持ち戻しされる(相続財産に含まれる)ことになり、遺産(みなし相続財産)は、普通預金100万円+定期預金2千万円+900万円=合計3千万円となり、各人の具体的相続分は次のとおりとなります。
- 長男B 3千万円×3分の1-900万円=100万円
- 次男C 3千万円×3分の1=1000万円
- 長女D 3千万円×3分の1=1000万円
(3) 被相続人の意思ではないが被相続人のために使われていた場合
母Aが高齢の場合は、長男Bが母Aの預金を下ろして、母Aの生活費、公租公課、医療費、介護費など、本人のために使ったと主張することもよくあります。
実際に被相続人のために消費されたのであれば、被相続人には損害・損失はないので、不法行為も不当利得も成立せず、横領罪にも該当しません。900万円という遺産は、相続発生時には既に「存在しなかった」だけのことです。
そのため、その主張を裏付ける領収書やレシートなどがあり、次男Cと長女Dが納得するなら(立証責任はBにあります)、残りの遺産について通常通り遺産分割の手続を進めることになります。
他方、裏付け証拠がなく、使途不明金として次男Cと長女Dが納得しなければ、長男Bに対して損害賠償請求または不当利得返還請求を求めて、訴訟で解決することになります。
以上が、母Aが生きている間に、長男Bが使い込んだ場合の法的処理です。
3.ケース② 相続発生後の使い込み
次に、母Aが亡くなった後に、長男Bが使い込んだ場合について見ていきましょう。
(1) 相続発生後の使い込みも横領
相続発生の事実が金融機関に伝われば直ちに口座は凍結され出入金はできなくなります。しかし実際には、遺族が伝えなければ預金を下ろすことが可能なので、相続発生後の使い込みが生じてしまいます。
相続が発生した時点で預金(厳密には銀行に対する預金債権)は遺産となっており、遺産分割されるまでは共同相続人の共有財産ですから(民法898条)、自己の法定相続分にあたる共有持分を超えた金額を処分するには、他の共同相続人の同意を要します(民法264条、206条)。
したがって、口座を管理する者がほしいままに預金をおろすことは、やはり横領行為といえます。次男Cと長女Dは、長男Bに対して不法行為・不当利得を理由に各自300万円ずつの請求権を持つことになります。
ただし、長男Bが下ろした預金が、故人の残した借金の返済、遺産である不動産の固定資産税、地代や家賃などに充てられた場合には、それが事実である限り、相続財産から支出するべき費用と認められ、その部分は不法行為や不当利得にはあたりません(民法885条1項)。
(2) 使い込み金を遺産分割の対象とできる場合
普通預金のうち使い込まれた900万円は遺産分割時点では存在しなくなっているので、遺産分割の対象とはならないことが原則です。
ただ、この場合も、従前の実務では、900万円を遺産分割の対象とすることに共同相続人の「全員」が同意していれば、遺産分割で、900万円を含めて分割する扱いとしていました。
ところが、この従前の扱いでは「全員」の同意が必要なので、900万円を下ろした長男Bが反対すれば、900万円を遺産分割の対象とはできません。
このため遺産分割は、残った遺産(普通預金100万円+定期預金2千万円)のみを対象とすることになり、具体的な相続分は次のとおりとなります。
- 長男B 2100万円×3分の1=700万円
- 次男C 2100万円×3分の1=700万円
- 長女D 2100万円×3分の1=700万円
もちろん、次男Cと長女Dは、それぞれ長男Bに対して、不法行為及び不当利得を理由として、各300万円ずつ請求する権利を有しています。しかしそのためには、わざわざ別途の訴訟を起こして解決しなくてはならず、遺産分割手続としては、長男Bにも同じだけの遺産を分割しなくてはならなかったのです。
それでは、次男Cと長女Dが時間と費用をかけて訴訟に踏み切らない限り、横領した長男Bが得をしてしまうことになり、あまりに不公平です。
そこで、2020(令和2)年4月1日施行の改正民法第906条の2は、次の例外を定めています。2項に注目してください。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2
1項 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2項 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
1項は、先ほどご説明したこれまでの取り扱いを述べているだけですが、2項では、遺産を処分した者の同意はいらないとしています。
遺産を勝手に処分されてしまい、遺産分割の時に存在せず、本来は遺産分割の対象とできない財産であっても、処分した当の本人以外の共同相続人が、その財産を遺産分割の対象とすることに同意すれば、遺産分割の対象とできるのです。
相続発生後の使い込みであるケース②では、次男Cと長女Dが同意すれば、長男Bが反対しても、遺産分割の俎上にのせることができるわけです。
この場合は、長男Bは遺産900万円を預かっていることになり、それを遺産に含めて遺産分割を進めることになります。
この民法の規定の創設は,これまでの実務や公平の観点を盛り込んだ非常に画期的なものと言えるでしょう。
(3) 他の共同相続人の同意がない場合
次男Cと長女Dが遺産分割での解決に同意しない場合(次男Cと長女Dの片方が同意しない場合も含む)は、原則にもどって、900万円は遺産分割の対象外であり、やはり損害賠償請求権・不当利得返還請求権の問題として訴訟で解決することになります。
4.不法行為と不当利得の消滅時効期間
使い込みの問題を訴訟で解決する場合には、以下の2つが想定され、どちらで請求するべきか気になる方もいらっしゃるでしょう。
- 不法行為に基づく損害賠償請求
- 不当利得に基づく返還請求
不法行為と不当利得は、消滅時効期間(民法724条、166条1項及び2項)や、不法行為に基づく損害賠償義務を受働債権とした相殺の禁止(民法509条)などの相違はありますが、実際は、両方を原因として支払いを請求することができることから、比較する意味はあまりありません。
ただし、どちらも消滅時効にかかることは確かですので、それぞれの時効起算点と時効期間は知っておいてください。
(1) 不当利得返還請求権の消滅時効
| 使い込み時期(※) | 起算点 | 時効期間 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日以前 | 使い込み時点 | 10年 | 改正前166条1項 改正前167条1項 |
| 2020年4月1日以後 | 使い込みを知った時点 | 5年 | 改正後166条1項1号 |
| 使い込み時点 | 10年 | 改正後166条1項2号 |
※改正民法の施行期日(2020年4月1日)よりも前に発生していた債権については、改正前の消滅時効期間が適用されます(平成29年6月2日法律第44号附則10条)。
(2) 不法行為に基づく損害賠償請求権
| 起算点 | 時効期間 | 条文 |
|---|---|---|
| 長男Bによる使い込みを知った時点 | 3年 | 改正後724条1号 |
| 使い込み時点 | 20年(※) | 改正後724条2号 |
※改正前の20年は消滅時効期間ではなく、除斥期間と理解されていたので、消滅時効のように途中で中断してリスタートするなどの扱いはありませんでした。
(3) まとめ
両者を比較すると、不法行為の時効期間のほうが長いことから、こちらを使うと良い気もします。しかし、使い込みが行われたのが相当前のことであれば、この時効期間が徒過してしまっている可能性もあります。
むしろ、使い込みを知る時点は、相続が発生し、調査をした後のことが多いので、その時効期間を強く意識して5年(不当利得)なり3年(不法行為)なりの消滅時効にかからないように注意することが大切であると考えられます。
5.遺産の使い込みについてのよくある質問(FAQ)
-
遺産の使い込みの調査方法は?
裁判で遺産の使い込みを争う際には、請求する側に立証責任があり、証拠が重要な役割を果たします。そこで、証拠収集のための調査が必要になります。
被相続人の預貯金が使い込まれた場合には、口座のある金融機関に対して、取引履歴の開示を請求し、使い込みの疑いのある相続人の口座への振り込みなど不審な出金記録を見つけ出して、使途不明金の総額を積み上げます。
しかし、こうした作業には、膨大な手間と時間がかかります。もっとも、遺産の使い込みは、調査段階から弁護士に依頼することができます。
-
遺産の使い込みを弁護士に依頼するメリットは?
弁護士であれば、「弁護士会照会制度」を利用することで、効率的に各金融機関から取引履歴を取り寄せて、内容の分析まで任せることが可能です。
遺産の使い込みでは、被相続人の病院のカルテや看護記録なども収集しなければならないこともあります。このような場合にも、弁護士に依頼すると、必要な証拠を自から判断し、収集することができます。
また、相手方との交渉を任せることができ、いざ訴訟となった際にも代理人として対応し、依頼人が最大限有利になるよう進めてくれるでしょう。さらに、その後の遺産分割についても、任せることができます。
このように、弁護士のサポートがあれば、遺産の使い込みの調査から、遺産分割手続きまで任せることができるのです。
6.遺産の使い込みが発覚したら弁護士へ
遺産の使い込みが発覚した場合や、その疑いがある場合、共同相続人間の話合いで解決できれば幸いですが、相続問題はこじれやすいものです。
泉総合法律事務所にご相談いただければ、遺産の使い込みに関する問題を含めて、遺産分割全体を迅速・円満に解決するためのサポートをご提供いたします。
遺産分割についてトラブルをお抱えの方は、ぜひお早めに泉総合法律事務所にご相談ください。