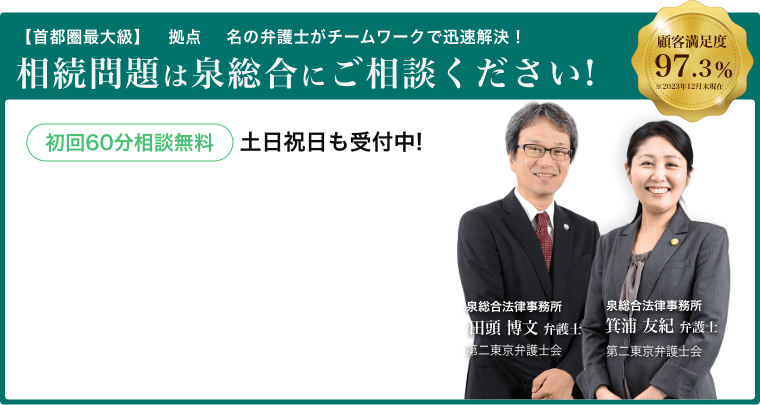相続放棄の期間(熟慮期間)は原則3ヶ月以内|起算点はいつから?

様々な事情で相続放棄を検討される方は少なくありませんが、相続放棄は、いつでもできるわけではありません。相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期間制限がある点に注意が必要です。
この記事では、熟慮期間がいつからいつまでなのか、熟慮期間内に相続放棄できない場合や、熟慮期間の期限が切れてしまったときの対処法などを解説します。
1.相続放棄とは
相続放棄は、読んで字のごとく、相続人が自分の相続権を放棄することです。
相続放棄を選択した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます(民法939条)。
相続では、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継するため、通常の相続(単純承認)をしてしまうと借金まで背負わされてしまうことになります。
しかし、被相続人と相続人は別の人間なのにも拘らず、配偶者であったり、血縁関係にあるというだけで有無をいわさず借金等まで押し付けられてしまうのは酷な話です。
そこで民法は相続放棄という制度を設けることで、相続人に対して相続をするか否かの選択機会を与えているのです。
2.熟慮期間は「3ヶ月」
(1) 熟慮期間の起算点
相続放棄の手続きには「熟慮期間」と呼ばれる期限があり、熟慮期間を過ぎた相続放棄は原則として認められません(一部例外はありますので後述します)。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です(民法915条1項)。この3ヶ月以内に、相続放棄申述書を提出し、相続放棄の申立てをする必要があります。
一般的には、「被相続人が死亡したこと」「自分が相続人であること」の両方を知った日をもって「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。
例えば、亡くなったことは知っていたが、先順位の相続人が全員相続放棄したことで自分に相続権が回ってきた、ということもあり得ます。したがって、この場合は、「自分のところに相続権がまわってきたことを知った時」から3ヶ月となります。
この3ヶ月の熟慮期間を何もしないまま経過すると、その相続人は単純承認したものとみなされます(法定単純承認921条2号)。
相続放棄の起算日と3ヶ月の数え方
では、この起算点をもう少し詳しく考えてみましょう。
民法では、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入せず(民法140条)、期間は、その末日をもって満了するとされています(同法141条)。ただし、期間が午前零時から始まるときは、期間の初日に算入します(同法140条但書)。
また、期間の末日が日曜日、祝日の場合は、その翌日に満了となります(同法142条)。
ただし、相続放棄の申述期間の場合、休日に土曜日、12月29日から12月31日日又は1月2日から1月3日が含まれます(家事事件手続法34条による民事訴訟法95条3項の準用)。
例えば、3月1日に被相続人が亡くなったことを法定相続人が知ったとします。この場合は、初日を算入しないため、3月2日(午前0時)が起算日となり、6月1日の24時(4月2日の午前0時)の時点で熟慮期間が終了することになります(民法143条2項)。
また、6月1日が日曜日の場合に、翌日が平日であれば6月2日が、6月2日が祝日であれば、6月3日が満了日となります。
(2) 熟慮期間が迫っていても決断できない場合
万が一、熟慮期間終了が目前なのに決断しかねているという場合には、熟慮期間が経過する前に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長(延長)の申立てを行うことができます。
伸長の申立てが受理されるかどうかはケースバイケースですが、被相続人の遺産が複雑で調査に時間がかかる等、期間の延長に値するやむを得ない事情があれば認められる可能性が高くなります。
熟慮期間の伸長が基本的に柔軟に認められているのに対し、伸長が間に合わなかったなどで熟慮期間の経過後にする相続放棄は一気にハードルが高くなります。少しでも熟慮期間を経過しそうだと思ったら、伸長の申立ての手続きに入ったほうがよいでしょう。
なお、相続放棄の申述から受理までにかかる期間は、およそ1ヶ月程度をみておいてください。
【新型コロナウイルスの影響による伸長】
特に2021年9月現在では、新型コロナウイルスの影響により熟慮期間内に相続放棄を決断できないケースもあるでしょう。
もともと裁判所は熟慮期間の伸長を緩やかに認めてきましたので、新型コロナによる遺産内容の調査未了を理由にした熟慮期間の伸長も問題なく認めてもらえます。新型コロナが原因で遺産内容の調査が滞っている場合には、それほど無理をする必要はないと思われます。
申立書には「〇〇年〇〇月〇〇日まで伸長するとの審判を求めます」と自分で希望を書きます。
実務上は、3ヶ月単位で伸長してもらえます。
裁判所HP:熟慮期間伸長の申立書記載例
3.熟慮期間を過ぎたやむをえない事情があるとき
(1) 被相続人に債務があることを知らなかったとき
たとえば、被相続人が死亡したことおよび自分が相続人であることの両方を知ってから3ヶ月が経ってしまっているものの、「被相続人に債務があることが後から判明した」というケースもあります。
こうしたケースでは、被相続人が「相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じた相当な理由」があれば、一定の場合には通常とは異なる起算点になり、熟慮期間がズレる可能性もあります。
最高裁昭和59年4月27日判決
三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
したがって、単に「うっかり、のんびりしていた」等の事情では難しいですが、家庭裁判所がやむをえない事情があると判断できるようなケースでは3ヶ月を過ぎても認めてもらえることが有り得ます。
こういったケースでは、3ヶ月を過ぎてしまった理由を説明するために、上申書を用意することが考えられます。詳しくは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
(2) 再転相続によって相続人となったとき
再転相続とは、ある相続が発生したときに(第一相続)その相続人が相続の承認または放棄の意思表示をしないまま亡くなってしまい、新たな相続が発生(第二相続)することです。
たとえば、子Aの祖父が亡くなり、子Aの父が相続人になったものの、父が相続について何ら意思表示しないまま亡くなった場合、子Aは①(父が持っていた)祖父を被相続人とする相続の相続権と②父を被相続人とする相続の相続権の両方を持つことになります。これが再転相続の状況です。
再転相続の熟慮期間については、民法には次のような規定があります。
民法第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間(注:熟慮期間)は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
しかし、この規定だけでは子Aの熟慮期間がいつから始まるかはまだ確定できません。
子Aが、父が亡くなったことと自分が父の相続人であることを両方知っている(自己のために相続の開始があったことは知っている)ものの、祖父の相続権が自分に回ってくることまでは知らなかったというケースもあるからです。
この点は、次のような判例があります。
最高裁令和元年8月9日判決
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。
つまり、先ほどの例で言えば、子Aが父の相続によって、自分が祖父の相続人にもなったことを知った時から、熟慮期間が始まるということになります。
再転相続の熟慮期間の考え方は複雑ですので、こちらも弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
4.相続放棄の手続きは弁護士に相談を
相続放棄について迷われたら、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
相続放棄自体の手続き、相続放棄の熟慮期間伸長の申立て手続きなど手厚くサポートいたします。
また、熟慮期間を過ぎてから相続放棄をするには特に弁護士の力が役立ちます。
泉総合法律事務所では、ご事情を伺い、裁判所に納得してもらえるよう手続きを進めてまいります。まずはお気軽にご相談ください。