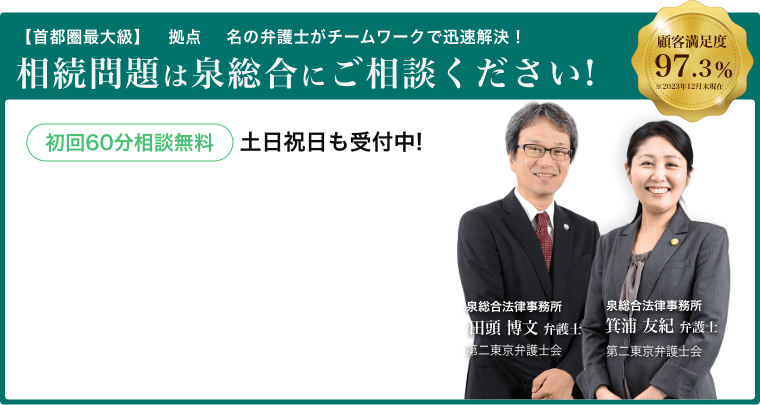相続時精算課税制度とは?

相続税対策としてまず考えられるのが「生前贈与」です。
生前贈与の税制には、毎年の贈与合計額から基礎除額である110万円を差し引いた金額に贈与税が課税される「暦年贈与」以外に、贈与者の相続時にまとめて相続税を支払う「相続時精算課税制度」という制度があります。
今回の記事では、「相続時精算課税制度」に焦点を当てて、「暦年贈与」との違いについて説明します。
1.相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は生前贈与の一形態です。
生前贈与には税制上次の2種類の方法があります。
- 暦年贈与
- 相続時精算課税
まず、相続時精算課税制度とはどんな制度なのかについて見ていきます。
(1) 相続時精算課税制度の概要
暦年贈与は、1月〜12月の贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に、贈与税が課税されます。
対して相続時精算課税制度とは、原則、贈与時には贈与税が非課税となり、贈与者の死亡時に、贈与者(被相続人)の相続財産に含めて相続税が課税される制度です。
相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除枠があり、贈与合計額がこの金額以下の場合、贈与税は非課税となる一方、贈与者の相続時に贈与財産の合計を相続財産に加算して相続税として課税されます。
相続時精算課税を利用できる者は以下の通りです。
- 贈与者:贈与した年の1月1日において60歳以上の直系尊属(父母、祖父母等)
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子ども、および孫
暦年贈与と相続時精算課税は二者択一で、一度相続時精算課税を選択すると、暦年贈与に戻す事はできません。
贈与を受ける受贈者から見て、贈与者ごとに、暦年贈与か相続時精算課税かを決められます。
例えば、父と母から子どもに贈与する場合、父から子どもの贈与を相続時精算課税、母からの贈与を暦年贈与とすることができます。
(2) 税率について
①相続時精算課税制度の課税方式
贈与財産の総額が2,500万円の特別控控除を超える部分については、一律20%の税率で計算した贈与税を納税します。
その後、贈与者の相続が発生した際に、相続時精算課税の対象の贈与金額全てを相続財産に含めて相続税の計算をして、相続税として納税します。
ただし、特別控除枠の2,500万円を超えて贈与税20%を支払っている場合は、相続税から差し引かれて相殺されます。
②相続時精算課税制度の税率
では、相続時精算課税を利用した場合に贈与者が死亡すると、相続税はどれくらいかかるのでしょうか?
下記に、相続税の税率の一部を抜粋してご紹介します。
| 法定相続分に応じた取得分 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
一方で暦年贈与の場合は、受贈者ごとに、贈与を受けた年間の合計額から110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与にかかる税率は次のとおりです、
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続税の税率と比較すると、贈与税の税率は非常に高く設定されています。
2.相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度は、使う際に注意すべきメリットとデメリットがあります。
(1) 相続時精算課税制度のメリット
2,500万円までの贈与に贈与税が非課税
「相続時精算課税制度」という名前の通り、贈与者の相続時に相続税として課税される制度ですので、特別控除枠の2,500万円までは贈与時が非課税となります。
価値の高騰が見込まれる財産を贈与すれば相続税の節税
相続時精算課税制度では、贈与者の相続財産に加算されて相続税が加算されますが、相続財産に加算する贈与財産は「贈与時の時価」となります。
そのため、将来的に値上がりする財産を贈与することにより、相続税の節税になります。
例えば、相続時精算課税制度を使い、父親から長男へ、令和1年5月1日に株式会社Aの株式1,000万円を贈与したとします。
令和1年の贈与税は、贈与額が2,500万円以内なので非課税となります。
父親が令和3年5月1日になくなり、その時の株式会社Aの株式評価額が1,500万円になっていた場合、父親の相続財産に加算されるのは、相続時の評価額1,500万円ではなく「贈与時の評価額:1.000万円」です。
結果として、このケースでは相続財産を500万円少なくすることができます。
収益財産を贈与すれば相続税の節税
例えば、父親が所有する不動産を活用して「駐車場経営」を行っているとします。
駐車場経営に使っている不動産の路線価評価額2,500万円、年間の駐車場収入200万円と仮定した場合、父親から長男に当該不動産を相続時精算課税制度で贈与することにより、贈与税と駐車場の収益は次のような扱いとなります。
- 不動産2.500万円の贈与税は非課税(父親の相続税として課税)
- 贈与以降の駐車場収入200万円は、長男の収入
結果的に、駐車場の収益である年間200万円が「父親の収入から長男の収入」となり、父親の相続時の財産がこの駐車場収入分減りますので、父親の相続税の節税になります。
贈与税額が相続税額より大きければ還付される
相続時精算課税では、贈与税の非課税枠2,500万円を超えて支払った贈与税は、相続税と相殺され、支払った贈与税が相続税よりも大きい場合は、納めすぎた贈与税が還付されることになります。
(2) 相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度を利用した相手には暦年贈与を利用できない
暦年贈与と相続時精算課税は二者択一で、一度相続時精算課税を選択すると暦年贈与に戻す事はできません。
例えば、父親から長男への贈与を「相続時精算課税」としてしまうと、父親から長男への贈与については、もう二度と「暦年贈与」に戻すことはできなくなります。
結果的に、110万円が控除できる「暦年贈与」は使えなくなります。
贈与税の基礎控除以下でも申告が必要
暦年贈与であれば、基礎控除110万円を越えなければ、原則申告は必要ありません。
一方で、相続時精算課税においては、贈与者が亡くなるまでの間、年をまたいで贈与財産の額を管理しなければならないうえに、贈与の金額にかかわらず贈与税の申告をしないといけません。
相続税時に相続税が課税される
一方で、贈与者の相続時に相続税として課税さますので、贈与財産の総額と相続財産総額の合計額について納税資金を準備しておく必要があります。
小規模宅地等の特例が併用不可
「小規模宅地等の特例」とは、例えば、被相続人が住んでいた宅地を、一定の要件を満たす相続人が相続した時に、相続税評価額を80%削減することができる特例です。
この特例は相続または遺贈によって取得した宅地に適用されるものですので、生前贈与した宅地にはこの特例は適用できません。
小規模宅地等の特例を使いたい場合は、生前贈与は行わずに、相続または遺贈により取得するようにしましょう。
 [参考記事]
小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引
[参考記事]
小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引
3.相続時精算課税制度を利用する手続き
相続時精算課税制度を利用するための手続きとして、初めて当該贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの贈与税申告期間に贈与税の申告を行うのと同時に、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出します。
提出書類は次のとおりです。
- 贈与税申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 添付書類
(受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類)
○受贈者の氏名、生年月日
○受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
4.税額の実際の計算例
最後に、下記の条件で、相続時精算課税と暦年贈与の税額を計算してみます。
贈与者:父親、受贈者:長男
贈与額:
2015年5月1日…預貯金1,000万円
2016年5月1日…預貯金1,000万円
2017年5月1日…預貯金1,000万円
贈与者死亡日:2021年3月1日
相続人:長男一人
(1) 相続時精算課税の場合
特別控除枠2,500万円までは贈与税がかかりません。
2015年
相続時精算課税の累計額1,000万円:贈与税額0円2016年
相続時精算課税の累計額2,000万円:贈与税額0円2017年
相続時精算課税の累計額3,000万円:贈与税(3,000−2,500)×20%=100万円
贈与者死亡時に、贈与者(被相続人)の相続財産に「相続時精算課税の累計額3,000万円」を加算して、相続税を算出します。
長男が支払う相続税は、すでに贈与税として納税している100万円を差し引いた税額となります。
(2) 暦年贈与の場合
年間の贈与額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に、贈与税が課税されます。
2015年
贈与税(年間贈与額1,000万円−基礎控除額110万円)×30%−90万円=177万円2016年
贈与税(年間贈与額1,000万円−基礎控除額110万円)×30%−90万円=177万円2017年
贈与税(年間贈与額1,000万円−基礎控除額110万円)×30%−90万円=177万円2015年から2017年で合計:531万円
(3) 相続時精算課税と暦年贈与の税額はどちらが低い?
上記の例では、相続時精算課税を使った場合100万円の贈与税を支払い、暦年贈与の場合は、合計531万円の贈与税を支払います。
一見すると相続時精算課税のほうが低い税額に見えますが、相続時精算課税は相続税がかかります。
例えば、上記の例で死亡時の財産が500万円と仮定した場合は、相続時精算課税3,000万円を加えて3,500万円が相続財産となります。
上記例の場合、相続税の基礎控除額が3000万円+(600万円×相続人1人)3,600万円となり、結果的に相続税ゼロとなりますので、相続時精算課税で納税した贈与税100万円が還付されます。
しかし、死亡時の財産が8,600万円あったと仮定した場合は、基礎控除額3,600万円を差し引いた5,000万円に相続時精算課税3,000万円を加えた金額8,000万円が課税財産となります。
5,000万円〜1億円の相続税率は30%ですので、相続時精算課税に対応する相続税は、3,000万円×30%=900万円となります。
このように、相続税まで考慮すると、「死亡時の財産額」や「相続人の数(基礎控除額)」等の条件によって、暦年贈与よりも相続時精算課税の税額の方が高くなったり安くなったりします。
そのため、相続時精算課税制度を選ぶか選ばないかは、相続税まで考えて判断することをお勧めします。
(4) 他の贈与税の非課税制度と併用可能
贈与税の非課税制度は何種類かあり、相続時精算課税制度と併用して使用できる主な制度には次のようなものがあります。
- 住宅取得資金等の一括贈与(適用期限2021年12月31日まで※)
- 結婚・子育て資金の一括贈与(適用期限2023年3月31日まで)
- 教育資金の一括贈与(適用期限2023年3月31日まで)
※ただし、2022年度の「税制改正大綱」では、この制度が2023 年12月31日まで2年延長されることになり、法案として取りまとめられた後、年明けの通常国会に提出されます。
5.まとめ
今回は、「相続時精算課税制度」について見てきました。
この制度をはじめ、生前贈与を計画的に利用することにより、効果的に節税することができます。
続時精算課税制度以外にも、節税効果のあるいろいろな特例がありますので、これらの特例を使うことにより、更に節税効果を高めることができます。
一方で、節税に関しては法令も頻繁に変更されますし、特例を正しく使わないと逆に税金が増えてしまうリスクもあります。
泉総合法律事務所では、長年相続問題について力を入れてきたことから、相続に関する税金に詳しい税理士とも関係を深めてまいりました。相続や贈与に関する税制についてお悩みであれば、ご紹介することも可能です。
是非、お気軽にご相談ください。