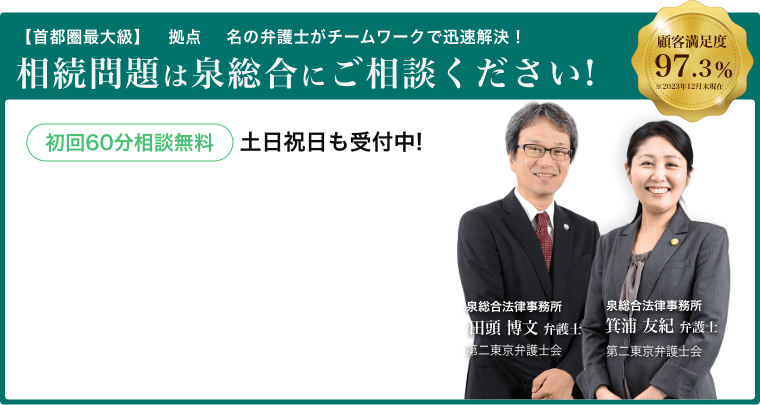相続財産の時効取得ができる要件とは?

相続は、故人(被相続人)の配偶者や子など、法定相続人が当然に相続財産を取得する制度です。
ところが、相続財産を、相続人が時効制度に基づいて「時効取得」する場合があります。これはいったいどのようなケースなのでしょうか?
また、相続財産を時効取得する場合、どのような手続が必要なのでしょうか?
1.相続財産を時効取得できる要件
取得時効とは、たとえ他人の財産であっても、長期間にわたって占有し続けた場合、その財産の所有権を取得できるという制度です。
かかる時効取得制度は、永続した事実状態を尊重し、法的な権利にまで高めて保護するものと理解されています。
相続人が相続財産を取得時効制度によって取得する場合は様々なパターンが考えられますが、典型的には次のケースです。
ABCが共同相続した相続財産を、Aが単独で20年間占有し続けた。BCが自分たちにも利用させるよう要求したところ、Aが時効取得による単独所有を主張して、BCの要求を拒否した。
この場合、はたしてAの主張は認められるのでしょうか?
Aの主張が認められるかどうか、民法の定める取得時効の要件を検討していきましょう。
取得時効を定めた条文は次のとおりです。
【民法第162条】
第1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
第2項 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(1) 「所有の意思をもって」
取得時効を認めるための占有(物に対する事実的支配)は、所有の意思に基づく占有でなくてはなりません。
「所有の意思」とは、所有者として占有する意思であり、所有者がなしうると同様の排他的支配を事実上行おうとする意思です。
所有者のように支配する意思であって、自分が所有者だと信じている必要はありません。
この所有の意思をもってする占有を「自主占有」と呼び、それ以外の占有を「他主占有」と呼びます。
【自主占有の判断基準】
自主占有か否かは、その占有を生じさせた原因たる事実、すなわち「占有の権原」の性質によって客観的に決まります。このため、例えば賃借人は他人から物を借りているので、その内心にかかわらず自主占有ではありません。
これに対して売買の買主は常に自主占有ですし、物を盗んだ犯人さえも、常に自主占有者と評価されます。
取得時効の制度は客観的な事実状態を尊重する制度で、仮に自主占有か否かを占有者の主観的事情によって決めるなら、外部から判別がつかず、真実の権利者が取得時効の成立を阻止する機会を失う危険があります。
冒頭の典型的なケースのように、共同で相続した財産を共同相続人の1人が占有している場合、それが自主占有と評価できるかどうかが大きな問題です。
この点、共同相続した遺産は共同相続人の共有財産ですから、共同相続人の1人が遺産を占有している場合、他の共同相続人との関係では、あくまで他人の共有物を管理しているに過ぎません(一種の事務管理と言われています。)。
より厳密に言うと、自己の相続分に対応した自己の共有持分権については自主占有ですが、他の共同相続人の共有持分権については、その者(他の共同相続人)に対して自己に所有の意思のあることを表示しない限り、自主占有にはなりません(※広島高裁松江支部昭和30年3月18日判決(高等裁判所民事判例集8巻2号168頁))。
したがって、共同相続人の1人が遺産の占有を開始、継続しても、他の共同相続人に対して自己に所有の意思のあることを表示しなかった場合、遺産全体の自主占有にはならないので、取得時効は成立しません。これが原則です。
共同相続人の自主占有が認められた判例
ただし、判例は一定の例外を認めています。
それは、共同相続人の一人が、他にも共同相続人がいることを知らないため、単独で相続権を取得したと信じて当該不動産の占有を始めた場合など、「その者に単独の所有権があると信ぜられるべき合理的な事由がある場合」です。
例えば、次のようなケースがあります。
【ケース1】
昭和15年に被相続人Aが死亡して相続が発生した事案です。遺産の土地を、BCDEFの5名が共同相続しました。ところが、当時は戸主による家督相続制度がとられていたことなどから、戸主Bが単独で相続したと誤信してしまい、Bのみが遺産の土地を占有、使用し、収益も得て、税金も支払ってきました。一方、他の共同相続人は、本当は自分たちが共同相続していたという事実を知らず、B単独の使用収益にも無関心で、異議を述べたこともありませんでした。
この事案では、最高裁は次のように述べて、自主占有を認めました(最高裁昭和47年9月8日判決)。
「共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかつたような場合には、前記相続人はその相続のときから自主占有を取得したものと解するのが相当である。」
【ケース2】
被相続人Aが死亡し、不動産をBCDが共同相続しました。ところがBはCDに無断で、CDの相続放棄を司法書士に依頼し、CDの虚偽の相続放棄の申述手続を行わせたうえ、Bが単独で相続したとして土地をB名義に登記しました。CDがBに対し、登記名義をBCDの共有名義に更正するよう求めたところ、Bは自主占有による取得時効を主張しました。
原審は取得時効を認めましたが、最高裁は自主占有と認めるには「その者に単独の所有権があると信ぜられるべき合理的な事由がある場合」であることが必要とし、本件Bは、CDという共同相続人の存在を知りながら、あえてCD名義の虚偽の相続放棄の申述をして単独名義の相続登記をしたのだから、自主占有の成立を疑わせる事実があるとして原審の判決を破棄しました(最高裁昭和54年4月17日判決)。
(2) 「平穏」かつ「公然」
取得時効が認められるための占有は、「平穏」かつ「公然」でなくてはなりません。
「平穏」とは、占有が暴行や脅迫など暴力的な態様ではないことを意味し、「公然」とは占有が世人の目に触れないように隠されて行われたものではないことを意味します。
(3) 「他人の物」
取得時効の条文は、「他人の物を占有した者」と定めています。
このため、共同相続した遺産は共有物であり、占有者からみて「他人の物」ではなく要件を充たさないのでは?と疑問があります。
しかし、自己の物であっても取得時効を認めるのが判例の立場です(前述の最高裁昭和47年9月8日判決など)。
取得時効制度は、永続する事実状態を保護する制度なので、保護に値する占有を開始、継続している以上、所有者が自己の権利を主張立証する手段として時効制度を利用することを禁ずる理由はないからです。
(4) 善意・無過失
取得時効に必要な占有継続期間は20年が原則ですが、その占有開始時点において、「善意であり、かつ、過失がなかったとき」には、10年で取得時効が認められます。
「善意であり、かつ、過失がなかったとき」とは、自己の所有物と信じ、そう信じたことについて過失がないことです。
2.時効取得の手続きと注意点
(1) 時効の援用
占有者に取得時効が認められるためには、時効の「援用」が必要です。
援用とは、時効によって直接に利益を受ける者による時効の主張であり、この主張がない場合、裁判所は時効の成立を認めることはできないとされています(民法145条)。
時効制度による恩恵を受けるか否かを、利益を受ける本人の意思に委ねたものです。
(2) 取得時効と登記
冒頭の例で、Aが相続不動産の単独所有権を時効取得した後に、その登記名義をAの単独名義としないままにしておくと、せっかく時効取得した権利を失ってしまう危険があります。
Aの取得時効が完成した後、登記をしていないうちに、BやCが自己の共有持分を第三者Dに譲渡し、Dが所有権移転登記を経てしまったときには、Aは時効による所有権取得をDに主張できないとするのが判例だからです(※最高裁昭和33年8月28日判決)。
(3) 所得税の課税対象になる
相続財産の時効取得は、無償での財産取得ですから、その財産の時価が経済的利益となり、時効を援用した年の一時所得として所得税の課税対象となります(所得税法34条1項及び2項、36条1項及び2項、所得税基本通達36-15)。
3.まとめ
ここに説明した以外にも、相続財産について時効の成否が絡む問題は数多くあります。
相続財産の時効取得をお考えの場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。