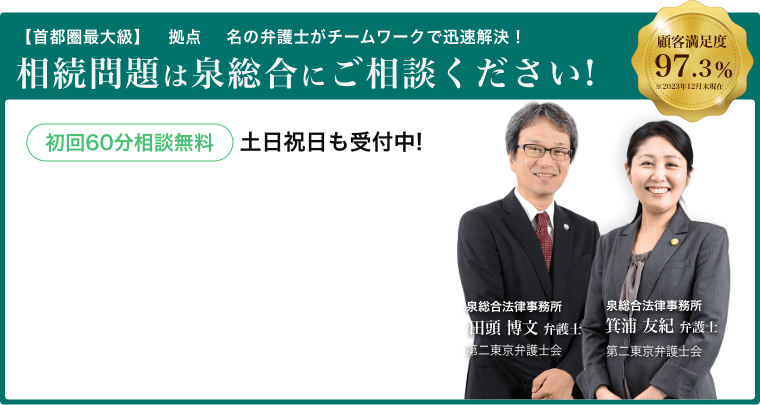不動産の遺贈を受けたら登記を忘れずに|相続登記の必要性・手続き

遺言書によって不動産の遺贈を受けたとしても、それだけで不動産を取得できたと安心してはいけません。
不動産に対する権利を確実なものとするためには、速やかに遺贈の「登記」を行う必要があります。
遺贈の登記手続が遅れてしまうと、最悪の場合、不動産に対する権利を失ってしまう事態にもなりかねません。
できる限り早めに弁護士などへ相談して、遺贈の登記を早期に完了できる手筈を整えましょう。
今回は、不動産の遺贈を受けた場合に、遺贈の登記を行うことの効果や重要性などを解説します。
1.不動産の「遺贈」とは?
「遺贈」とは、遺言による贈与を意味します。
遺贈は、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類に大別されます(民法964条)。
包括遺贈
遺産を割合的に指定して行われる遺贈です。遺産の全部を指定して遺贈することも可能です(全部包括遺贈)。
(例)Aに、全遺産の3分の1を遺贈する。
特定遺贈
遺産を特定して行われる遺贈です。
(例)Aに、X不動産を遺贈する。
特定の不動産を遺贈することは「特定遺贈」に該当します。
不動産の(特定)遺贈が行われた場合、相続開始時点で、被相続人(遺言者)から受遺者(遺贈を受けた人)に不動産の所有権が移転します。
2.不動産の遺贈後は速やかに相続登記を行うべき
もし不動産の遺贈を受けたら、不動産に対する権利を保全するため、速やかに相続登記(所有権移転登記)の手続きを行うことをお勧めいたします。
(1) 遺贈の相続登記の法的効果
不動産についての物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できないとされています(民法177条)。
つまり遺贈の登記は、「遺贈によって不動産の所有権を取得した」ことを第三者に主張するために必須の手続きなのです。
なお、ここで言う「第三者」とは、登記の不存在を主張することについて、正当な法律上の利益を有する者を意味します。
典型的には、被相続人や他の相続人から不動産を購入した(と主張する)人などです。
ただし、未登記不動産の所有者に対する嫌がらせ目的や、暴利をむさぼる目的で、当該不動産の購入等を行ったなどの、いわゆる「背信的悪意者」については、信義則上、登記の不存在を主張する正当な利益を有しないと解されています(最高裁昭和43年8月2日)。
したがって、背信的悪意者である第三者に対しては、遺贈の登記を具備していなくても、遺贈によって不動産の所有権を取得した事実を主張することが可能です。
(2) 遺贈の相続登記をしないとどうなる?
遺贈の登記を怠っていると、受遺者は最終的に、不動産の所有権を失ってしまうおそれがあるので要注意です。
具体的な設例を2つ見てみましょう。
<設例①>
・Aは、被相続人から不動産Xの遺贈を受けた。
・Bは、被相続人が亡くなる前に、被相続人から不動産Xを購入した。
・Bは(Aよりも先に)、不動産Xについて、被相続人からの所有権移転登記を受けた。
設例①では、Aは不動産Xについて遺贈の登記を受けていないため(又はBより後に遺贈の登記をしたため)、被相続人が不動産Xを二重譲渡したBに対して、不動産Xの所有権を対抗することができません。
それどころか、Bが(Aより先に)不動産Xの所有権移転登記を経由したため、不動産Xの所有権はBが取得することが確定します。
その結果、Aは遺贈を受けたはずの不動産Xの所有権を、すべて失ってしまう結果となるのです。
<設例②>
・相続人Cは、被相続人から不動産Xの遺贈を受けた。
・C以外の唯一の相続人であるD(Cの兄)は、自らの法定相続分に相当する、不動産Xに係る2分の1の共有持分をEに譲渡した。
・Eは(Cよりも先に)、不動産Xに係る2分の1の共有持分について、共有持分権移転登記手続を行った。
設例②では、相続人Cは民法899条の2第1項の規定に基づき、自分の法定相続分に相当する、不動産Xに係る2分の1の共有持分権の取得についてEに対抗できます。
その反面、Cの法定相続分を超える、残りの2分の1の共有持分権の取得については、遺贈の登記手続をしていない(又はEに遅れて遺贈の登記手続をした)ので、Eに対抗することができません。
残りの2分の1の共有持分権については、Eが先に共有持分権移転登記手続をしたため、Eが確定的に取得することになります。
その結果、不動産X全体を遺贈により取得できるはずだったCは、その半分の共有持分権を失い、見知らぬEと不動産Xを半分ずつ共有する状態になってしまいます。
このように、遺贈を受けた不動産について、所有権移転登記を具備せずに放置していると、誰かに不動産に対する権利を奪われてしまう事態になりかねないので注意が必要です。
3.不動産の遺贈について相続登記をする方法
不動産の遺贈を受けた際、相続登記の手続きを誰が行うかは、「遺言執行者」がいるかどうかによって変わります。
(1) 遺言執行者がいる場合|遺言執行者が相続登記を申請
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するための事務を行う者を指します。
遺言者(被相続人)は、遺言書の中で記載することにより、遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することが可能です(民法1006条1項)。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。
「遺言の執行に必要な一切の行為」には、遺贈の登記も含まれます。
したがって遺言執行者は、遺贈の登記手続を単独で申請することが認められます。
遺贈の登記手続を行うタイミングについては、遺言執行者が裁量によって決定します。
ただし、遺言執行者には善管注意義務(民法1012条3項、644条)が課されています。
そのため、正当な理由なく遺贈の登記手続きを遅滞した結果として、受遺者が損害を被った場合には、遺言執行者に対して損害賠償を請求することが可能です。
 [参考記事]
遺言執行者は誰がなれるの?弁護士・弁護士法人ではどちらがいい?
[参考記事]
遺言執行者は誰がなれるの?弁護士・弁護士法人ではどちらがいい?
(2) 遺言執行者がいない場合|相続人全員が共同で相続登記を申請
遺言執行者がいない場合には、不動産登記法の原則に従い、遺贈の登記は登記権利者と登記義務者の共同申請となります(不動産登記法60条)。
本来であれば、登記権利者は受遺者、登記義務者は被相続人(遺言者)です。
しかし、被相続人はすでに亡くなっているため、相続財産を共有する相続人全員が登記義務者となります(民法898条参照)。
したがって、遺言執行者がいない場合における遺贈の登記は、共同相続人が全員で申請することが必要です。
他の相続人が非協力的な場合
遺言執行者がいないケースにおいて、他の相続人の一部が遺贈の登記に非協力的である場合には、共同相続人全員で遺贈の登記を申請することができません。
この場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の審判を申し立てることができます。
家庭裁判所は、遺言執行者が不在ゆえに、遺言に関する事務が滞っている実態があると認めた場合には、新たに遺言執行者を選任する審判をします。
家庭裁判所によって選任された遺言執行者は、遺言によって指定された遺言執行者と同様に、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。
したがって、遺言執行者は単独で遺贈の登記手続申請が可能となり、登記申請が滞る事態を解消できます。
遺言執行者選任の審判に関する申立先・費用・必要書類などについては、以下の裁判所ホームページをご参照ください。
参考:遺言執行者の選任|裁判所
4.不動産の遺贈登記の手続き・必要書類
不動産の遺贈に関する所有権移転登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局の登記所に申請して行います。
具体的な手続き・必要書類・費用などについては、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。
 [参考記事]
相続登記の申請方法は?手続き・必要書類・登記申請書の書式・費用
[参考記事]
相続登記の申請方法は?手続き・必要書類・登記申請書の書式・費用
不動産の遺贈の登記手続については、司法書士に依頼するのがスムーズです。
遺産分割や遺言執行について弁護士にご相談いただければ、遺贈の登記についても司法書士と連携を行い、ワンストップでご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
5.まとめ
不動産の遺贈を受けた場合、速やかに遺贈の登記手続を行い、不動産に対する権利の保全を図ることが大切です。
遺贈の登記を怠っていると、不動産に対する権利を主張する第三者が登場し、その第三者に権利を奪われてしまう事態になりかねません。
そのため、相続発生後に遺言の内容を確認したら、速やかに遺贈の登記手続を完了しましょう。
遺贈の登記手続を行う際には、多数の必要書類を集めなければならない点が煩雑です。
弁護士にご相談いただければ、提携先の司法書士と連携を行い、スムーズに遺贈の登記手続を完了いたします。
不動産の相続・遺贈に関するご相談は、ぜひお早めに弁護士までご連絡ください。