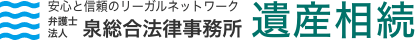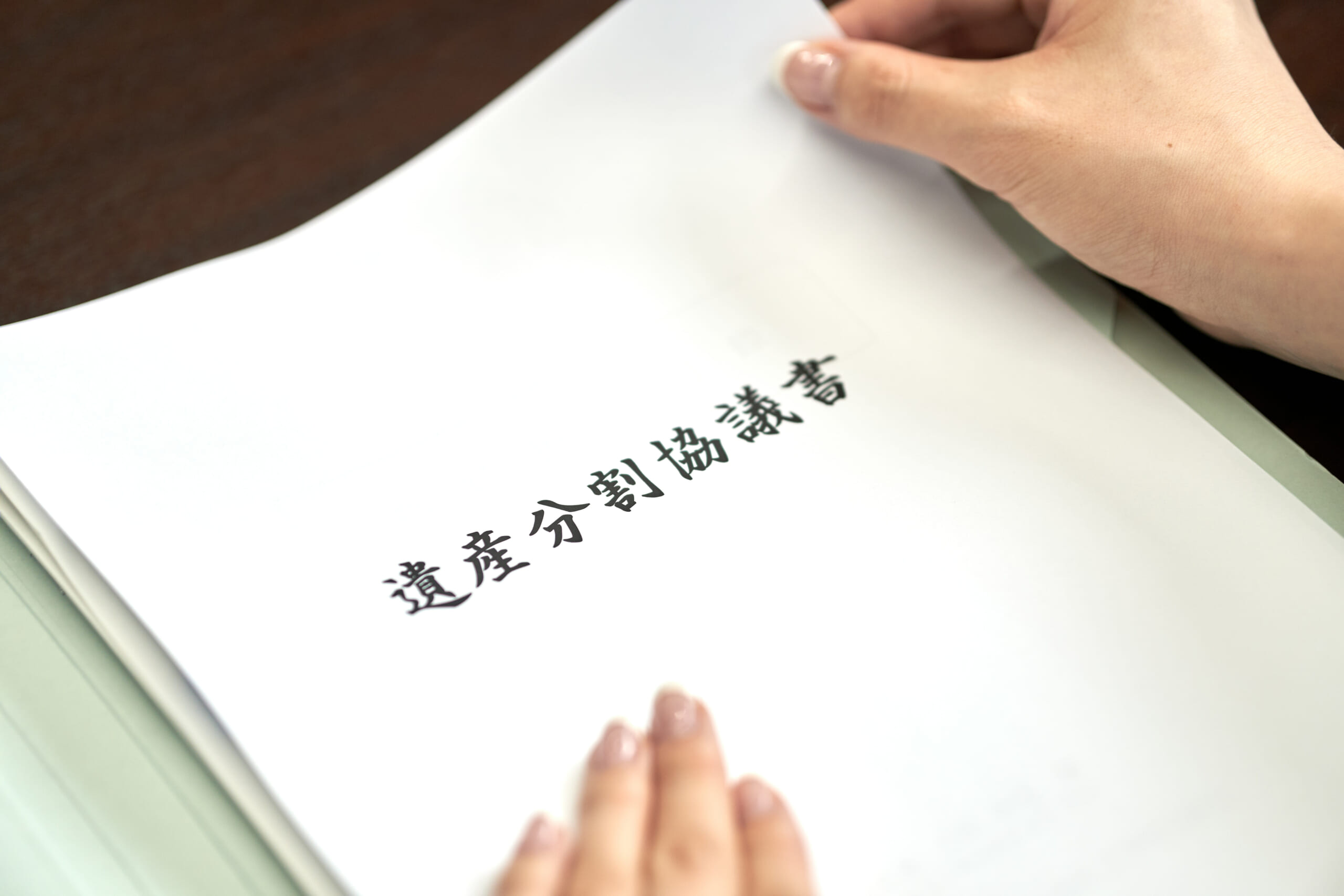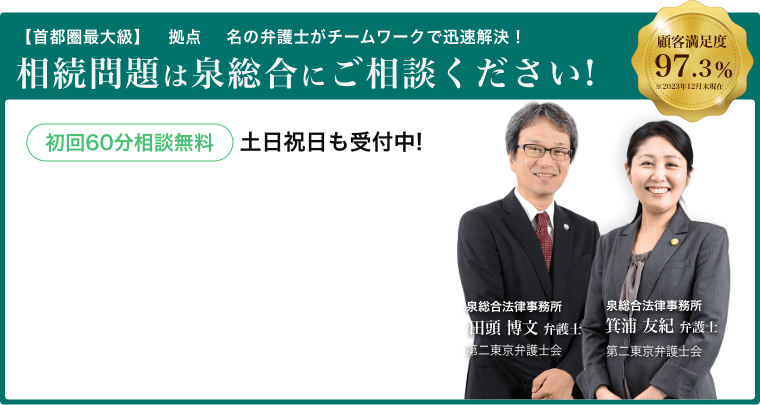遺産分割審判の進め方と気を付けるべきポイント

遺産分割「調停」が裁判所での「話し合い」だということは、今では広く知られており、イメージも湧きやすいかと思います。
しかし、遺産分割「審判」となると、「訴訟」とは違うのか?具体的にどんな手続でどのように進行するのか?など、多くの方はイメージが浮かばないと思われます。
この記事では、そんな「遺産分割審判」を理解するための、基本的な知識と流れを解説します。
なお本記事での法律の条文は、特に記載のない限り「家事事件手続法」を指します。
1.遺産分割調停から遺産分割審判への移行
遺産分割が共同相続人間の協議でまとまらない場合には、ほぼ例外なく遺産分割調停手続を経ることになり、調停でも合意できない場合に、最終的に遺産分割審判で決着がつくことになります。
遺産分割審判に至るルートには、次の2つのパターンがあります。
(1) いきなり遺産分割審判を申し立てる
調停を経ずに遺産分割審判を申し立てることも制度上は可能です。遺産分割審判は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意によって定めた家庭裁判所に申立てをすることになります。
ただし、調停を希望しない者がいきなり遺産分割審判の申立てをした場合は、特段の事情がない限り、裁判所の判断によって調停手続に回されます。これを「付調停」と言います(274条1項)。
相続問題は親族間の話し合いでの解決が望ましく、また調停であれば、法定のルールにとらわれない柔軟な解決が可能だからです。
付調停とされると、審判事件と調停事件が併存することになりますが、調停事件が終了するまで審判事件は手続中止となり、調停が不成立となったときに、もともと係属していた審判事件の手続が再開されて進行します(275条2項)。
一方、調停が成立した場合には、審判は終了します(276条2項)。
(2) 遺産分割調停を行ったが不成立となる
遺産分割調停を行ったものの不成立に終わった場合は、自動的に遺産分割審判の手続きに移行し、遺産分割調停申立ての時点で遺産分割審判の申立てがなされていたものと扱われます(272条4項)。
こちらの流れが一般的であり、遺産分割審判は、実質的には「調停プラス審判」というセットの一部と考えて問題ありません。
2.遺産分割審判手続の特徴
次に、遺産分割審判手続の特徴についてご説明します。
(1) 審判は訴訟に似ている
遺産分割審判は訴訟ではありません。
民事訴訟では、当事者が互いに主張・立証の攻防を行い、裁判所が公平な第三者として判断する「当事者主義」を採用しています。
他方、家庭裁判所の審判は、裁判所が自ら事実を調査する「職権探知主義」が採用されています(56条1項)。ここでは、当事者は裁判所の証拠収集・事実調査活動に協力する立場と位置づけられます(56条2項)。
しかし、裁判所が自ら事実を調査すると言っても、相続問題という家庭内の事情を外部の裁判所が、何らの手掛かりもなしに調査することは困難です。また、そもそも、相続問題は法律上では財産の争いであって、一般の民事紛争と、そう大きな差違があるわけではありません。
そこで、実務の運用は、まず当事者に主張させ、証拠も提出させて、裁判所から見て主張立証が足りない部分については、裁判所から当事者に主張・立証を促し、裁判所の職権で補充的な調査を行った上で、裁判所が判断を下すという運用になっています。
(2) 当事者の攻防は調停で終わっている
では調停が終わって審判となったら、いよいよ当事者の間で主張・立証合戦が始まるかというと、実際にはそうでもありません。
当事者同士の主張立証は、既に調停の段階で終わっているケースが大半だからです。
遺産分割調停は、裁判所における話し合いですが、単に調停委員が双方の言い分を聞いて相手に伝え、利害を調整するだけのものではありません。
遺産は、調停がまとまらなければ、最終的には必ず審判で、法律の枠組みに則って、裁判官によって分割されることが決まっています。
したがって、遺産分割調停は、単に当事者の希望を調整するだけではなく、後の遺産分割審判も視野に入れて、遺産を分割する法的枠組みにしたがい、ひとつひとつの問題点を整理し、解決しながら、最終的な着地点を目指す場でもあるのです。
そして、各問題点をつぶしていきながら、当事者が合意できるかどうかを探ります。
調停で問題点とされるのは、審判において裁判官が遺産分割方法を決める際にも従うことになる法的枠組みであって、裁判所は、各問題点に関する当事者の主張と証拠を、調停委員を通じ、調停の段階で収集するようにしているのです。
このため「遺産分割審判は、先行する調停手続の成果を継承するものである」と言われています(※)。先に、調停と審判はワンセットと説明したのも、この趣旨です。
※『東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用』(判例タイムズ1418号)19頁
3.審判の手続
では、実際の遺産分割審判の手続きの流れをご説明しましょう。
(1) 審判期日まで
審判のベースは、裁判所が主導的な立場で当事者に主張や立証をさせていくという職権探知主義ですから、当事者の主張・立証が調停の段階で出尽くしているなら、調停が不成立となった後に、別途当事者の主張を聞く期日を設けることなく、これまでの主張・立証に基づいて裁判官が審判を下すことも可能です(73条1項)。
実際、特に審判期日を開かず、書面で当事者の意見を聴取するだけで審判を下すというケースもあります。
ただ、通常は、審判を下すには足りない資料などがある場合や、当事者が新たな主張をする機会を与える趣旨で、審判手続に当事者が出頭する期日を指定します。
なお、実務では多くの場合、調停不成立が決まった最終の調停期日において、裁判官から当事者全員に対して、審判を下すために裁判所が必要と考える資料を提出するよう指示すると同時に調停段階で明らかになった争点の内容を確認します。
そして、もしもさらに主張があるなら、指定された期日までに提出するよう指示されます。
(2) 審判期日
当事者の出頭のもと、調停不成立以後に提出された主張や証拠があれば、裁判官がこれを確認します。そのうえで、主張・証拠が全部提出されていることを確認し、審理を終結して(71条)、審判を下す日(審判日)を指定します(72条)。
審理が終結された後は、もはや主張や証拠の提出は許されません。
なお、事案によっては、当事者が裁判官の前で主張や意見を陳述する「審問」を実施するケースがあり(68条)、その場合は事前に「陳述書」の提出が求められます。
さらに、これも事案によって必要があれば、事実調査のひとつとして、証人尋問や鑑定が実施されることもあります。
これらの手続を実施するための期日が必要であれば、別途そのための審判期日を指定し、これらの実施を終え、もはや必要な事実調査は尽くしたことを確認したうえで、審理を終結し、審判日を指定することになります。
(3) 審判の効力
審判日に審判が下されると、家庭裁判所から審判書が送達され、送達の翌日から起算して2週間が経過すると審判内容が確定し(86条1項)、裁判所で確定証明書を入手することができるようになります。
審判書と確定証明書によって、遺産分割に必要があれば、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、不動産の登記義務の履行その他の給付を命ずることができます(196条)。この給付命令には、強制執行の根拠となる債務名義としての効力があります(75条)。したがって、審判の一方当事者が強制執行権を行使した場合には、他方当事者は、無視することも、従わないこともできません。
例えば、遺産として、共同相続人AとBが共有持分2分の1ずつを有する家屋を相続人Aが占有している事案で、相続人Bがこれを取得する審判の場合、次のような審判主文となります。
1、別紙物件目録記載の建物は、申立人Bが取得する。
2、相手方Aは、申立人Bに対し、同建物を明け渡せ。
3、相手方Aは、申立人Bに対し、同建物につき、遺産分割を原因とする共有持分2分の1の持分移転登記手続をせよ。
この審判書(確定証明書付)に基づき、Aが明け渡しに応じない場合に強制的に退去させる手続をとることができますし、Aが移転登記に応じなくても、B単独で移転登記手続を完了することができます。
(4) 審判内容に不服があるとき|即時抗告
審判内容に不服がある場合には、送達の翌日から起算して2週間以内に、高等裁判所に対して「即時抗告」を行わなければなりません(86条1項、198条1項1号)。
即時抗告は審判をした家庭裁判所に提出します(87条1項)。
4.遺産分割審判についてのよくある質問
-
遺産分割審判を弁護士に依頼するとどんなメリットがあるの?
遺産分割審判を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 弁護士は代理人として審判に出席することができるため依頼人は審判に出席する必要がない
- 当事者に代わり、法律に基づいた主張をしてくれる
- 法的に重要な問題を見落としてしまう心配がない
また、審判では、多くのケースで相手方は弁護士を付けてくるでしょう。こちらが弁護士なしでは不利になることが目に見えています。
-
遺産分割審判に欠席することは不利益になる?
審判期日においては、当事者が欠席したとしても手続は進行します。自分が欠席し、相手方の相続人が出席すれば、自分は主張すべきことを主張できず、相手方の相続人だけが自分の主張をすることになります。
もっとも、多くの場合審判では、法定相続分による分割といった決定になるため、大きな不利益はないかもしれません。しかし、ご自分の特別受益や他の相続人の特別受益について主張したい場合に審判を欠席することは、これらが考慮されずに決定が下される可能性があります。
こうしたケースで裁判所に連絡し、欠席理由が「顕著な事由」だと認められれば審判期日を変更してもらえることがあります(同法34条3項)。ただし、審判の相手方相続人の都合もあり、後の進行にも影響するため、簡単ではありません。
遺産分割審判に欠席しながらも不利益を被らない方法には、弁護士に依頼することが挙げられます。
弁護士は代理人として審判に出席することができ、依頼人は審判に出席する必要がありません。弁護士と打ち合わせを行うだけで、依頼人は、遺産分割審判から解放されます。
-
遺産分割審判にかかる費用はいくら?
遺産分割審判にはどれくらいの費用が必要になるのでしょうか?
弁護士費用以外に遺産分割審判でかかる費用
- 遺産分割審判の申し立て手数料(収入印紙代):1,200円/相続人1人につき
- 連絡用切手代:裁判所によって金額は異なるため、管轄裁判所にお問い合わせください
遺産分割審判の弁護士報酬相場
弁護士費用は、主に「着手金」と「報酬金」とから構成されています。
「着手金」は、弁護士が事案に着手する際に発生する費用で、結果の如何にかかわらず支払うことになります。
「報酬金」は、事案の成功時に発生する費用で、事案の終了時に支払います。弁護士事務所が費用を設定する際に今でも参照することが多い旧弁護士報酬基準によると、遺産分割審判での弁護士費用は、次の通りです(なお、金額は全て税抜き表示となります)。
経済的利益の額 着手金 報酬金 ~300万円 8%
ただし最低額は10 万円16% 300万円超~3,000万円 5%+9万円 10%+18万円 3,000万円超~3億円 3%+69万円 6%+138万円 3億円超~ 2%+369万円 4%+738万円 調停から審判へ移行する際の着手金の相場は、経済的利益の額や事案の複雑さなどによって変化しますが、概ね10万円~30万円程度になるでしょう。
報酬金の相場については、上表から概ね経済的利益の6%~16%程度に当てはまることが多いです。当事務所では、わかりやすくリーズナブルな費用設定を心掛けています。
詳しくは「費用について」をご覧ください。
5.遺産分割審判は弁護士に依頼するのがお勧め
遺産分割では、親族同士ということもあって、互いに、長年の不満・鬱憤を晴らすかのような激しいやりとりが行われることも珍しくはありません。
しかし、法律論を抜きにした感情的な言葉の応酬で問題が解決するはずはありません。声が大きい方が勝つわけではないのが裁判所です。
多くの遺産分割審判で争点となるのは、不動産を筆頭とした遺産の評価額や、特別受益の存否、寄与分の認定といったものになります。
こういった問題については、既に多くの審判例が残っており、判断基準も明確になっていることが多いため、過去の審判例を洗いだし、裁判所を納得させる主張をすることが重要になってきます。
遺産分割審判は、当事者の主張・立証を基本として、裁判官が判断する手続ですので、やはり専門的な知識がある弁護士の力が必要になってくると言えるでしょう。
遺産分割について迷われたら、泉総合法律事務所までお気軽にご相談ください。