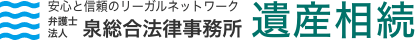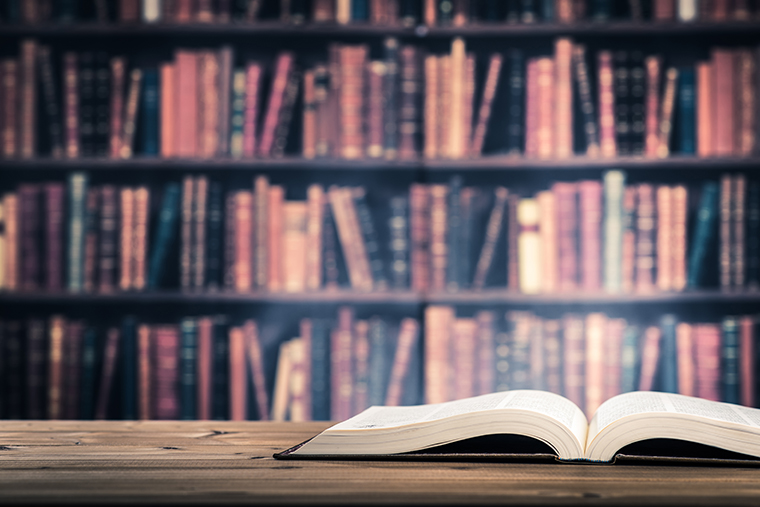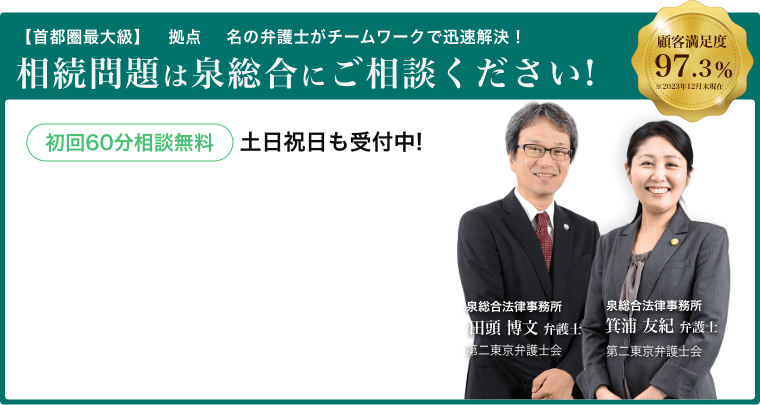相手が遺留分侵害額請求に応じないときの対処法

被相続人が遺した遺言の内容によっては、相続人の遺留分が侵害されていることがあります。例えば子がいるにも関わらず「妻に全財産を相続させる」といった遺言書を、被相続人である夫が残すケースです。
このような場合には、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
しかし、遺留分侵害額請求をしても、相手方から無視されるなどして支払いに応じてもらえないことがあります。そのような場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。
今回は、相手が遺留分侵害額請求に応じないときの対処法について解説します。
1.遺留分侵害額請求について
まず、遺留分侵害額請求の基本について説明します。
(1) 遺留分侵害額請求とは
被相続人は、自分の財産を自由に処分することができ、遺言で相続人の一人にすべての遺産を相続させることも可能です。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
(2) 遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過した場合には、時効によって消滅します(民法1048条)。
そのため、ご自分の遺留分が侵害されていると知った場合には、すぐに遺留分侵害額請求をする必要があります。
(3) 遺留分侵害額請求に失敗しないために
遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと民法が改正されたことで、遺産そのものの現物返還から金銭による清算になりました。遺留分減殺請求をした相手方は、何がしかの遺産を受け取っているため、通常であれば請求に対して支払い不能ということはあまりないかもしれません。
ただし、相手方が受け取った遺産を消費して支払うだけの資力を失ってしまうことや、遺産を隠匿してしまう可能性も考えられます。
そのため、遺留分侵害額請求に失敗しないために、民事保全手続きを利用して、相手方が相続財産を処分するのを防ぐことも一つの方法です。
民事保全手続きは、相続人自身が行うことが難しいため、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
2.遺留分侵害額請求調停の申立の流れ
遺留分侵害額請求をしても、遺留分は渡さないと頑なに相手が応じてくれなければ、裁判所に対して遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。
遺留分に関する争いは、基本的には家族間の争いです。そのため、いきなり訴訟を提起するのではなく、できる限り話し合いで解決することが好ましいとされています。
そこで、「調停前置主義」により、すぐに訴訟を提起するのではなく、まずは調停で当事者の話し合いにより解決を図ることになっています。
(1) 遺留分侵害額請求調停の申立
遺留分侵害額請求調停の申立てをすると、2週間前後で裁判所から第1回調停期日の日程調整の連絡が来ます。日程調整の結果にもよりますが、第1回目の調停期日は、申立てから1か月半から2か月後の日程で設定されます。
調停期日の日程が決まると、裁判所から相手方に対して、呼出状や申立書の写しなどの書類が送付されます。
(2) 第1回調停期日
遺留分侵害額請求調停は、裁判官1名と調停委員2名によって組織される調停委員会が紛争の解決に向けて調整を行うことになります。
調停では、原則として当事者同士顔を合わせて話し合いをすることはなく、お互いの主張は、調停委員を通じて相手方に伝えることになります。
第1回目の調停ですべて解決するということはあまりなく、次回の日程を調整して第1回目の調停は終了となります。
(3) 2回目以降の調停期日から終了まで
2回目以降の調停でも引き続き話し合いが進められ、必要に応じて遺留分侵害額請求の主張を基礎づける資料の提出が求められます。
調停で遺留分の侵害が認められる場合には、相手方には遺留分に相当する金額を支払う義務が生じます。
感情的な理由から遺留分侵害額請求に応じないという場合には、調停委員が説得することで、支払いに応じてくれることもあります。
お互いに一定の譲歩することで、合意ができると調停は終了します。当事者が合意した事項については調停調書に記載され、合意した内容は裁判所の判決と同様に法的拘束力を持つことになります。
何度か調停期日を行っても当事者双方の合意が得られない場合には、調停は不成立となり、次の段階に進むことになります。
3.遺留分侵害額請求訴訟の提起
遺留分侵害額請求調停が不成立になると、最終的に遺留分侵害額請求訴訟を提起して解決を図ることになります。
(1) 遺留分侵害額請求訴訟とは
前述の通り、遺留分侵害額請求調停は当事者同士の話し合いの手続きです。
これに対して、遺留分侵害額請求訴訟では、当事者の主張・立証を踏まえ、最終的に裁判官が遺留分についての判断を下すことになります。
(2) 遺留分侵害額請求訴訟の流れ
遺留分侵害額請求訴訟の流れは、以下のとおりです。
①裁判所への訴状の提出
遺留分は被相続人の遺産に関する争いであり、調停と同様に家庭裁判所が管轄するようにも思えます。しかし、遺留分侵害額請求訴訟は、金銭の請求を目的とする民事訴訟であるため、簡易裁判所または地方裁判所が管轄することになります。
遺留侵害額請求訴訟を提起するためには、管轄する裁判所に対して訴状および証拠を提出します。訴状を提出すると、裁判所が内容に不備がないかをチェックして、問題がなければ受理します。
その後、裁判所は、原告の都合を確認しながら、第1回口頭弁論期日の日程を調整し、日程が決まった段階で訴状などの書類一式を被告に送達することになります。
訴状の送達を受けた被告は、答弁書で訴状記載事実についての認否を行うとともに、反論があれば記載して、第1回口頭弁論期日までに裁判所に提出します。
②第1回口頭弁論期日
当事者は、指定された日時に裁判所に出頭して第1回口頭弁論期日を執り行います。
ただし、被告は、あらかじめ答弁書を提出することによって、第1回口頭弁論期日を欠席することも認められています。これを「擬制陳述」といいます。
③第2回目以降の期日(続行期日)
ほとんどの事件では、第2回目以降の期日が指定され、その後も1か月に1度のペースで期日が開かれることになります。
各期日では、原告および被告が主張を行い、それを裏付ける証拠を提出しながら、争点を明らかにしていくことになります。
④証拠調べ期日
原告および被告の主張立証によって争いのある事実が明らかになると、裁判所の法廷において当事者尋問および証人尋問が行われます。
それまでは書面での主張立証が主でしたが、証拠調べ期日では、当事者や証人から話を聞くことによって当事者の主張する事実の存否を明らかにしていきます。
⑤和解または判決
訴訟は、最終的に当事者の主張と証拠を踏まえて裁判官が判決を言い渡すことになります。ただし、その前の段階で裁判官から和解の提案がなされることがあります。
和解では、その時点での裁判官の事件に対する心証を踏まえた解決案が提示され、それを当事者が受け入れれば、その時点で訴訟は終了となります。他方、和解を受け入れない場合には、その後、必要な手続きを行い判決が言い渡されます。
4.遺留分侵害額請求と弁護士に関するQ&A
-
請求に応じてもらえない時、弁護士に依頼するメリットは?
遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合に弁護士に依頼するメリットには、次のものが考えられます。
- 相手方が請求側の真剣さを理解し、交渉がまとまる可能性が高くなる
- 依頼者が交渉する必要がなく精神的ストレスや負担を軽減できる
- 正確な遺留分の計算が可能になる
- 調停・訴訟に発展しても対応可能
遺留分侵害額請求には時効があります。もし、ご自分で請求することが難しいと感じたら、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
-
弁護士に依頼するべきケースとは?
遺留分侵害額請求に応じてくれない原因には、感情的な理由から応じてくれないケースや遺留分侵害額の計算根拠に納得がいっていないケースがあります。
こういった場合には、弁護士に依頼することで、早期に解決できることがあります。当事者同士での話し合いでは、どうしてもお互いに感情的になってしまいがちですが、弁護士が代理人として交渉を行うと、法的な根拠に基づいて説得的に話し合いを進めることが可能になるのです。
仮に話し合いで解決することができなかったとしても、弁護士に依頼すれば、調停や訴訟手続きを一任することができ、手続き的な負担は相当軽減されます。
遺留分の侵害に気付いた場合には、確実に権利を実現するためにも早めに弁護士に相談をするようにしましょう。
泉総合法律事務所では、遺留分侵害額請求についてのご相談を積極的に承っております。遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、是非一度ご相談ください。