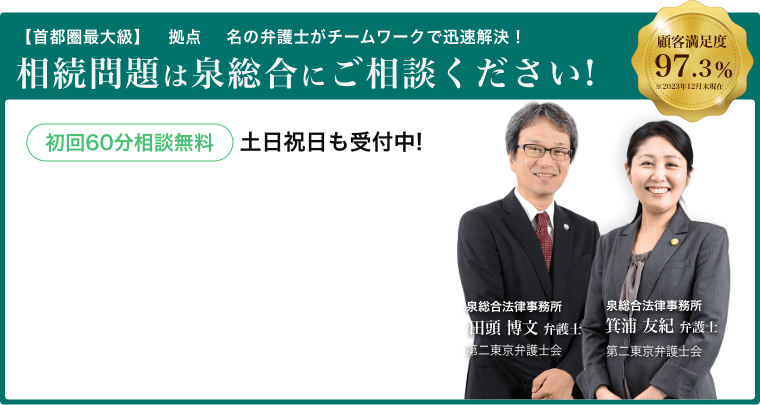遺留分制度は民法改正で何が変わった?改正ポイントと注意点

2019年に施行された改正相続法により、遺留分に関するルールが大きく変更されました。
今回は、遺留分に関する改正の要点について、改正前後のルールを比較しながらわかりやすく解説します。
1.遺留分に関する権利を金銭債権化
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続できる遺産の最低保障額をいいます(民法1042条1項)。
もし、遺言書などにより、遺留分を下回る遺産しか受け取ることができなかった場合には、遺産を多く受け取り他の相続人の遺留分を侵害している相続人に対して、不足分の補填を請求できます。
この不足分の補填を請求する権利を、相続法改正前は「遺留分減殺請求権」と呼んでいましたが、改正後は「遺留分侵害額請求権」と呼ぶようになりました。
改正前の「遺留分減殺請求」は、現物分割を請求できる権利であるのに対して、改正後の「遺留分侵害額請求権」は、金銭による精算を請求できる権利である点に、両者の大きな違いが存在します。
(1) 改正前|現物返還が原則(遺留分減殺請求権)
相続法改正前の制度である「遺留分減殺請求権」では、遺留分権利者が侵害者に対して、遺留分減殺の対象となる遺産そのものを分割したうえで、共有持分を譲り渡すように請求することができました。
たとえば被相続人の子であるAとBの2名が相続人であるケースで、唯一の遺産である自宅の土地・建物(不動産)をAが単独で相続したとします。
この場合、BがAに対して遺留分減殺請求を行うと、自宅の土地・建物の4分の1の共有持分がAからBに対して移転し、土地・建物共AとBの共有状態となりました。
しかし、共有関係はトラブルの元になることも多く、また実際には、遺産の現物自体を欲しない相続人も多かったことから、遺留分減殺請求権は使い勝手の悪さが指摘されていました。
【共有関係を解消するには?】
共有関係を解消するには遺留分減殺請求とは別に「共有物分割訴訟」という手続を採らなければなりません。「共有物分割訴訟」とは、共有関係になってしまった土地建物を競売して現金化し、現金を共有者間で分ける手続きです。
遺留分減殺請求の後、共有物分割訴訟を提訴しなければならないという点からも、遺留分減殺請求は使い勝手が悪いと指摘されていました。
(2) 改正後|金銭請求により手続きが簡便化
相続法改正後に新設された「遺留分侵害額請求権」は、純然たる金銭債権として規定されています(民法1046条1項)。
たとえば前述の例では、Bは相続した自宅の土地・建物を単独で所有したまま、Aに対してはその価値の4分の1に相当する金銭を支払えば、遺留分侵害額に関する精算が完了します。
このように、遺留分の精算を金銭に一本化することで、遺産配分に関する被相続人の意思を尊重するとともに、精算手続きが簡便化され、使い勝手が改善されました。
(3) 代物弁済も可|ただし譲渡所得への課税に注意
なお、遺留分侵害額請求を受けた人が精算金を準備できない場合には、当事者同士の合意さえあれば、従来の遺留分減殺請求のケースと同様に、現物による代物弁済を行うことも可能です。
ただし、代物弁済による遺留分の精算を行う場合、税務上、所有権の移転時点で譲渡所得への課税が生じ得る点に注意が必要です。
特に、不動産を代物弁済するケースで、取得時よりも地価等が上昇していると、譲渡所得課税が発生する可能性が高いので、事前に税理士等の専門家に取り扱いを確認しましょう。
2.遺留分計算の基礎に算入する生前贈与の期間を限定
遺留分を計算する際の基礎となる財産の金額は、原則として以下の計算式によって求められますが、(民法1043条1項)特別受益とされる生前贈与については例外的に、遺留分計算の基礎財産に算入されるケースがあります。
遺留分計算の基礎財産
=相続開始時点の財産額+遺贈額-相続開始時点の負債額
相続法改正の前と後では、特別受益を遺留分計算の基礎財産に算入する条件について、ルールの変更が行われました。
特別受益に当たる生前贈与とはどういうものなのか、遺留分計算に算入する特別受益の条件についてどのようにルール変更がなされたのかを解説します。
(1) 特別受益に当たる生前贈与とは
特別受益に当たる生前贈与とは、被相続人が相続人に対して行った、以下のいずれかの生前贈与を指します。
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
 [参考記事]
特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説
[参考記事]
特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説
(2) 改正前|特別受益を無制限に算入
相続法改正前は、これらの特別受益に当たる生前贈与は、無制限に遺留分計算の基礎財産に算入することになっていました。
しかし、あまりにも遠い過去にさかのぼって特別受益の有無を調査することは困難であり、また被相続人の意思にも沿わない可能性が高いという問題が指摘されていました。
(3) 改正後|相続開始前10年以内の特別受益に限り算入
相続法改正後のルールでは、相続人に対する特別受益を遺留分計算の基礎財産に算入すべき期間は、相続開始前10年以内に限定されました(民法第1044条3項、1項)。
特別受益の算入期間が合理的な期間に限定されたことにより、相続に関する被相続人の意思を尊重し、さらに遺産調査の手間を軽減する効果が期待されます。
【遺留分侵害を知って行われた贈与は、引き続き無期限に算入】
ただし、相続法改正後であっても、特別受益に当たる生前贈与の贈与者と受贈者が、当該生前贈与が遺留分権利者に損害を与えることをともに知っていた場合には、上記の10年間の期間制限は適用されません(民法第1044条3項、1項)。
つまりこの場合、相続法改正前のルールと同様に、無制限に特別受益に当たる生前贈与が遺留分計算の基礎とされるので注意が必要です。
3.負担付贈与に関する遺留分ルールの明確化
贈与の見返りとして、受贈者が何らかの義務を負担する負担付贈与の金額を、遺留分計算の基礎財産にどのように算入するかは、相続法改正前には見解が分かれていました。
しかし、今回の相続法改正によって、この点に関するルールが明文化されました。
(1) 改正前|一部算入説と全部算入説が対立
相続法改正前には、負担付贈与をどのように遺留分計算の基礎財産に含めるかについて明確なルールがありませんでした。
そのため、以下の「一部算入説」と「全部算入説」が対立していました。
①一部算入説
負担分を控除した後の残額のみ、遺留分計算の基礎財産に含める説
②全部算入説
負担分を控除せず、贈与の目的物価額の全額を遺留分計算の基礎財産に含める説
(2) 改正後|一部算入説を明文化、解釈の違いを解消
相続法改正後は、遺留分計算の基礎財産に含める負担付贈与の価額を「その目的の価額から負担の価額を控除した額とする」(民法1045条1項)と明記されました。
つまり、明示的に「一部算入説」が採用されたことにより、上記の曖昧さ、不透明さが立法的に解決されたことになります。
4.不相当な対価による有償行為に関するルールの変更
被相続人が生前不相当な対価で財産を推定相続人に譲渡した場合における、対価の精算方法のルールも相続法の改正に伴い変更になりました。
例えば、被相続人が生前、あまりにも安い対価で不動産を(推定)相続人に譲渡した場合は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、「不相当な対価をもってした有償行為」とみなして、実質的に「贈与」とみなし、遺留分計算の基礎財産に算入します(民法1045条2項)。
こういったケースでは、対価分の精算が必要となりますが、この対価清算のルールが相続法の改正前後でどのように変更になったのかご説明します。
(1) 改正前|現物返還による減殺、その後対価を償還
相続法改正前のルールでは、いったん現物返還によって遺留分減殺を行った後、対価分を金銭により、遺留分権利者から侵害者に対して償還することになっていました。
相続法改正前は、遺留分減殺請求権が非金銭債権、対価償還請求権が金銭債権という異なる性質を有しているため、両者を分けてそれぞれ精算することが必要でした。
(2) 改正後|負担付贈与とみなし、対価相殺後の金額を金銭で精算
相続法改正により、遺留分侵害額請求権と対価償還請求権は、ともに金銭債権となりました。
そのため、両者をあらかじめ相殺したうえで、一括的に精算する方法を取れるようになりました。
5.遺留分権利者の債務を弁済した場合に関するルールの変更
遺留分権利者が負担すべき債務を、遺留分侵害者が代わりに弁済していたケースの清算ルールについても、相続法の改正の前後で変更されています。
相続財産中の債務は、一部の相続人が一括して弁済するというケースも多いところです。
その結果として、遺留分権利者の債務負担分を、侵害者が代わりに弁済していることもあり得ます。
この場合、遺留分の精算に関しても、上記の弁済に係る求償関係が反映・精算されるべきです。
では、改正の前後で、どのようにルールが変更されたのでしょうか。
(1) 改正前|現物返還による減殺、別途求償権を行使
相続法改正前は、いったん現物返還によって遺留分減殺を行った後、求償分を金銭により、遺留分権利者から侵害者に対して償還するとされていました。
(2) 改正後|求償分を自動的に減額することを請求可能
これに対して改正後は、債務を代わりに弁済してあげた侵害者が、遺留分権利者に対して意思表示を行うことにより、自動的に求償分を遺留分侵害額から減額することが認められました(民法1047条3項)。
考え方としては「不相当な対価をもってした有償行為」に関する改正と同様で、遺留分に関する権利が金銭債権化されたことに伴い、求償に関する精算を一括で行えるようにして、手続きの簡便化を図ったものになります。
6.相続法の改正前後で変わらない遺留分の消滅時効
一方で、相続法の改正前後で変わらない点もあります。それが、遺留分の請求権に関する消滅時効です。
改正前においては、遺留分減殺請求権は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったときから1年行使しないときは、時効によって消滅する」としていました(旧民法1042条前段)。
一方、改正後においても、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」としています(民法1048条前段)。
遺留分の請求権に関する除斥期間についても、同様に「相続開始の時から十年を経過したとき」です(旧民法1042条後段、民法1048条後段)。
7.遺留分ルールを変更する改正相続法はいつから適用される?
上記の各点を内容とした、改正相続法による遺留分ルールの変更は、2019年7月1日からすでに施行されています。
改正前・改正後のどちらのルールが適用されるかは、相続が開始したタイミングによって決まります。
- 2019年6月30日以前に開始した相続:改正前のルールを適用
- 2019年7月1日以降に開始した相続:改正後のルールを適用
どちらのルールが適用されるかわからないという方は、弁護士にご確認ください。
8.まとめ
遺留分に関するルールは、今回の相続法改正によってかなり使い勝手が改善されました。
もし遺言書や生前贈与がご自身にとって不利な内容であり、相続に関して冷遇されているのではないかと疑念を抱いた方がいらっしゃれば、泉総合法律事務所にご相談ください。
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)の可否について法的な分析を行い、相続人としての権利を回復するための方策についてアドバイスを差し上げます。